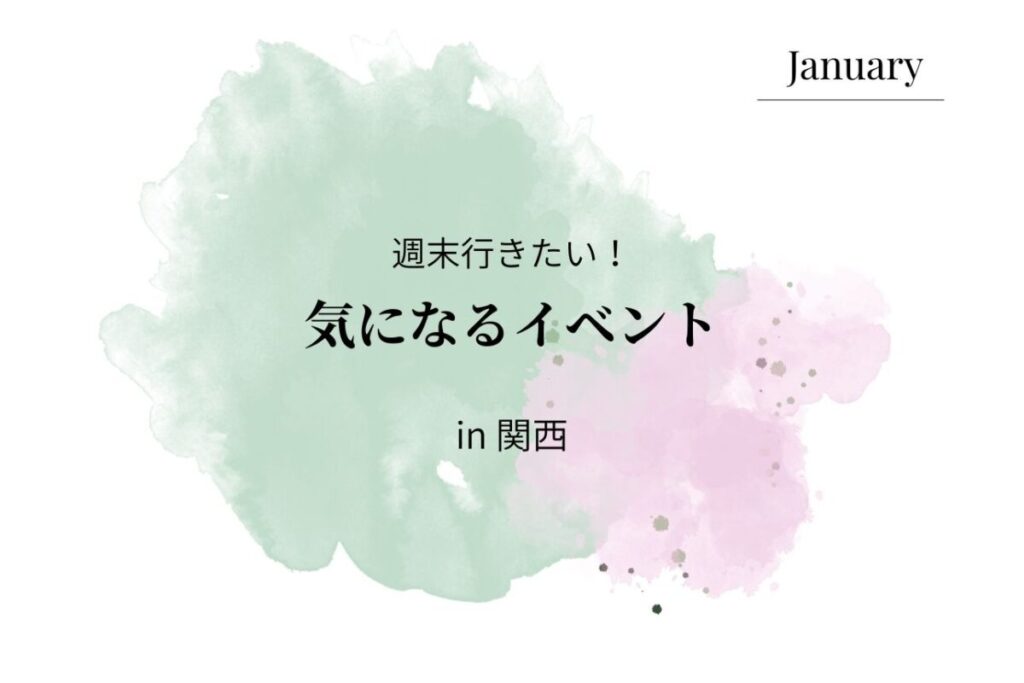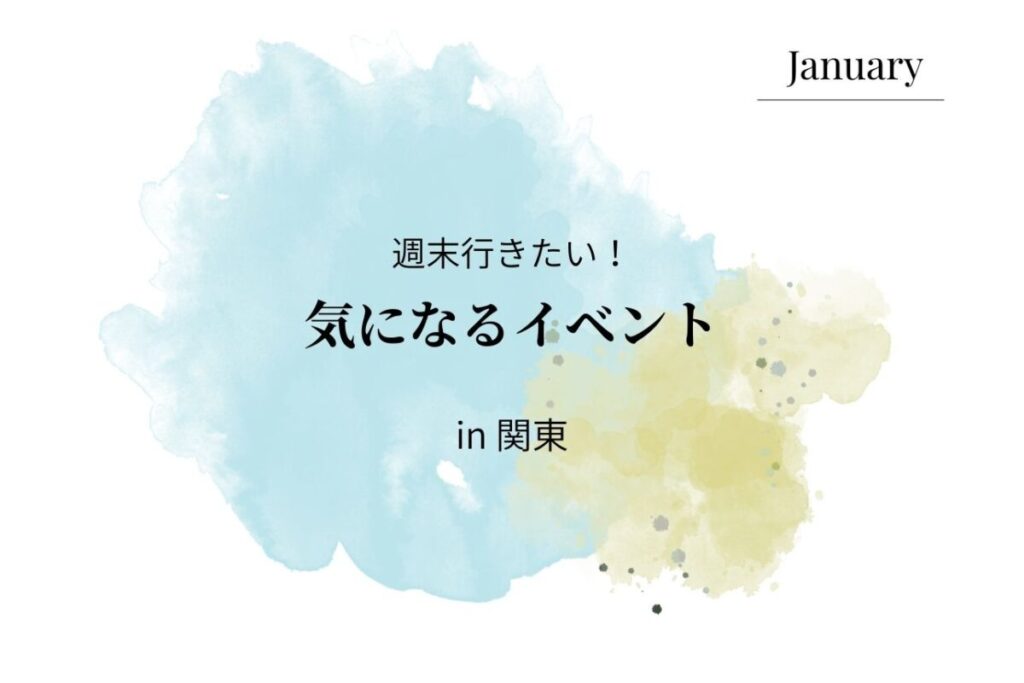近年、豪雨や猛暑により、河川氾濫や土砂災害、さらには停電・ライフラインの寸断など身近に感じる危険が増えています。
非常用バッグの中身を見直す、家族との連絡方法を確認する、家具の固定をする。このように、日々の暮らしに少しの工夫と話し合いを取り入れるだけでも、いざという時の安心感に繋がります。
夏の終わりを迎えるこの時期こそ、防災への意識を高めるため、「防災の日」について知ることからはじめてみてください。
「防災の日」とは?いつ?
「防災の日」は、国民の防災意識を高めるために定められた全国的な記念日です。毎年9月1日が防災の日として制定されています。防災の日を含む8月30日から9月5日は防災週間とされています。
地震や台風など自然災害の多い日本において、災害はいつどこで起きても不思議ではありません。だからこそ、日頃からの備えが命を守ることに繋がります。
「防災の日」は、自分と家族の命を見直す日として、生活の中で少し立ち止まり、防災への意識を再確認するきっかけになります。
ここから、防災の日の由来について詳しくみていきましょう。
「防災の日」が 9月1日の理由は
防災意識を高めるための防災の日ですが、なぜ9月1日なのでしょうか。
その理由は、1923年9月1日に起こった関東大震災にあります。死者約10万5,000人ともされる未曾有の大震災。この被害を後世に伝え、防災意識を共有するために制定されました。
また、この日は立春から数えて“二百十日”にあたり、台風が本格化する時期とも重なります。1959年の伊勢湾台風の甚大な被害も「防災の日」制定のきっかけとなり、自然災害への心構えを育む意図が込められています。
1960年6月に「防災の日」として正式に制定され、以降、毎年全国で防災週間(8月30日〜9月5日)を中心に防災啓発活動が行われるようになりました。
「防災の日」は毎月ある? 広がる習慣化の工夫
「防災の日」は1年に一度ですが、多くの家庭や自治体、企業では「毎月1日は備蓄チェックの日」「定期的に避難ルートを家族で確認」など、独自の防災ルールを設けています。
こうした取り組みは、防災への意識を日々の暮らしの中に定着させる効果があり、小さなアクションの積み重ねが安心の備えに繋がります。
例えば、ローリングストックの習慣づくりや、防災アプリの通知設定、避難経路の確認など、月ごとのチェックを意識するだけで非常時の備えが整ってきます。
災害に備えることは決して特別なことではなく、できることから少しずつ始めていくことが大切です。
「防災の日」にできる7つのチェックリスト
「防災の日に何をしたらいいのかわからない」という方も多いかもしれません。しかし、少し見直しするだけでも大きな安心に繋がります。
大切なのは、できることから始めること!
特別な知識や道具がなくても、家族との話し合いや持ち出し袋のチェックなど、今すぐにでも始められる備えがあります。
ここでは、内閣府や自治体の防災ガイドを参考に、日々の暮らしの延長として取り組める防災チェックリストをご紹介します。
| アクション | 内容 |
| 避難ルート確認 | 災害時移動ルートやハザードマップを家族で確認する |
| 非常用持ち出し袋点検 | 食品、飲料水、携帯充電器、救急薬、マスク、電池、衛生用品など。賞味期限も確認する |
| 災害時の家族連絡ルール | 災害伝言ダイヤルなどの使い方を確認。集合場所なども決めておく |
| 耐震・防災グッズを見直し | 家具固定・ブレーカーの位置・消火器の設置や使用期限などを確認する |
| 防災アプリ登録と通知設定 | 気象庁や自治体の速報を受け取れるように事前に準備する |
| 身近な防災訓練の確認 | 自治体の訓練日や近隣でのイベント情報を調べ、参加する |
| 誰でも見直せる備蓄整理 | 備蓄品を書き出して家族と共有。高齢者や子どもでも気付きやすい状況を作る |
全国で行われる防災関連のイベント紹介
「防災の日」には、全国の自治体や企業、学校などでさまざまな取り組みが行われています。避難訓練やワークショップを通じて、防災への理解を深めたり、家庭での備えを考え直すきっかけにもなるでしょう。
地域によっては子どもから大人まで楽しみながら学べるイベントが企画されていることもあり、防災がより身近に感じられる機会になります。
ここでは、2025年に予定されている防災イベントの事例をいくつかご紹介します。
● ぼうさいこくたい2025 in 新潟
2025年9月6日(土)〜7日(日)、新潟市朱鷺メッセで開催予定の日本最大級の防災イベント。行政・企業・地域が連携し、防災・減災を総合的に学べる場です。展示やワークショップ、地域との連携事例など、家族で訪れて楽しみながら備えるヒントが得られます。
https://bosai-kokutai.jp/2025/
● 防災フェアinお台場
2025年10月4日(土)〜5日(日)、東京・お台場で開催される体験型イベント。起震車、VR体験、災害時車両展示、自衛隊・消防の活動紹介、防災食配布など、実際に触れて学べる内容が魅力です。
● 全国防災キャラバン(イオンモール)
イオンモールとボーイスカウト日本連盟による親子向けのイベント。各地モールで開催され、地域と一体になった防災体験を通じ、子どもも保護者も楽しみながら防災知識を学べます。
https://online-event.aeonmall.com/bousai-caravan
その他、地方自治体や地元企業主催の防災ワークショップや講座、防災訓練なども夏〜秋にかけて多く企画されています。
インターネットで「〇〇市 防災フェスタ 2025」などで検索が可能です。お住まいの地域でも開催されているか、ぜひチェックしてみてください。
「防災の日」をきっかけに日々の暮らしへ広げよう
「防災の日」は、ただの記念日ではありません。一年に一度、備えを見直す大切な機会です。
そして一過性の習慣ではなく、日常の一部として“もしもの備え”を育む意識に変えていくことが重要です。
小さな話し合いと確認が、安心の輪へと繋がります。9月1日をきっかけに、自分なりの防災のルールや習慣をつくってみませんか。
参考:
自然災害への備えは万全ですか?チェックしてみよう!|内閣府
災害が起きる前にできること|首相官邸
災害時の心がまえ|東京海上日動