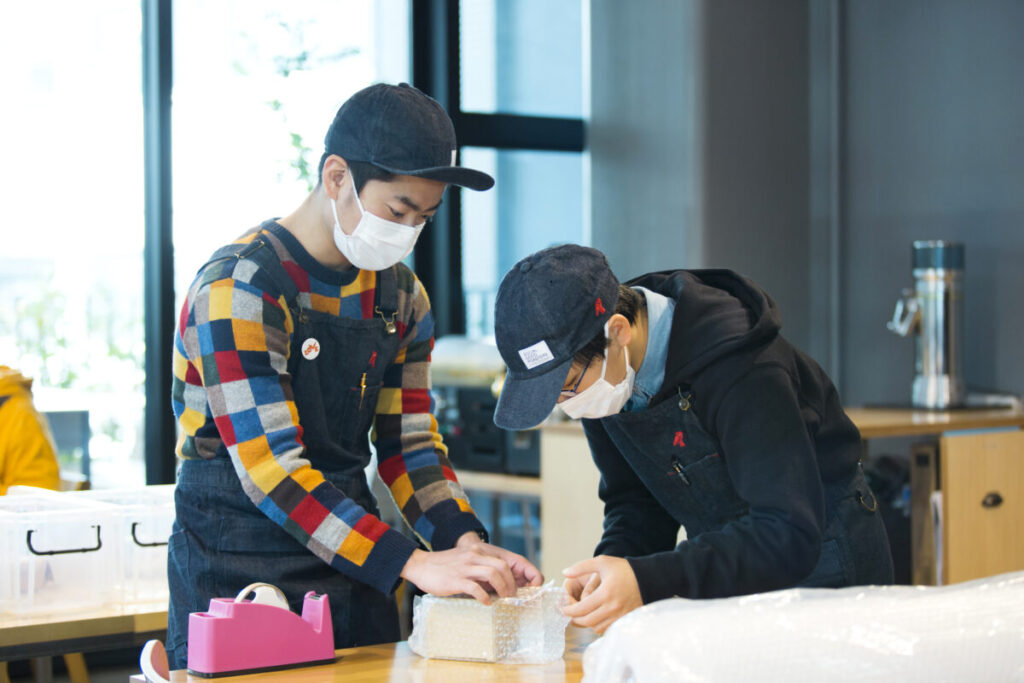INTERVIEW– category –
-

モノが少ないからこそ見える豊かさ―DAR AMALカモチリナさんとモロッコ女性たちが織る物語
-

繋がりが生む豊かさ。ウガンダ発バッグブランド・RICCI EVERYDAY仲本千津さんが大切にする心の余白
-

「映像体験が分断をなくす」映像作家の久保田徹さんが語るドキュメンタリーの力
-

「今の世界を納得して生きたい」グランプリ受賞、内田英恵さんのドキュメンタリーはなぜ多くの共感を呼ぶのか
-

「相手の目線に立つことが強い社会への第一歩」福祉団体ビーンズが目指すもの
-

「Less is moreに生きる」 久保まゆみさんが考える豊かさ
-

夜パンB&Bカフェが新オープン。枝元なほみさんが目指す「繋がる社会」とは
1