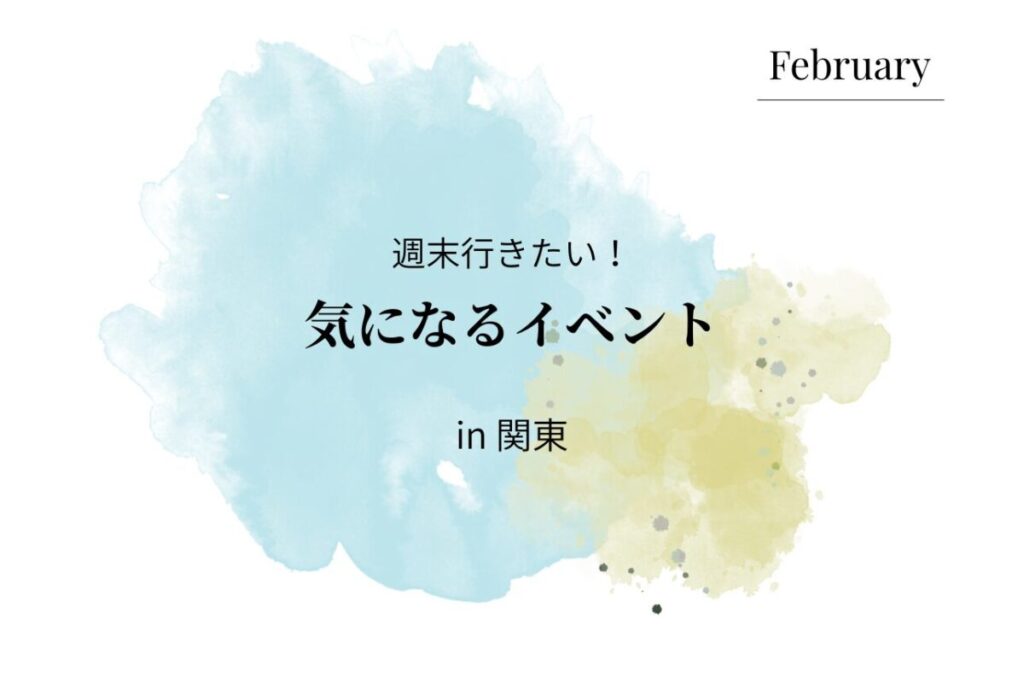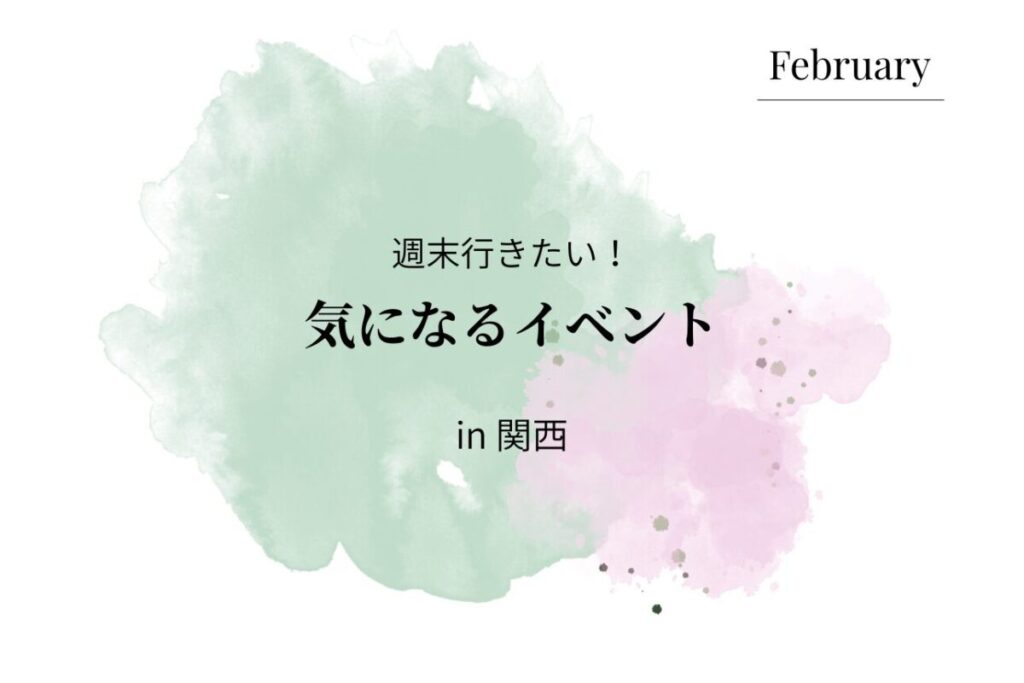世界で深刻さが増す水不足。日本に住んでいる私たちには無縁だと思うかもしれませんが食糧の輸入大国である日本は、間接的に生産地の水を消費しています。それが世界各地の水不足に繋がっているかもしれません。
この記事では、私たちの水の消費量がわかるバーチャルウォーターについて説明していきます。
バーチャルウォーターとは

バーチャルウォーター(仮想水)は、ロンドン大学名誉教授のアンソニー・アラン氏が初めて提唱した概念です。バーチャルウォーターとは、「食料を輸入している国において、仮にその輸入しているものを自国で生産したら、どのくらいの水の量が使われるのか」を示すものです。
食料を栽培する上で、水は欠かせません。食料を輸入しているということは、言い換えると間接的に水も輸入しているということなのです。バーチャルウォーターは、輸入することで水をどのくらい消費しているかをわかりやすく示してくれます。
世界中の国々で水不足が大きな問題に
バーチャルウォーターが注目される背景には、深刻な水不足があります。
地球上の水のうち、人間が生活・飲料として使用できる淡水は2.5%しかありません。うち70%は氷河が占めており、残りの30%のほとんどが地下水だと言われているので、私たちにとってもともと水は非常に貴重な資源です。
そこから、1960年代ごろには世界の産業化や人口増加などで、世界で使用される水の量が増加。気候変動による大雨や干ばつのほか、都市開発や森林伐採が進むことによる水源の破壊も水不足が進む大きな要因とされています。
2019年時点、世界で水資源が貧しい地域に住む人口は約40億人。2050年までには、50億人まで膨れ上がるという予想もあり、水不足はますます深刻になっていくとされています。
一例ですが、アメリカの中西部では農地の灌漑用水に地下水を使ってきましたが、その地下水を使いすぎたことにより、地下水脈が枯れ始めています。
地下水の輸出用が多く、農業にも地下水が多く使われるインドでは、地下水が年々減少しています。場所によっては、日々の生活用水を手に入れるのにも苦労している人々が増えているのが現状です。
世界の人口の4分の1はウォーターストレスの高い状態
すでに述べたように、人口増加や気候変動で世界的に水不足が進んでいますが、元々水資源が貧しい地域や、経済的な理由などで水インフラが整っていない地域では問題はさらに深刻です。
世界資源研究所(World Resource Institute)の調査よると、世界の人口の約4分の1が住む17カ国の国で、非常に高いウォーターストレスにさらされているとされています。ウォーターストレス(水ストレス)とは、水の需要が供給を上回っており、日常生活において、水不足が原因で不便さを感じる状態のことです。
水資源の利権を争う戦い

貴重な水資源は、ときには争いに発展します。
現在も、アジアやアフリカ、南米など、世界の様々なところで水の所有権や水資源の配分を巡って、水紛争が引き起こされているのです。
例えば、インダス川周辺の地域では、農業などの主要産業への利用や人口増加のため水資源の重要性が高まっており、パキスタンとインドの間で衝突が繰り返されてきました。
両者が核保有国であることも、緊張状態が続く一因となっていると言われています。
水の問題は人権問題と直結していることを忘れてはなりません。
国連が掲げるSDGs目標6「安全な水と衛生を世界に」では、2030年までに水資源の持続的確保のため水資源の水質改善や、国境などの垣根を超えた水資源の管理に協力することなどを呼び掛けています。
身近な食品のバーチャルウォーター

では、バーチャルウォーターに関わる品目はどのようなものがあるのでしょうか。ここからは3つの食材を例に、それぞれを輸入した場合、どれくらいのバーチャルウォーターが使われているのか見ていきましょう。
炊いたご飯
お米を輸入した場合、炊いたご飯1杯(75g)のバーチャルウォーターはおよそ277ℓ。輸入されたお米は、お茶碗一杯のご飯にも多くの水が使用されています。
牛肉
牛肉100gあたりのバーチャルウォーターは20600ℓ。「牛肉の消費を減らせば地球環境問題に貢献できる」とよく言われるように、牛を育てる上での穀物や水の消費量は膨大です。エサとなるトウモロコシを栽培するのにたくさんの水が必要となり、牛一頭を飼育するのに、そのトウモロコシが大量に必要になります。
コーヒー
コーヒー1杯に対するバーチャルウォーターは210ℓ。飲み物のなかでは群を抜いてバーチャルウォーターの値が高いのがコーヒーです。コーヒー一杯に対して、500mlのペットボトル420本もの水が必要になります。
その他、食材にどのくらいのバーチャルウォーターが使われているかどうかは、環境省の仮想水計算機で簡単に算出することができます。
日本のバーチャルウォーターの現状

日本で生活していると、日常の生活の中で水不足に陥ることはほとんどないので、水不足の問題は、直接私たちに影響がないように思うかもしれません。
しかし、日本は、カロリーベースの食料自給率から見ると、実に6割以上を輸入の食品に頼っています。そして、その輸入によって、見えないところでたくさんの水が消費されているのです。
環境省によると、2005年に海外から日本に輸入されたバーチャルウォーター量は、約800億m3であり、その大半は食料に起因。これは、日本国内で使用される年間水使用量と同程度にあたります。
わたしたちは何気なく消費している外国産の食物や製品をつくるために消費された水が、誰かの生活や地球環境を脅かしているかもしれず、水不足問題は決して他人ごとではありません。
私たちがこれからできること

では、私たちができることはあるのでしょうか。
日々の生活では、以下のようなアクションでバーチャルウォーターの量を減らすことが期待できます。
・地元で生産された野菜などの食品を購入する
・レストランを利用するときは地産地消のお店を選ぶ
・大豆ミートなど代替肉を取り入れ、肉類の消費を減らす
一人ひとりの生活スタイルに合った方法で地産地消を楽しむことが大切です。
関連記事:実はこんなにたくさん!地産地消のメリットとは
関連記事:新たな食の選択肢、プラントベースとは?進化した代替肉や植物性ミルクが続々登場
今回は輸入しているものの水の消費量を知ることができるバーチャルウォーターについて紹介しました。
まずは日々の生活で水を輸入し消費しているということを知ることから始め、世界の水不足問題に目を向けて、できることを見つけてみてはいかがでしょうか。
【参考】
環境省 – 仮想水 https://www.env.go.jp/water/virtual_water/index.html