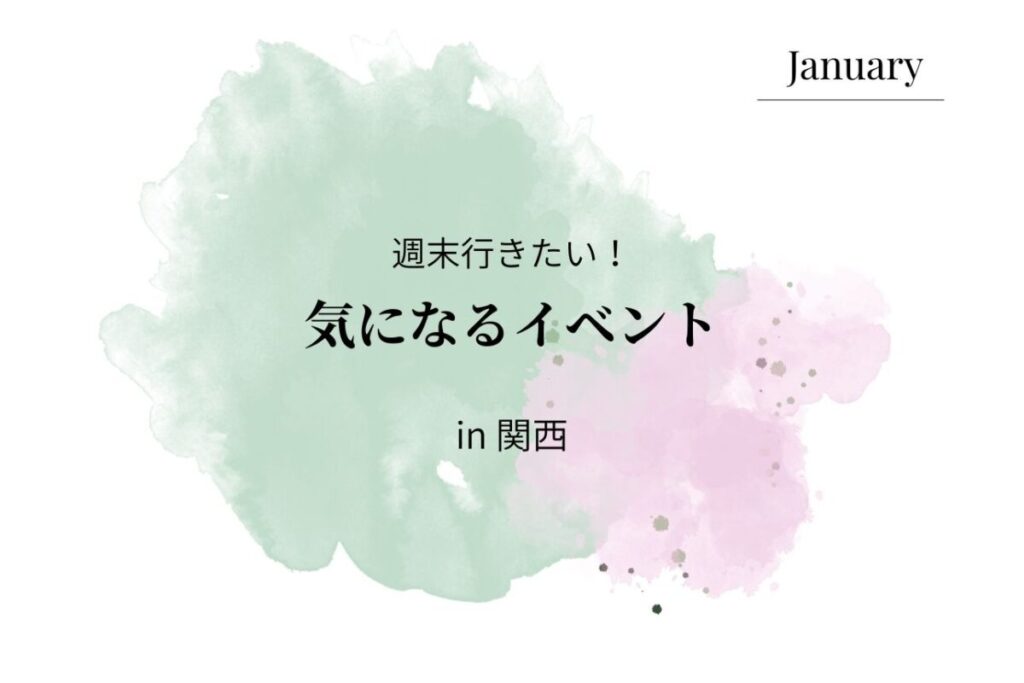私たちの住むこの地球上には、多種多様な生き物が共生しています。ヒトを含め、生き物は相互に深くかかわり合い、支え合いながら生きてきました。
しかし今、様々な理由から生物多様性のバランスが崩れています。持続可能な地球のため、この生物多様性を守ることが急務とされているのです。
この記事では、生物多様性とは何か、そして私たちにできることは何かをご紹介します。
生物多様性とは

生物多様性とは、さまざまな個性を持つ生き物たちが繋がり合い、バランスを保った状態を指します。
地球上には、目に見えない菌類をはじめ昆虫や哺乳類など、さまざまな生き物が生息しています。
未知の生き物を含めると、およそ3,000万種の生き物がいるとされており、環境の変化に適応しながらこれまで進化してきました。
どの生き物にも個性があり、お互いに支え合って生きています。その豊かな生き物たちの個性と繋がりを生物多様性というのです。
人間は生物多様性の恩恵を大きく受けている!
例えば、土の中に棲む生き物が落ち葉や動物のフンを食べ、分解することで土壌が豊かになります。豊かな土壌は、植物が育ちやすい環境をつくります。そして植物は太陽の光を浴び、雨水を吸収し、養分を蓄え成長します。そして人間がそれらの植物を食べます。
このように、すべての生き物は密接に関わり合って生きています。一つの種が消滅し、その生き物の役割が失われれば、こうした生物間の繋がりが途絶えてしまいます。
生物多様性とは単に「動植物の種類が多ければ良い」ということではありません。生き物たちの、相互の繋がりが維持されることを示す言葉なのです。
生物多様性が失われるとどうなる? 日本の例から見てみよう
かつては日本にもオオカミが生息していました。絶滅した要因は所説ありますが、自然環境の変化や、人間が家畜への被害を恐れて駆除を推奨したことが挙げられます。
日本でオオカミが絶滅したことで、家畜への被害は無くなりました。しかし今度は、それまでオオカミが餌にしていたシカやイノシシが増え、農作物に被害をもたらすようになったのです。
自然のサイクルのピースが一つ欠けるだけで、環境に大きな影響を与えます。つまり、生物多様性は、私たち人間の都合だけで消失させて良いものではないのです。
生物多様性が今、危機的な状況に

前述の通り、地球上にはおよそ3,000万種の生き物が生息しています。しかし、現代では人間の経済活動の影響で生息数が減少し、絶滅の恐れがあるとされる種が多数あります。
2025年3月の時点でIUCN(国際自然保護連合)の「レッドリスト(正式名称:絶滅のおそれのある種のレッドリスト)」には、絶滅危機種に4万7,187種の野生生物が記載。
日本国内では、2020年版の環境省のレッドリストに、絶滅の恐れのある3,716種が登録されています。
ここで問題なのが、「一度絶滅した生き物は二度と復活しない」ということ。例えば、恐竜は約6600万年前には絶滅したとされています。およそ1億6,000万年もの長い間、繁栄していたにも関わらず、絶滅して以降その姿を現していません。
絶滅の危機に瀕している生き物の例
実際にどのような生き物が絶滅の危機にさらされているのでしょうか。一例を見ていきます。
① コアラ
オーストラリアで発生している、地球温暖化による森林火災の深刻化が要因の一つです。また、地球温暖化がもたらしたと考えられる干ばつが、コアラの餌であるユーカリの森を枯死させていることも大きな要因となっています。
② ジャイアントパンダ
かねてより、開発に伴う山林の消失で、ジャイアントパンダの生息地は奪われてきました。加えて、近年は地球温暖化の影響も大きく、パンダの餌である竹が気温や気候の変化により発芽できなくなる恐れがあると懸念されています。
③ アオウミガメ
日本では沖縄諸島や小笠原諸島など、温暖な地域で見られることで知られるアオウミガメ。実は1980年代から絶滅が危惧されています。絶滅危機の要因はさまざまで、海洋汚染、卵の乱獲、産卵場所である砂浜の開発などが指摘されています。
生物多様性と私たちの経済活動の関係

生き物が絶滅する原因のほとんどは「人間の経済活動」によるものです。人間の活動によって生き物が絶滅するスピードは、人の影響がない場合と比べ約1,000倍も速いといわれています。
生物多様性の減少に影響を与える要因をいくつかご説明します。
① 開発や乱獲
過度な森林伐採、沿岸部の埋め立てなどの開発行為により、生き物の生息地が減少しています。また、観賞や販売目的での乱獲が行われ、象牙の密漁によってアフリカゾウの存続が危ぶまれるなど、野生動物に大きな影響を及ぼしています。
② 里山の手入れ不足
かつての日本は農業や林業など、自然にあるものを手入れしながら生活に役立てていました。しかし、生活様式が変化した現代では、人の手が入らず荒廃した里山が増加。手入れされない里山は植生が乏しく、動植物が育ちにくい環境になっています。
③ 外来種の持ち込み
人の手によって持ち込まれた外来種が在来種の生息場所を奪っています。他にも、外来種による在来種の捕食や交雑も生態系に大きな影響を与えています。
④ 気候変動などの地球環境の変化
温暖化により、平均気温が1.5~2.5度上がると、氷が溶け出す時期が早まる、高山帯が縮小する、海面温度が上昇するなどの問題が起こります。それにより、20~30%の動植物における絶滅リスクが高まるといわれています。
人間の影響で、日本の野生動植物の約3割が絶滅しようとしています。豊かな自然と生き物を守るためには、私たちが行動しなければなりません。
生物多様性のために私たちができること

このまま私たちが何も対策をしなければ、豊かな自然が失われ、多くの生き物が瞬く間に絶滅してしまうでしょう。冒頭でもお伝えした通り、私たち人間は、生物多様性の恩恵を大きく受けています。豊かな自然と生物多様性を守るために、私たちにできることは何でしょうか。
① 買い物の際は「本当に必要か」よく考える
SNSやメディアの影響で、私たちは日々、購買意欲を掻き立てられています。次々に発売される便利グッズや写真映えする食べ物など、例を挙げれば切りがありません。そこで、何か欲しい物があるときは「本当に必要か」「代わりになる物はないか」と少しだけ考えてみましょう。買っては捨てる、を繰り返せばごみが増え、資源を無駄にし、二酸化炭素を増やすことになります。
② 環境に配慮した商品を使用する
環境に配慮した商品には「エコマーク」が付いていることはよく知られています。他にも、近年は環境への意識の高まりもあり、さまざまなマークが存在します。
買い物の際、それらの環境ラベルが付いた商品を購入することが重要です。環境省の「環境ラベル等データベース」では、それぞれのマークがどんな商品に表記されているのか調べることができます。ぜひ参考にしながら、環境に配慮された商品を購入してください。その企業を応援することにもなり、結果的に環境に良いサイクルが生まれます。
③ ボランティアに参加する
大規模な活動に参加する必要はありません。町で行う「シティクリーン」や「ビーチクリーン」も、環境に優しい立派なボランティアです。
ビーチクリーンは、ダイビングショップやサーフィンショップなど、海辺で活動を行う店舗が実施することも増えています。観光と併せてできるので、気軽に参加しやすい活動の一つです。
「アクティボ」では、国内外のボランティアの募集案内を掲載しています。動物関係や農業関係など、テーマごとにさまざまな活動を掲載しているので、どんなボランティアがあるのか調べてみるのもおすすめです。
④ 自然保護活動を行う団体に寄付する
ボランティアに参加するのはハードルが高いという方は、自然保護団体への寄付はいかがでしょうか。団体により金額や方法はさまざまですが、会員にならずとも、1,000円前後で1回からの寄付が可能なところもあります。
各団体の活動を調べて、共感したところにぜひ寄付をしてみてください。
【自然保護団体の一例】
・WWFジャパン https://www.wwf.or.jp/
・日本自然保護協会 https://www.nacsj.or.jp/
・グリーンピース・ジャパン https://gooddo.jp/nf/greenpeace-4pc/
豊かな自然を守るために、できることから始めよう!

この先、生物多様性が維持されるかどうかは、私たち一人一人の行動にかかっています。
何か一つからで良いので、まずは気軽にご紹介したアクションから始めてみてはいかがでしょうか。
参考:
https://biodiversity.pref.fukuoka.lg.jp/kids/
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/5777.html
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/biodiv_crisis.html