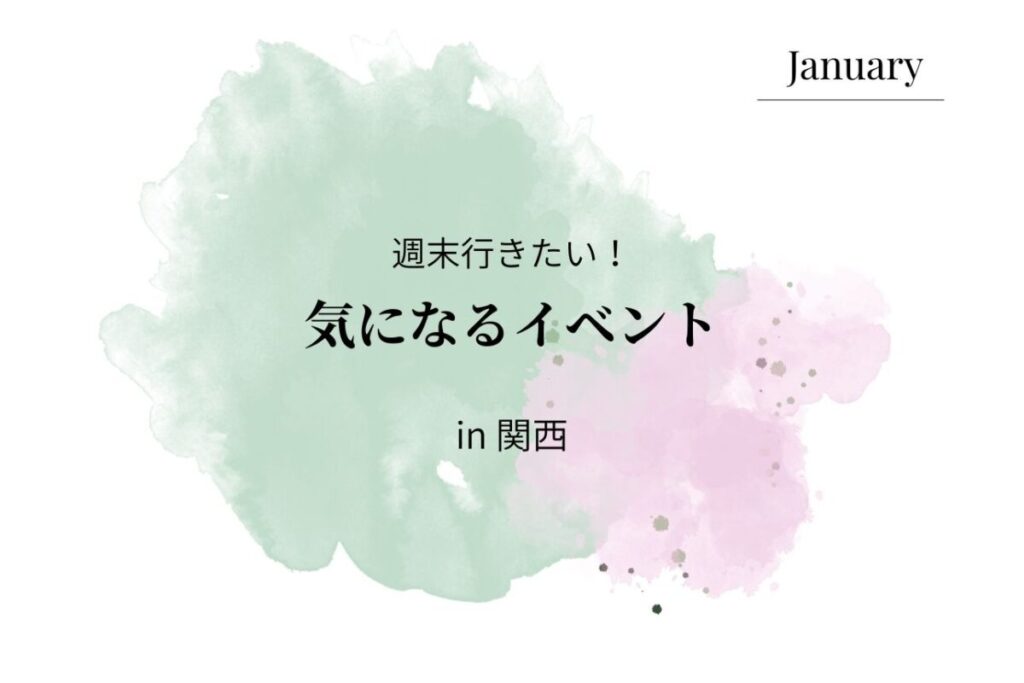「多文化を受け入れよう」と言うのは簡単ですが、実際に異なる価値観を持つ人々と接すると、その難しさを実感したことはありませんか。
言語や価値観が違えば、自分にとっての当たり前は通用しなくなります。そんなときに大切なのは、どの価値観に対しても「優劣」や「正誤」といったジャッジをせずに、お互いに歩み寄る機会をつくることです。
スウェーデンの「ドリーム・オーケストラ」では、約25カ国からあつまったメンバーが共に音楽を奏でています。様々なバックグラウンドを持つ人々がいるなか一つの団体として活動するドリーム・オーケストラから、多文化共生のヒントを深掘りしていきます。
ドリーム・オーケストラ、設立のきっかけ

ドリーム・オーケストラは、難民や移民を中心としたメンバーが集まるスウェーデンのオーケストラです。現在のメンバー数は400人を超え、現地のスウェーデン人も属する多国籍団体として知られています。
オーケストラを立ち上げたのは、ベネズエラ出身バイオリニスト、ロン・デイビス・アルバスさんです。きっかけは2015年、アルバスさんが留学生としてスウェーデンを訪問したときのこと。ストックホルムの駅で、たくさんの若い移民たちが、ひとりきりで駅に降りてくる光景を目の当たりにしたアルバスさんは、紛争や戦争から逃れた人々が安心して過ごせる場所を作りたいと考えました。

翌年2016年、アルバスさんはドリーム・オーケストラを結成。現在は、バックグラウンドを問わず、多様な人が集まり音楽を学びながら心を通わせる場となっています。
さらに、経済的支援や進学支援など、自立サポートを提供。ベツレヘム教会や現地の大学など、さまざまな機関との連携のもと、運営を行っています。
ドリーム・オーケストラから学ぶ多文化共生のヒント

アルバスさんは2024年、地域コミュニティに貢献した人物を選出する「CNN HERO」のトップ5に選ばれました。難民や移民としてスウェーデンにやって来た人々を受け入れ、多文化が共生する環境をつくりあげた背景には、どのような工夫があったのでしょうか。言語・コミュニケーション・文化の共有の視点から、その背景を探ります。
言語以外の情報でコミュニケーションをとる
ドリーム・オーケストラでは、言語だけでなく身体の動きや色をサインとして用いるなどの工夫をしています。
ひとつのチームを形成していくなかで、最も大切なのはコミュニケーション。しかし言語が違うというだけで意思疎通をはかるのは各段に難しくなり、場合によってはお互いを誤解してしまうリスクがあります。
オーケストラでは主に英語で指導をしますが、中には母国語以外の言語を話せないメンバーも。その人たちを取り残さないよう、言語以外の情報を交えながら、日々コミュニケーションを積み重ねているといいます。
明るい雰囲気を大切にする
アルバスさんは、日ごろから明るい態度でメンバーと接し、みんなが安心して集まれる環境づくりに努めてきました。
多文化・多国籍の人々が集うドリーム・オーケストラは、様々な理由から祖国から逃れ、大きな不安を抱えている人々や、新しい生活環境に緊張を覚えている人々もいます。
アルバスさんの明るい態度は、そういった不安や緊張を和らげ、オーケストラを安心して通える場所にしています。
メンバー同士がリラックスして話せる時間を設ける
ドリーム・オーケストラでは、「フィーカ」という時間を設けて、メンバーたちが気さくに交流できる機会を用意しています。
フィーカとは、スウェーデンの習慣で、家族や仲間たちがコーヒーやお菓子を楽しみながら過ごす団らんの場です。こうした時間を設けることのメリットはふたつ。ひとつは、メンバーの社交性を育てること。もうひとつは、メンバー同士が家族のような繋がりを持つことです。
異文化に触れる機会を提供する
ドリーム・オーケストラが使用するのは、スウェーデンの音楽だけではありません。世界各国の音楽を用いることで、お互いの文化を受け入れ合う姿勢を身につけています。
アルバスさんは、メンバーそれぞれが違うバックグラウンドを持っていることについて、こう語っています。「みんなそれぞれ、生まれ育った土地での豊かな経験をしています。ほかの人に伝えられるものもあれば、ほかの人から学べるものもあるんです」
オーケストラの方向性やアルバスさんの言葉は、人々が「おたがいに伝え合い、受け入れ合う」ことの重要性を伝えています。どちらか片方の文化だけを優先する状態は、多文化共生というには不十分なのでしょう。
現地の人々も交える
ドリーム・オーケストラは、若年の難民や移民に安心できる居場所を提供するために始まった活動です。しかし現在は、中高齢のメンバーや現地スウェーデンで生まれ育った人も属しています。
その理由は、人種や出生地などによって人々を分断させないため。特定の人だけの居場所をつくるのではなく、双方が理解し合い共に歩めるように、難民や移民の人々、そして現地の人々がともに体験を共有できる環境をつくっているのです。
多文化共生とは何か。ドリーム・オーケストラから学ぶ、その意味

多文化共生とは、単に国籍や言語が違う人々が同じ空間にいることではありません。一人ひとりが異なるバックグラウンドや価値観を持っていると理解したうえで、双方が歩み寄っていくこと。そして、その関係性のなかで成長していき、それぞれが社会を支える一人として生きていくことではないでしょうか。
ある文化圏で暮らす人々が、別の文化圏から人々を迎え入れるとき、無意識に「受け入れてあげる側」と「受け入れてもらう側」、そして「分け与えてあげる側」と「分け与えてもらう側」といったように、2つの立場に分けて考えてしまいます。
ドリーム・オーケストラも、難民や移民の人々への支援を主な目的としているという点では、「あげる側」と「してもらう側」といった関係性があるのかもしれません。しかし、「学び合う」といったように、双方が自分の持っているものを共有し合う関係性も成り立っています。
また、気楽にコミュニケーションをとる場を設けることで、悩みごとを相談し合う障壁が低くなります。不安や心配を解消できる場にいるということは、自分が生きていくうえでの課題を明確に理解し、そこから脱する方法を探る能力を身につけられる場にいるということ。こうした環境は、受け入れられている側が援助され続けるといった依存的なサイクルを抜け出し、今後の人生を自分の力で歩んでいくためにも重要です。
参考:
DREAM ORCHESTRA|Our history
CNN|His love of music is helping refugees and immigrants build new lives