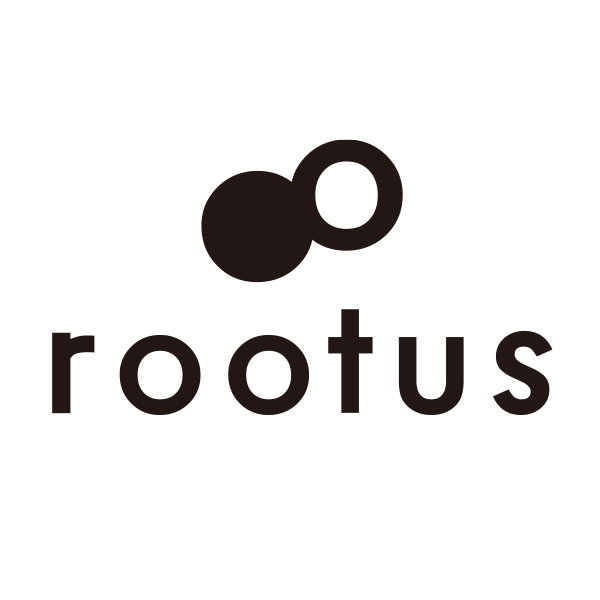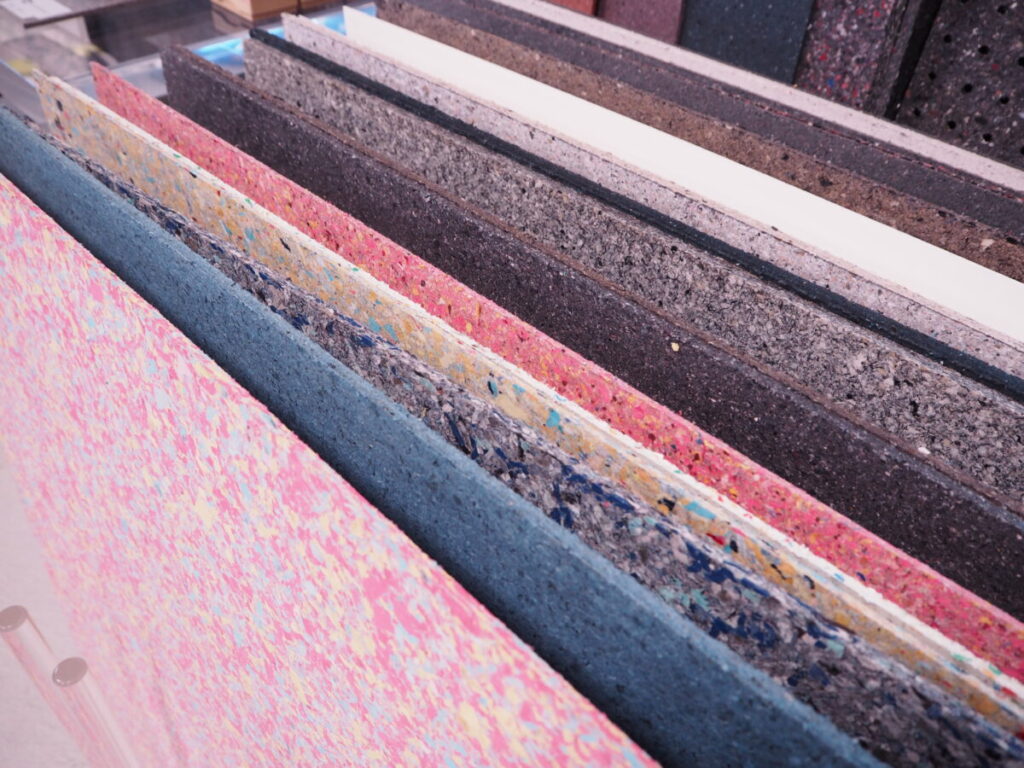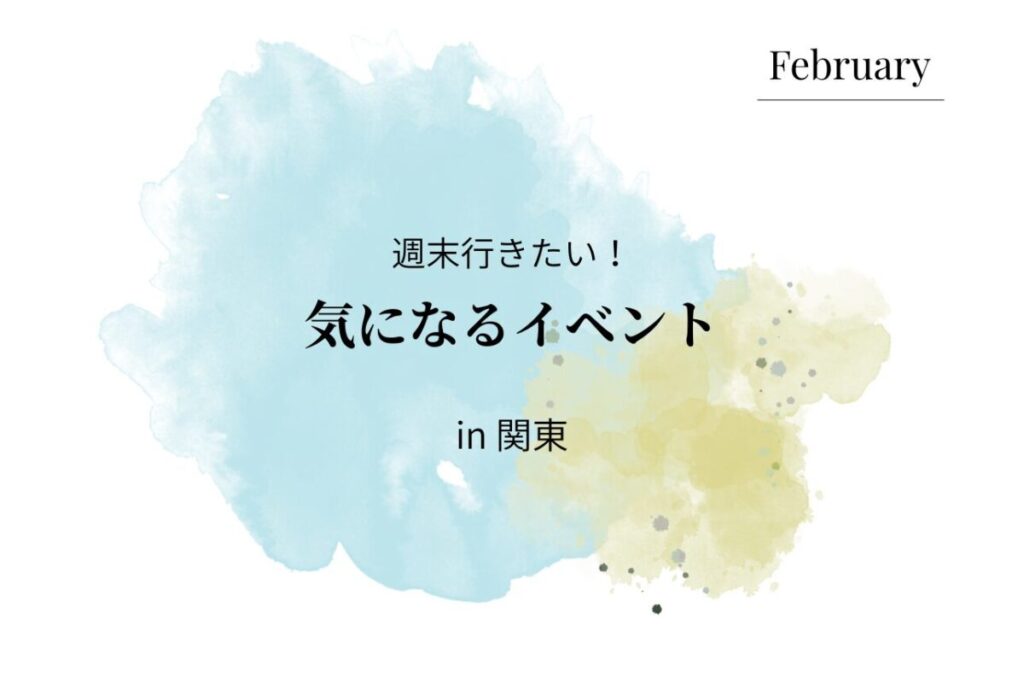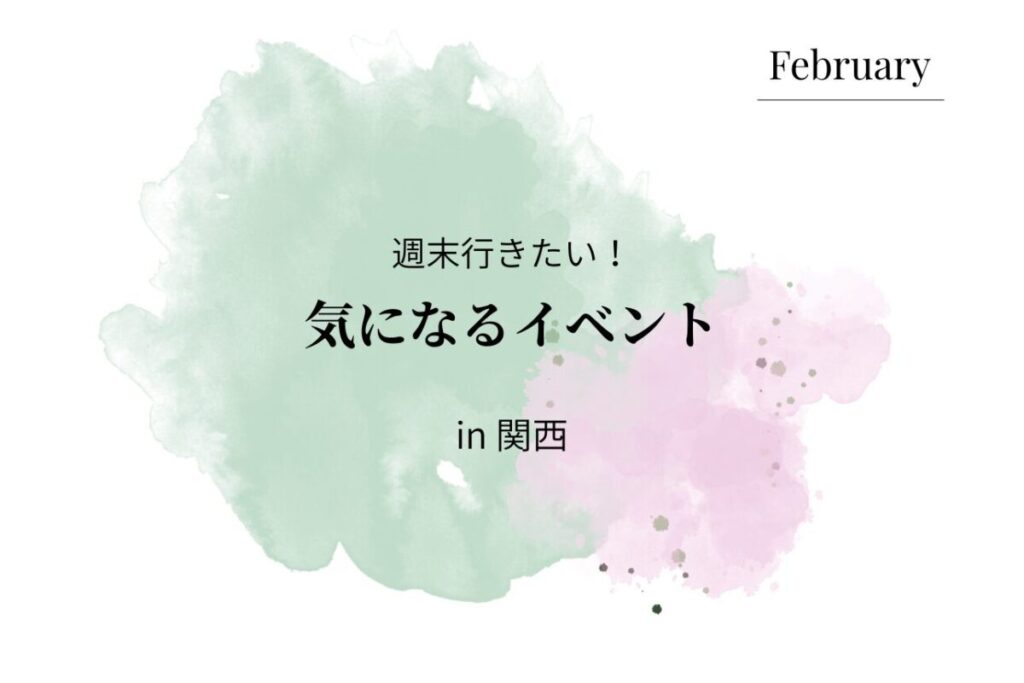月に一回、銀座のスナック「SNACK LIFE IS ROSE GINZA」で開催されるKANPAI for GOOD。お酒を片手に、社会や環境のために活動するゲストのトークを通して参加者みんなで社会に思いを馳せる、ソーシャルグッドなイベントです。
2025 年7月には第四回目となるKANPAI for GOOD拡大版が開催されました。KANPAI for GOODとrootusのコラボレーションによって実現した今回のテーマは、「社会課題解決×教育」です。
それぞれ異業種で子どもや若者の教育現場に携わるゲストのお二人に、教育が社会課題解決にもたらす可能性についてお話しいただきました。
ゲストプロフィール

鈴木 柚子さん
渋谷区内小学校 教諭。大学から教職大学院へ進学し、卒業後は品川区の小学校で特別支援学級担任に。品川区の小学校で図工専科として勤務し、現在は渋谷区内小学校で図工専科。昔から自然の中で遊ぶことが大好きで、今はマリンスポーツを10年以上続けている。令和6年より渋谷区で探究「シブヤ未来科」が始まり、探究学習の機会が拡充。テーマ探究や図工における探究的な学習などを行っている。今年度は校舎の緑化とファッションの循環に挑戦。

金川 雄策さん
一般社団法人DDDD Institute代表理事。2004年より全国紙の映像報道記者として、東日本大震災、熊本地震、パリ同時多発テロ事件、ブラジル・リオパラリンピックなど国内外の現場で取材。NY でドキュメンタリーフィルムメイキングを学ぶ。17年にインターネットメディアに転職し、ドキュメンタリープラットフォームや中高生向けのドキュメンタリー教材の立ち上げを主導。一般社団法人DDDD Institute代表理事、特定非営利活動法人Tokyo Docs 理事。武蔵野美術大学非常勤講師、京都芸術大学非常勤講師。放送文化基金賞、日本民間放送連盟賞、全日本テレビ番組製作会社連盟賞などの審査員を歴任。
今現場ではどんな新しい教育が取り入れられている?
ゲスト、参加者がそろったところでまずは「カンパイ」!
全員で自己紹介を行い、対談がスタートしました。
―渋谷区の小中学校でスタートした探究「シブヤ未来科」とはどんな取り組みなのでしょうか。

鈴木さん:探究「シブヤ未来科」とは、区立小中学校で令和6年度から渋谷区で実施されている文部科学省の「授業時数特例校制度」を活用した、全国的にも注目を集める探究学習のことです。
従来の総合的な学習の時間に加え、各教科から時間を一割ずつ割いて横断的な学習を行う全国初の取り組みで、子どもたちが興味のあるテーマを選んで深く学ぶことができるようになっていることが特徴です。
金川さん:色んな先生たちを巻き込むとともに、子どもたちにとって多様な選択肢が広がる取り組みなんですね。
ドキュメンタリーの世界でも、ディレクター、プロデューサー、カメラマンなどのチームを組んで制作を行います。協力して映像を作り上げるプロセスは必須であり、特に意見をぶつけ合いひとつのテーマに絞り込んでいく過程が探究学習と共通していると思います。
―一方ドキュメンタリーの教育現場ではどのような取り組みが始まっているのでしょうか。

金川さん:私は現在ドキュメンタリーを発信するプラットフォームのプロデューサーを本業としています。
その傍ら、この春より学生から社会人まで幅広い人を対象としたドキュメンタリースクール「DDDD Film School」を開講しました。日本ではドキュメンタリー制作を学ぶ場所が少ないことに以前から課題を感じていたからです。
海外のドキュメンタリーを学ぶフィルムスクールに一年間留学すると生活費も含め年間1,000万ほどの費用が必要になりますが、私のスクールでは約10分の1以下の費用で海外のフィルムスクールの手法を取り入れたカリキュラムを学ぶことができます。
またこのスクールとは別に、ドキュメンタリーの現場の新しい教育事例として、中高生向けの探究学習用の教材を制作しました。
具体的な内容としては、スマホでショートドキュメンタリーを自ら制作するというもの。そもそも学生は何をテーマに探究したら良いか分からないケースが多いようで、ベースとなるものを提供することで「自分は何に、なぜ心が動くのか」に気づくきっかけになれば良いなと思っています。
図工教育とドキュメンタリーの可能性
―ゲストのお二人の取り組みなどを伺ったところで、それぞれご質問があるということで用意してきていただいています。鈴木さんから金川さんには、ドキュメンタリーの制作についてお聞きしたいと伺っています。

鈴木さん:学習指導要領にもICTを活用した表現や鑑賞を進めていきましょうといった文言があり、図工とドキュメンタリーって何ができるんだろう?と思ったんです。
そもそも、ドキュメンタリーを撮られる方たちはどんなことを考え、伝えたいと思い、映像を作られているのでしょうか。
金川さん:前提として、映像は多くの情報を伝えられるメリットがある一方、詰め込み過ぎると何も伝わらないデメリットもあります。メッセージを絞り込み、自分の伝えたいことを意識することでようやく伝わるのかなと思っています。
そして、ドキュメンタリー自体はひとつの箱、フォーマットに過ぎません。中身はファッションかも知れないしスポーツかも知れません。
だからこそ毎回伝えたいメッセージは変わりますし、そこがドキュメンタリーの面白さだと考えています。
これからの時代は、生成AIを活用した才能あるクリエイターも多く登場することが予想されていますが、被写体と撮影者の人間関係が色濃く反映され、人の血が通うドキュメンタリーは教育に生かすべきメリットが多くあるのではないでしょうか。
―金川さんから鈴木さんへのご質問はいかがでしょうか。
金川さん:大学院で鑑賞教育を学ばれたとのことですが、具体的な中身を教えて下さい。
鈴木さん:学校教育における鑑賞教育の目的は、単に「この絵に何を感じますか?」を問いかけることに留まらず作者のメッセージや社会的背景、歴史的文脈まで深く理解することを指します。
例えば建築模型ひとつとっても、ただ作るのではなく建築家の想いを組み込むことで伝えたいことをより深く理解できると思うんです。
なので、ドキュメンタリーを授業に取り入れるとしたら子どもたちの目線でテーマを決め、グループで会話をしながら撮影し、そこからどんな学びが深まっていくのか…ということができたら面白いかなと思いました。
社会課題にフォーカスした教育が次世代にもたらすもの
―お二人がそれぞれの現場で活動される中で、教育が社会課題解決にもたらす影響や可能性についてどのように考えていますか。

鈴木さん:探究「シブヤ未来科」では環境問題など社会課題をテーマとして取り入れることで、単純に動物や自然の絵を描く、など従来の図工学習の枠組みを越えた見方や考え方が子どもたちにもたらされていると思います。
題材の一例を挙げると、「まだ見たことのない建物を作ろう」をテーマに、個々が自由な発想で未来にあったら良いなと思う建物の模型を作りました。
制作の前に、東急不動産の商業施設で取り組む緑化や再エネ事業にご協力いただき、建築家の方からも建築やデザインについてお話を聞いたんです。
これまでの図工と違う点は、いつもならひとつの題材につき大体2時間から6時間ぐらいのところを20時間ほどじっくりと時間をかけ、建築やデザインの裏側にある想いなどを知ってから、制作を行ったところです。
なかには休み時間を費やして没頭する子どももいるなど、とても楽しんでいる様子を見られるのが教員としてうれしく感じています。
金川さん:教育とは、社会を前に進めることなんじゃないかなと思っています。これまでの歴史から学び、次世代へ教訓を伝えしっかりとバトンを渡していくこと。
映像教育を通じて、スキルの獲得に限らず、倫理観や価値観など自分なりのものさしや豊かな人間性を養ってほしいなと思っています。
多様性を認め合い、ひとり一人の個性が輝く社会を実現したい
―最後に、教育を通じて実現したい社会について教えてください

鈴木さん:探究学習は遊びの延長線上にあるものなんじゃないかと思う時があります。自分の「好き」を、探究を通じて突き詰めていくことが理想的なのではないでしょうか。
現在毎週300人以上の子どもと関わる生活を送る中で、三者三様の個性や興味があることを実感しています。長所や強みなど潜在的なものを、教育を通じもっと引き出して、みんなが輝くことができる社会が実現してほしいです。
金川さん:ドキュメンタリーには「赤の他人にも寄り添う力」があると信じています。映像を通じて自分の人生に全く接点がない人のことを知ることができるからです。
最近は外国人排除の動きなど、社会から人が爪弾きにされることがいとも簡単な時代だからこそ、社会全体として何が最適解なのかを考え続けていくことが大切なのです。
ドキュメンタリーという存在は個々人の社会を見る幅を広げてくれ、 その社会の中でどういうふうにしていけばいいのかということを考える素地を与えてくれる。分断ではなく融和の道を模索する社会のあり方を目指せるのではないかと考えています。
これまでの枠にとらわれない教育で、社会課題と向き合う
従来の暗記型教育から探究型学習が取り入れられることの意義や、日本のドキュメンタリー教育の現状など、異なる領域の教育に携わるお二人のコラボレーションが実現した、今回のKANPAI for GOOD。
和やかなムードのなか、社会課題解決を目指した教育の在り方について多くの話題が飛び出しました。
豊かな社会をつくるため、また次の世代へとバトンをつないでいくために私たちは何ができるのか。教育の現場から新たな可能性や希望を見出すことができた一夜となりました。

取材・文/kagari
イベントでは、スナックならではのフランクな雰囲気の中、様々な活動を行うゲストから直接話を聞くことができます。初めての方も大歓迎。興味のある方はぜひ足を運んでみては?
最新の開催情報はSNACK LIFE IS ROSE GINZA公式インスタグラムから。