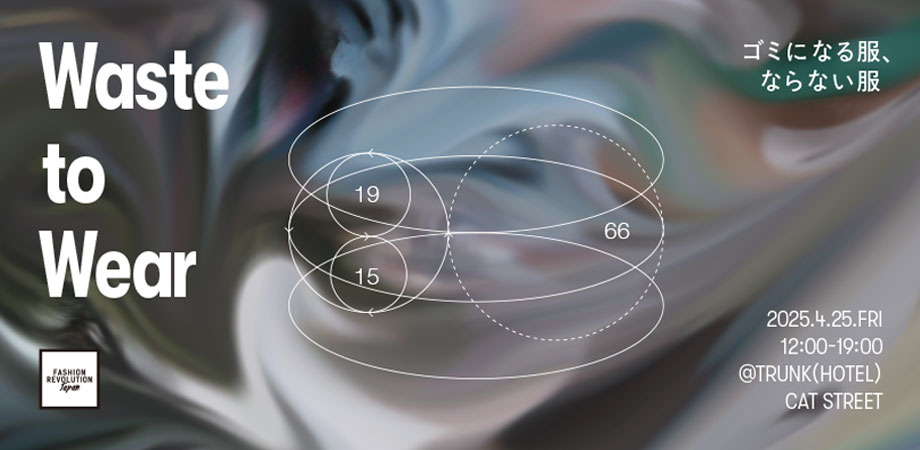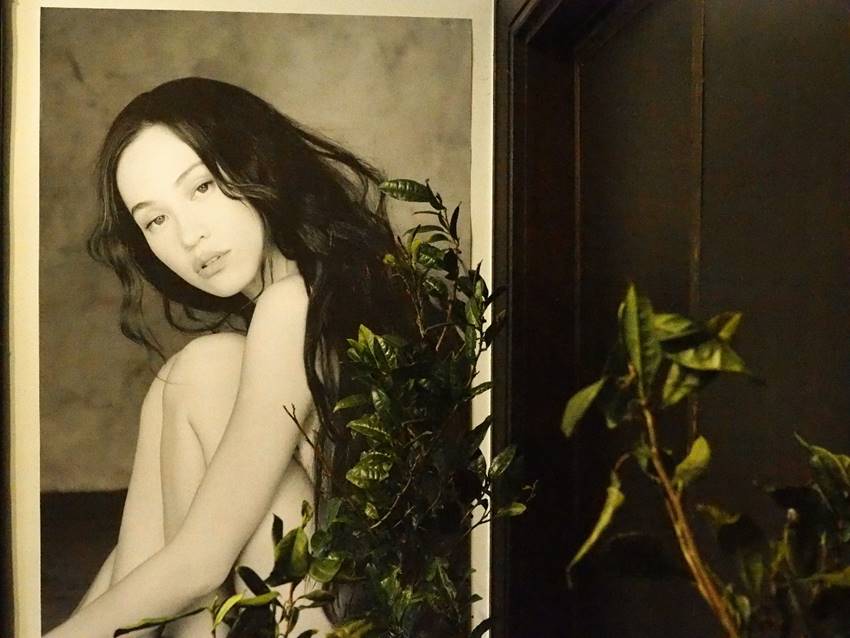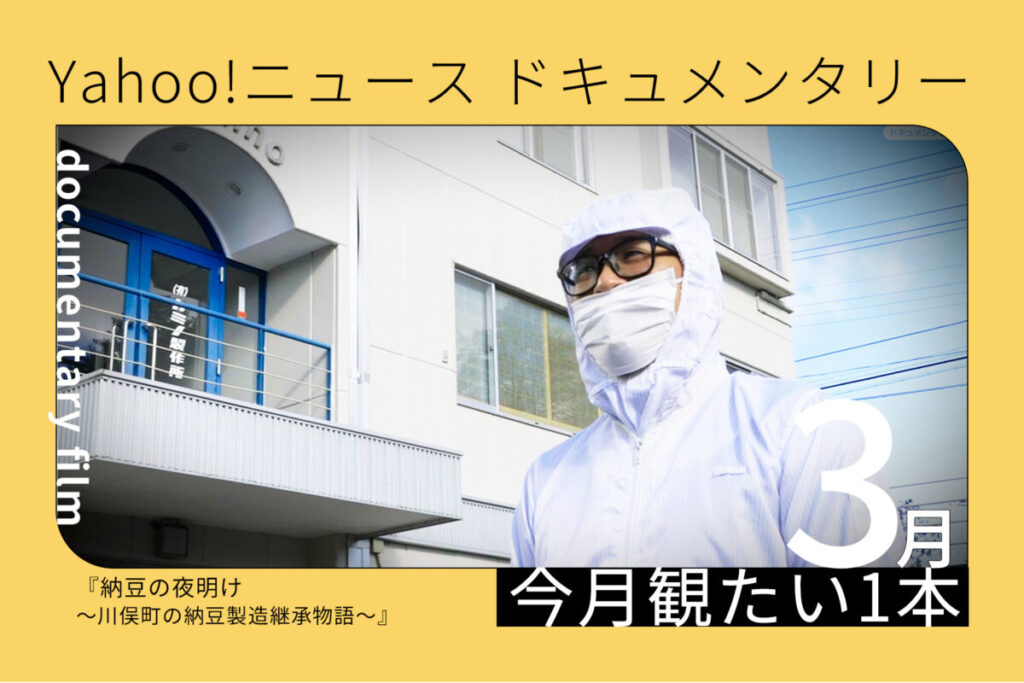rootus編集部– Author –
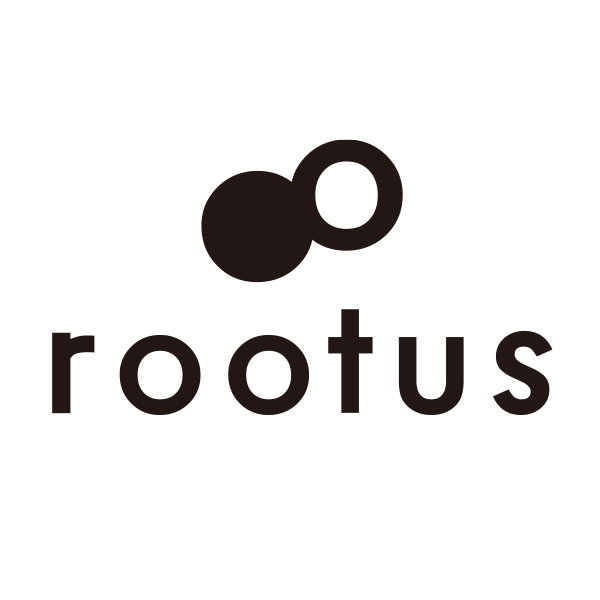 rootus編集部
rootus編集部
「豊かな未来に繋がる日常のアイデア」を編集部がご紹介。本当の豊かさを見つめなおすきっかけになるヒントを発信していきます。
-
 TOPICS
TOPICSサステナブル×日本文化がテーマの交流型イベント「rootus night」開催
-
 TOPICS
TOPICSフェアトレード企画展が11月16日まで下北沢にて開催。初日のアワードではフェアトレードを推進する団体・企業が受賞
-
 TOPICS
TOPICSCACL×LIXIL×永山祐子建築設計が能登半島地震で廃材となった黒瓦をアップサイクル
-
 FEATURE
FEATURE【KANPAI for GOODレポート】教育現場の最前線。教育が社会課題解決にもたらすものとは?
-
 FASHION
FASHION【保存版/レディース・メンズ】選択肢が広がる!エシカルファッションブランド21選
-
 FEATURE
FEATUREYahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『苦しみを言葉に変えて 不登校生動画選手権へ 親子の挑戦』
-
 TOPICS
TOPICS下北沢に「みんな商店」がオープン。サステナブル体験を通じて、地域コミュニティをつなぐ場所に
-
 TOPICS
TOPICS2025年ファッションレボリューション、ファッションロス解決に向けたシンポジウムを開催
-
 FEATURE
FEATURE【サステナブルコスメアワード受賞】水原希子さん本人が語る、kiiksに込めたエシカルマインドとは?
-
 FEATURE
FEATUREYahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『母の心配』
-
 TOPICS
TOPICS4月1日~DEAN & DELUCAがサステナブルなデリ総菜やプラントベースメニューを販売
-
 TOPICS
TOPICSソーシャルプロダクツ・アワード2025が決定。能登半島地震復興につながる商品・サービスなどがテーマ
-
 TOPICS
TOPICSグローバルワークなどの店舗で、PASSTOの循環型衣料品回収を導入
-
 FEATURE
FEATUREYahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『納豆の夜明け〜川俣町の納豆製造継承物語〜』
-
 TOPICS
TOPICSインドの天日干しデニムや、手つむぎ手織りの伝統素材も。RIKO YAMAGUCHIが最新コレクション発表
-
 TOPICS
TOPICS渋谷で古紙から3,580個のトイレットペーパーを生産。サステナブルツーリズムの実現へ
-
 TOPICS
TOPICS2025年3月15日、銀座に都内初のヘラルボニー常設店舗が誕生
-
 FEATURE
FEATUREYahoo!ニュース ドキュメンタリー 今月観たい1本『境界のフィルムメイカーたち』
-
 FOOD
FOOD【2025年】おしゃれで美味しくて、サステナブル!バレンタインに贈りたいチョコレート7選
-
 TOPICS
TOPICSアカデミー賞ノミネートの快挙。伊藤詩織さんと山崎エマさんが作品に込めた想い