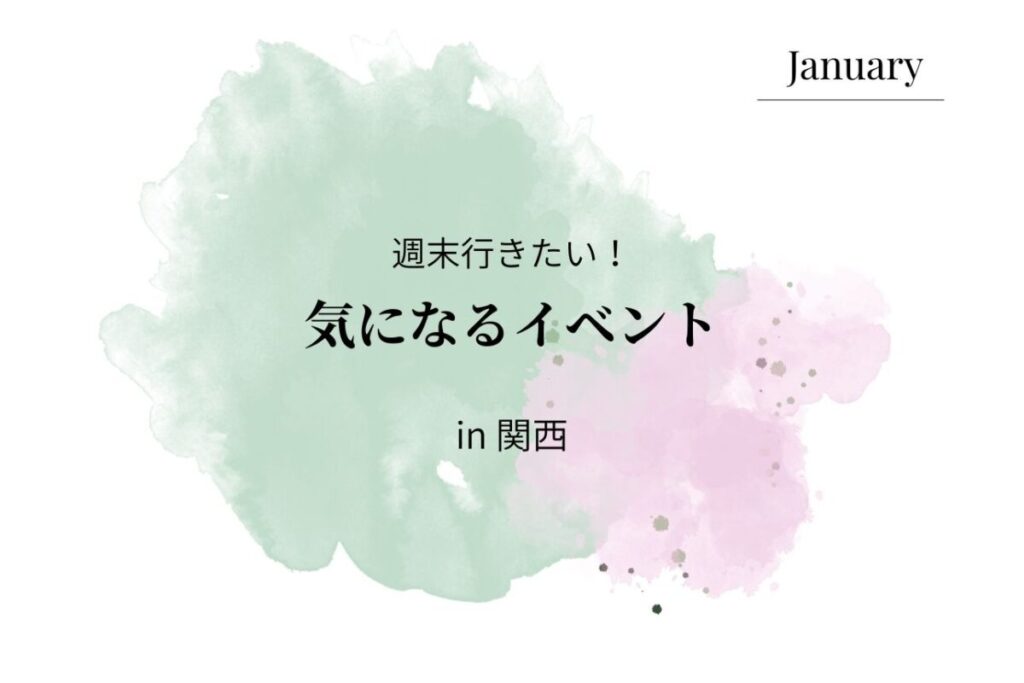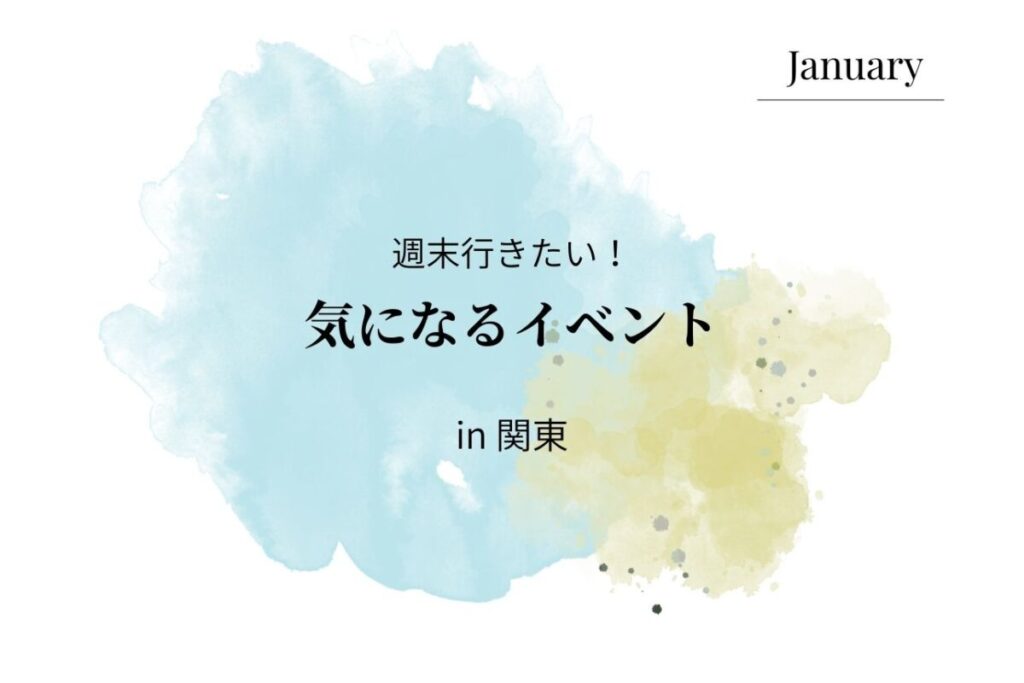ヴィーガンではないけれど食べてみたい、使ってみたい。そんな魅力的なメニューや商品が増えてきたこともあり、ヴィーガン認証マークが気になっている方は多いのではないでしょうか。
マークがヴィーガン対応の目印であることを知っている人は増えても、どこの国のものなのか、どういう基準で認証されているかまでは、あまり知られていないかもしれません。
そこでこの記事では、ヴィーガン認証について、また各国のヴィーガン認証マークや認証基準を紹介します。
ヴィーガンについてもっと知りたいという方は、参考にしてみてくださいね。
ヴィーガン認証とは?

ヴィーガン認証とは、その製品がヴィーガン基準を満たしていることを保証するものです。
ヴィーガンは「完全菜食主義」とも呼ばれ、動物由来の食品の摂取や製品の使用を避けるライフスタイルです。肉や魚、卵、乳製品はもちろん、動物性の原料を含む加工食品の他、製造工程で動物性の原料が使われたものも対象になります。
また、動物愛護や環境保護の観点から、はちみつも摂取を避ける場合が多くあります。
関連記事:世界中で広がるヴィーガン。ベジタリアンやペスカタリアンとの違いは?
ただし、ヴィーガンの人が必要な情報を製品表示で見分けるのは簡単ではありません。そのため、ヴィーガン認証制度が設けられ、基準を満たした食品や製品であることを示す「認証マーク」が表示されるようになりました。
ヴィーガン認証の条件

ヴィーガン認証の条件は主に以下の4点です。
- 動物性の原材料を使っていない
- 動物実験を行っていない
- 動物の遺伝子、または動物由来の遺伝子組み換え作物を使っていない
- 製造過程で動物性原料が混入しない生産設備がある、または混入を防止する対策をしている
これらは基本的な認証条件で、国や地域、認証団体によって異なる場合があります。
例えば、動物由来の遺伝子組み換え作物の使用を規制していないものもあれば、昆虫由来の成分の使用を禁止しているものもあります。
ヴィーガン認証マークの種類

世界中に数多くあるヴィーガン認証マークの中から、代表的なものをいくつか紹介します。
日本の認証マーク
ベジプロジェクトジャパン

- 設立:2013年(2016年にNPO法人化)
- 基準:動物性原料不使用、動物実験なし
- 日本で最も多くの商品に利用されているヴィーガン認証マーク
ヴィーガン認証協会

- 設立:2007年正式登録
- 基準:JAS規格に基づいた基準を採用
- 約300商品、500店舗以上が認証を受けている
日本ヴィーガン協会

- 設立年 2020年02月03日
- 基準:ヴィーガンJAS規格 (国家認証 2023年施行)
- 2025年現在JASヴィーガン認証事業者は5社
海外の認証マーク
The Vegan Society
- 国:イギリス
- 設立:1944年
- 基準:動物性原料不使用、動物実験なし、動物遺伝子組み換え原料不使用、製造過程での動物由来混入の防止
- 認証商品は食品、サプリメント、コスメ、日用品など68カ国で70,000点以上
Bioagricert(バイオアグリサート)
- 国:イタリア
- 設立:1984年
- 基準:動物性原料不使用、動物実験なし、製造過程での動物由来混入の防止
- ヴィーガン認証の他、ベジタリアン認証、プラントベース食品認証、コスメ(天然由来・オーガニック・植物由来の3種類)、洗剤(天然由来・オーガニックの2種類)、日用品(天然由来・オーガニックの2種類)など多種多様
https://www.bioagricert.org/en
Vegan Action
- 国:アメリカ
- 設立:1995年
- 基準:動物性原料不使用、動物実験なし、動物遺伝子組み換え原料不使用、製造過程での動物由来混入の防止、昆虫または昆虫由来原料不使用
- 1,500社を超える企業との連携により、15,000種類以上の製品が認証済み
V-Label(欧州ベジタリアン連合)
- 国:スイス
- 設立:1996年
- 基準:動物性原料不使用、動物実験なし、動物遺伝子組み換え原料不使用、製造過程での動物由来混入の防止、バイオテクノロジー生産プロセス基準を満たすこと
- 各国にパートナー組織がある国際的機関。認定製品は、代替食品や製菓、サプリメントなどさまざま
NZ Vegetarian Society
- 国:ニュージーランド
- 設立:1943年
- 基準:動物性原料不使用、動物実験なし、動物遺伝子組み換え原料不使用、製造過程での動物由来混入の防止
- 認証商品は、食品、飲料、レストラン、コスメ、日用品、サプリメントと多種多様
Vegecert
- 国:カナダ
- 設立:不明
- 基準:動物性原料不使用、動物実験なし、製造過程での動物由来混入の防止、昆虫や爬虫類由来原料不使用
- ワールドワイドな認証マークとして知られ、各国の企業の商品が認定されている
EVE Vegan
- 国:フランス
- 設立:2016年
- 基準:動物性原料不使用、動物実験なし、製造過程での動物由来混入の防止
- 食品の他、レストラン、カフェ、宿泊施設、コスメ、テキスタイルやバッグ、サプリメント、医薬まで認証範囲がとても広い
Vegan Australia
- 国:オーストラリア
- 設立:2012年
- 基準:動物性原料不使用、動物実験なし、製造過程での動物由来混入の防止
- 食品や飲料など、3800種類以上のさまざまな製品が認定されている
https://www.veganaustralia.org.au/
他にも、ギリシャ、トルコ、韓国、メキシコ、中国、インドなど様々な国に、認証機関とヴィーガン認証マークがあります。
ヴィーガン認証製品を探してみよう

サステナブルやエシカルへの関心、アニマルウェルフェア(動物福祉)への意識の高まりにより、ヴィーガンを選ぶ人が増えています。それに伴って、ヴィーガン対応の商品も多く目にするようになりました。ただし、それら全てがヴィーガン認証を受けているわけではありません。
ヴィーガンやナチュラルフードの専門店は別ですが、量販店やスーパーなどでは認証商品はまだまだ少なくレア。その分、偶然見つけた時の驚きや嬉しさは、ヴィーガンでない人にとっても大きいものです。
それぞれの認証基準を参考にしながら、積極的にヴィーガン認証製品を探してみませんか。いつもの買い物が、ちょっと楽しくワクワクするものになるかもしれません。
参考:
https://vegan.org/certification/
https://vegan.or.jp/association
https://www.vegansociety.com/vegan-trademark/vegan-trademark-standards
https://www.vegansociety.com/about-us/further-information/key-facts
https://www.bioagricert.org/wp-content/uploads/2025/05/Standard_EN-For-The-Certification-of-Vegetarian-Vegan-and-Plant-Based-Products.pdf
https://www.bioagricert.org/en/certification/no-food-and-other-services/cosmetic
https://vegan.org/certification
https://www.v-label.com/criteria
https://www.evevegan.org/certification-standards
https://veganaustralia.org.au/certification/certification-standard
https://greekexports.org/en
https://www.veganmark.org/about-us
https://www.chinavegans.org
https://www.foodchainid.com/mx
https://www.koshercertified.in
https://vegewel.com/ja/style/statistics3
https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20210203_022067.pdf