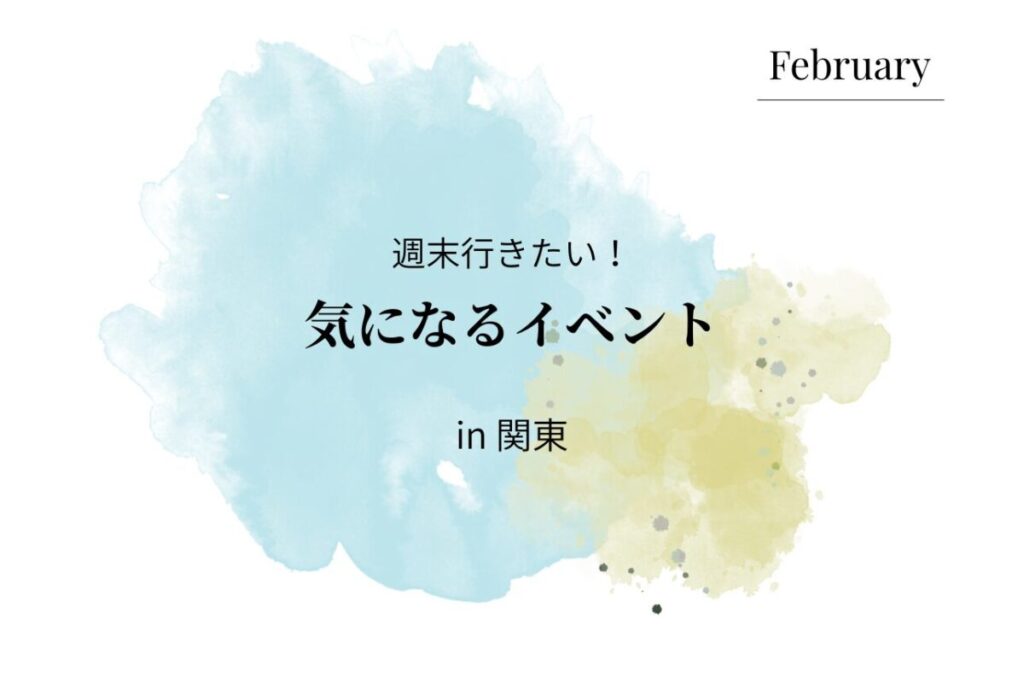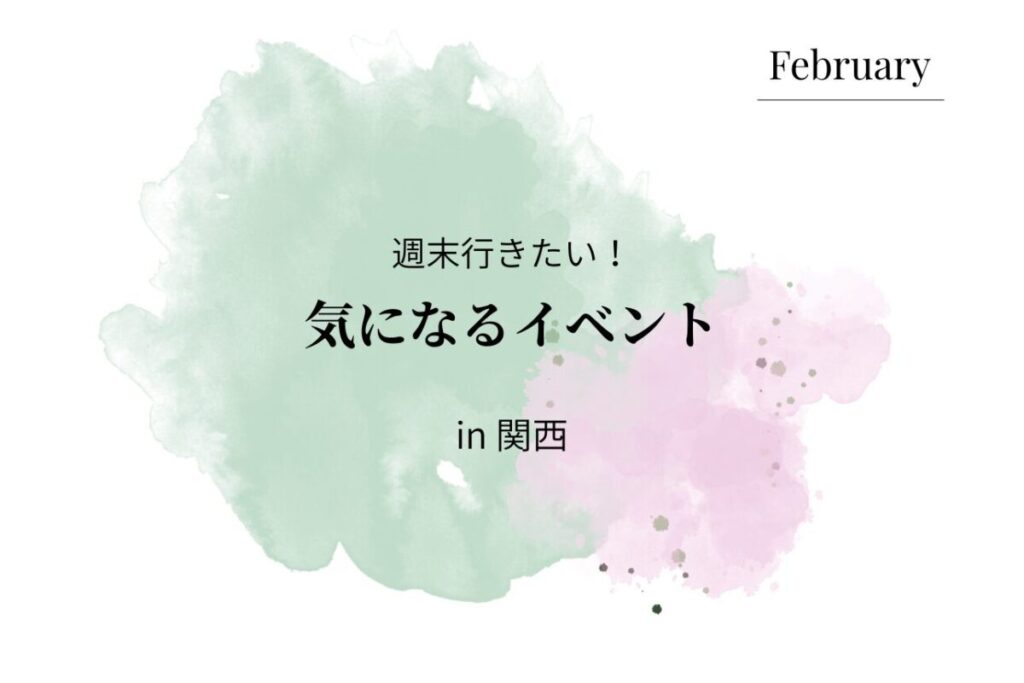持続可能な社会の実現が世界各国において求められています。誰も取り残すことなく、人々が幸せに、生きやすい社会にしていくために、サステナビリティを重要視した街づくり、社会づくりが注目されるようになってきています。そこで近年増えるソーシャルデザインとはなにか、事例を交えてご紹介します。
ソーシャルデザインとは

ソーシャルデザインとは、社会の課題をアイデアによって解決し、人々が住みやすい社会を作っていくための構想です。ソーシャルデザインとひとことに言っても、定義が明確に定められているわけではなく、種類も広範囲に及びます。
ソーシャルデザインは、社会で暮らす一人ひとりの人に焦点がおかれているため、モノの見かけをデザインするという意味合いだけではなく、育児、教育、福祉、災害、産業における社会的な課題を解決するための行動やシステム、取り組み、製品やサービスなども含まれます。
最近ではSDGsが広く知れ渡るようになり、社会的意義を持ったソーシャルデザインの裾野が広がりを見せています。
ソーシャルデザインが取り入れられている場所

私たちの身近な日常生活の中にもたくさん取り入れられているソーシャルデザインは具体的にどのようなものか見ていきましょう。
例えば、美術館や劇場などの施設や、廃校になった校舎などをリノベーションして地域の交流拠点とすることなどが挙げられます。このような取り組みは、使われない場所や資源の再利用が進み、地域の活性化にも繋がります。また、人々が関わり合い、助け合う社会のための一翼を担います。
他にも、育児や家庭の悩みを聞くサービス、障がい者やハンディキャップを持つ人の就労支援などもソーシャルデザインと言えます。また本来は捨てられるはずのものや、海洋ゴミなどをアップサイクルする取り組みなども挙げられます。
身の回りでは、思っているよりもたくさんのソーシャルデザインが取り入れられているのです。
ソーシャルデザインの事例
社会の課題を解決するデザインであればソーシャルデザインと言えるため、対象の範囲かなり広いことは先に述べた通りですが、ここでは、地域社会にインパクトを残し、人と人との繋がりを実現したソーシャルデザインの事例をご紹介します。
関連記事:人のための社会づくり。日本と世界の都市のソーシャルデザイン事例
ソーシャルデザインの事例① 祈りのツリー Project
日本ユニセフ協会が2011年から2015年まで毎年行った「祈りのツリーProject」。
東日本大震災に見舞われた子どもたちの幸せを願い、飾るオーナメントを届けるプロジェクトです。
28人のクリエーターから始まったこのプロジェクト。2014年までにオーナメント制作に携わったデザイナーは3300人を超え、東北で行われた子どもたちによるオーナメント作りにはのべ200人以上のデザイナーや美大生がボランティアとして参加する大きな取り組みとなりました。
作られたオーナメントは、東京や東北の各所に置かれた「祈りのビッグツリー」に飾られ、被災地の幼稚園や保育園にもおくられました。
中でも、震災により被害を受けた飲食店が集まる気仙沼横丁(2017年閉鎖)に作られた津波の高さと同じ8mの”きずなの塔”は「祈りのビッグツリー」として装飾が施され、プロジェクトを象徴するものとなりました。
全ての人々の復興への想いがツリーという形になってあらわれ、希望の光として人々の心を照らす存在となったのです。一方的な被災地支援ではなく、気仙沼の子どもや住民が携わったことも、このプロジェクトの大きなポイントだったと言えるでしょう。
参考:https://www.unicef.or.jp/kinkyu/japan/2011_1219.htm
ソーシャルデザインの事例② HAGISO
HAGISOは東京都台東区にある「最小文化複合施設」です。
1955年に木造アパートとして建てられ、2004年から東京藝術大学の学生たちのアトリエ兼シェアハウスとして使用されていた萩荘。
解体の話が出ている中、入居者より大家さんへの最後のお願いとして、萩荘に集っていた学生やアーティストたち約20名によるグループ展「ハギエンナーレ2012」を開催。建物を人々の記憶に残すことが目的でしたが、予想外の盛況を受け、計画は一転、改修され2013年3月「最小文化複合施設」としてオープンしました。
1階がカフェになっており、アートギャラリーやホテルのレセプションなどが建物の中に入っています。
カフェではハンドドリップコーヒーや、日本各地の食材を取り入れた「旅する朝食」を味わうことができ、ギャラリーやレンタルスペースではアーティストの展示やワークショップなどを開催。
2階のホテルのレセプションから案内される宿泊棟hanareは、まち全体をひとつのホテルと見立てることをコンセプトに、周辺の銭湯から好きなところ選べるチケットが宿泊料に含まれ、おすすめのレストランや個性的なバーを紹介してくれるなど、単なる宿泊体験ではなく、町をまるごと楽しめるアイデアが満載です。
昭和の良き風景を残しながら、現代的なカフェや宿泊施設として新たな人々の集いの場を提供しているこちらの施設。歴史を受け継ぎながら、都会で失われつつある人と人とのつながりを生み出す拠点となっているのです。
デザインの力が、社会と人々を豊かにする

今回は、私たちの社会の課題を解決に導くソーシャルデザインについてご紹介してきました。アイデアひとつと社会にいる私たちの行動で、社会はより良いものへと変えていくことができます。これからますます増えていくことが予想されるソーシャルデザインにこれからも注目です!
ぜひみなさんの身近なソーシャルデザインを探してみてくださいね。