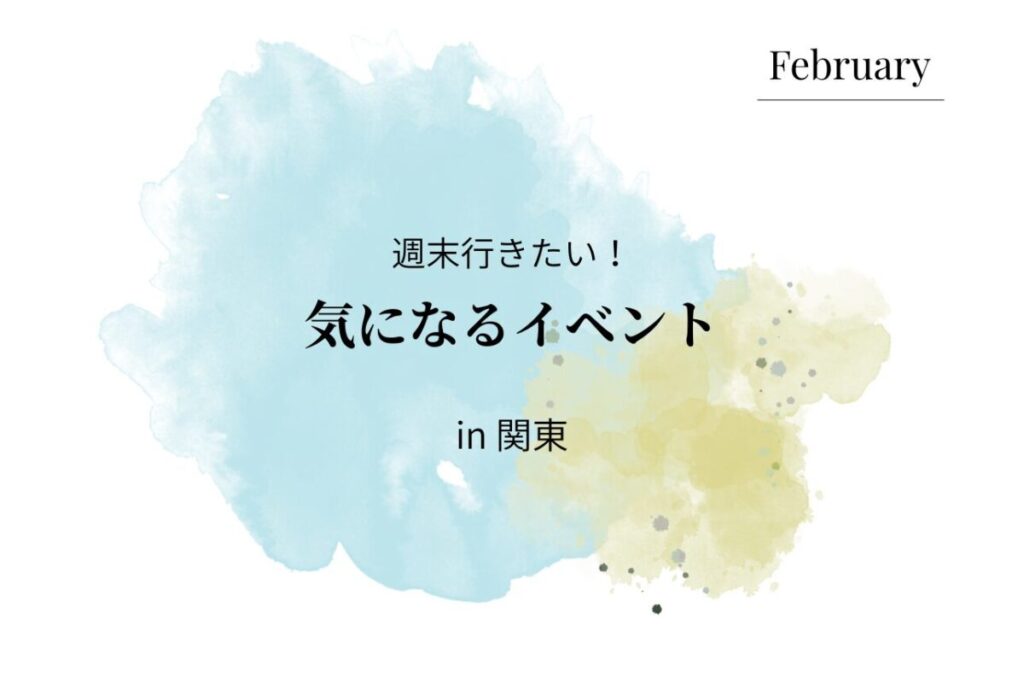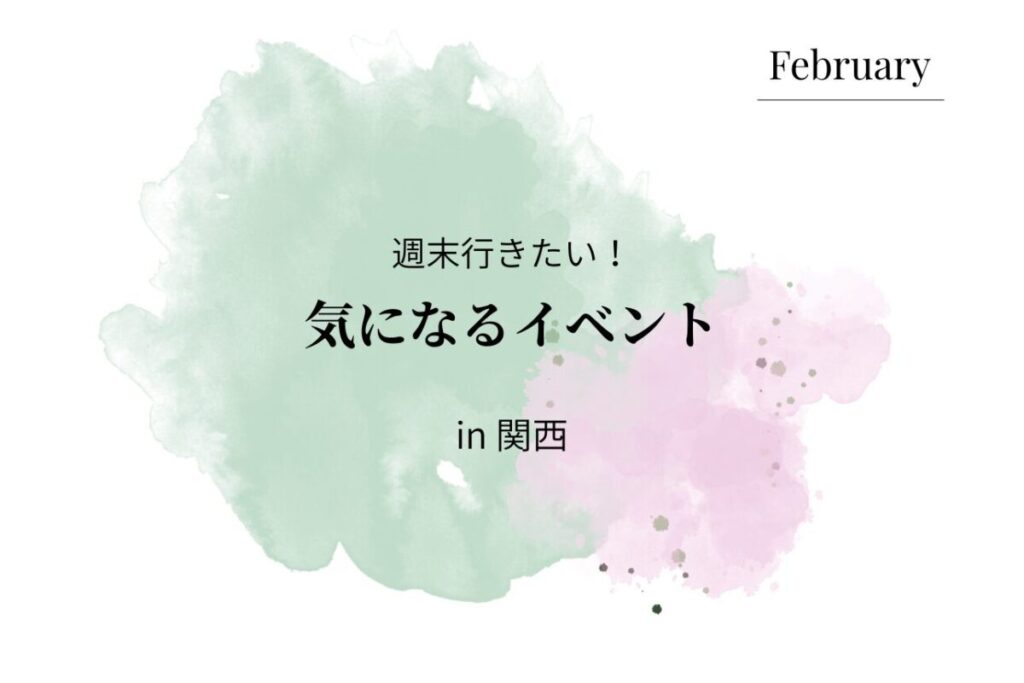カーボンニュートラルは、私たちの住む地球を持続可能なものにしていくためのキーワードの一つです。近年、テレビや新聞で取り上げられることも増え、国や企業を中心にカーボンニュートラルを意識した取り組みが広がっています。こちらの記事では、少し難しいように感じるカーボンニュートラルについて、かみ砕いてわかりやすく解説します。
カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルとは、人の活動が起因となって発生する温室効果ガス(CO2など)の排出量から、植林などによる「吸収量」を差し引き、排出量の合計を実質的に「ゼロ」にすることを指します。
2015年のパリ協定では、世界共通の長期目標として、
・世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること(2℃目標)
・今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成すること
などが合意されました。
これに伴い、日本を含む120以上の国が2050年までにカーボンニュートラルを達成するために取り組みを始めています。
カーボンニュートラルが必要な理由

世界では海面上昇や砂漠化、大規模災害、深刻な水不足など、気候変動が人々や生態系に大きな影響を与えています。私たちの住む日本も例外ではなく、埼玉県や群馬県、岐阜県といった内陸の県の夏は異常な暑さとなり、全国的にゲリラ豪雨などによる被害も多く発生しています。
世界の国々が一丸となってカーボンニュートラルを目指す主な理由は、このような気候変動危機を回避することにあります。
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)によると、世界で工業化が進んでから、世界の平均気温は約1.1℃上昇しているとされており、人類や地球上の生態系に深刻な影響が出る境界値は工業化からプラス1.5℃と言われており、気温上昇はあと0.4℃に抑える必要があるのです。
持続可能な未来に向けて、今すぐ私たちが取り組まなければならない喫緊の課題である気候変動。気候変動を食い止める一つの策としてカーボンニュートラルの取り組みが求められています。
日本政府も目指す「2050年カーボンニュートラル」
日本では、2020年10月に開かれた臨時国会の所信表明演説において、当時の内閣総理大臣だった菅義偉氏が「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指す」という宣言をしました。
日本は、CO2だけに限らず、メタン、N2O(一酸化二窒素)、フロンガスを温室効果ガスとして削減することを目指しています。
現在国内の温室効果ガスの排出量は、年間12億トンを超えると言われています。
「2050年カーボンニュートラル」を確実に進めるために、2030年には温室効果ガスを2013年度の46%削減することを目指し、段階を踏んで達成していくことを宣言しています。
国が進める具体的な取り組み
日本政府はカーボンニュートラルを現実のものとするために、多方面での取り組みを行っています。いくつか具体的な事例を見ていきましょう。
グリーン成長戦略
並大抵の努力では実現が難しい2050年カーボンニュートラル。目標を達成するためには、エネルギー・産業の構造の大きな転換や、投資によるイノベーションが必要となります。積極的に温暖化対策を行うことが成長のチャンスであるという考えのもと、「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策 がグリーン成長戦略です。
国は、再生エネルギーの促進をはじめとし、農業やIT産業など14の分野でそれぞれの課題や目標を明記。税金の投入や、規制改革および標準化・国際連携などを通して全面的に企業をサポートします。
ゼロカーボンシティの実現
環境省は、地方公共団体の脱炭素化への取組に対し、情報基盤整備、計画等策定支援、設備等導入を支援しています。2050年カーボンニュートラルを宣言する地方公共団体は増加してきており、2022年12月時点では、800を超える地方公共団体が取り組みを始めています。
脱炭素社会の実現に向けて
国の動きに連動して、国内では脱炭素社会に向けた取り組みを行う大企業が増えてきています。
国や企業が脱炭素社会に向けて取り組むインパクトは、社会にとって大変大きいもので、2050年カーボンニュートラルの実現のためには不可欠です。
私たちの生活に関わる企業も取り組みを始めています。そのような企業に注目することが私たち一人ひとりにできるカーボンニュートラルに向けたアクションになってくるでしょう。
【参考】
令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)第1部 第2章|資源エネルギー庁
国の取組 – 脱炭素ポータル|環境省