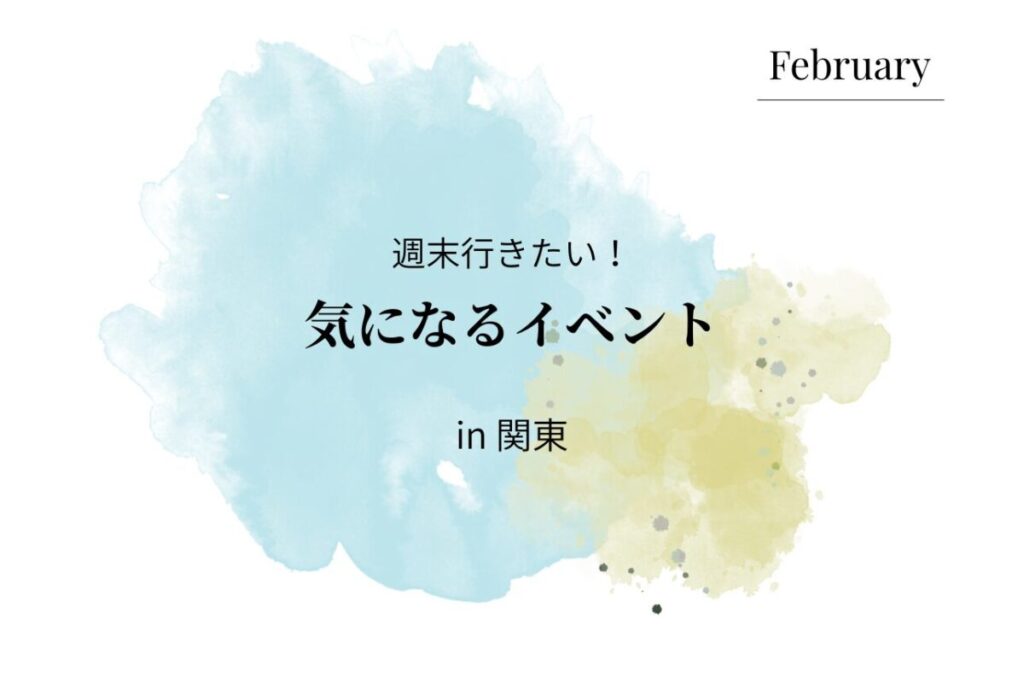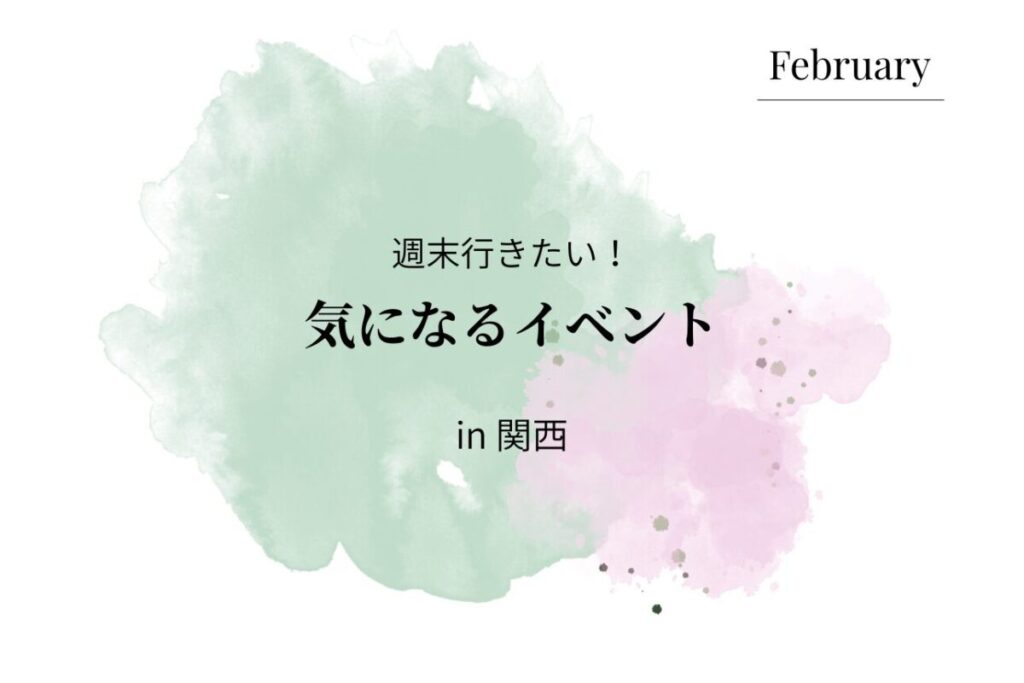「マイノリティ」という言葉の意味をご存知でしょうか。その意味を知りたいという人が増えるだけで、さまざまな特性を持つ人が生きやすい社会作りに繋がります。
今回はマイノリティとはどういった意味を持つのか、またマジョリティやインターセクショナリティとの違いなどを整理していきます。
マイノリティとは
マイノリティ(minority)とは、2つのもののうち少数派を表す言葉です。マイノリティの由来とされる「マイナー(minor)」は少ないという意味だけでなく、重要ではないという意味もあります。
人種、宗教、障がい、性別、性的志向などの社会的少数派を指し、そういった人たちは多くの場面で不当な扱いを受けてきたのが現実です。
マイノリティとは、ただ少数派なだけでなく、その特性によって差別や偏見を受けやすい場合を指しています。
SDGsとの関連も深いマイノリティ
マイノリティの性質を持つ人が生きづらさを感じるのは、社会は基本的にマイノリティではない人が生きやすいように設計されているからです。
課題は残るものの、少しずつマイノリティの人たちを取り残さない社会にしようという動きが出てきています。
2015年に国連で採択された国際目標であるSDGs、17の「持続可能な開発目標」が一例です。
例えば「1 貧困をなくそう」では、世界の6人に1人の子どもが、極度に貧しい暮らしをしており、貧困自体がマイノリティであることが分かります。それだけでなく、マイノリティの人々は差別を受けやすいため、貧困に陥りやすいともいわれています。
他にも「10 人や国の不平等をなくそう」では、障がいのある子どもは学ぶチャンスが少ないというデータを提示しています。エチオピアの農村部では、中学校に通えない子どもの割合は、障がいがない場合は47%、障がいがある場合は98%という数値が出ています。
マジョリティとマイノリティの違い

マイノリティと併せて確認しておきたいのが、「マジョリティ」という言葉の意味です。マジョリティとは「多数派」を意味していて、マイノリティの対義語です。社会での多数派の集団に対して使われることが多く、重視されやすいグループを指しています。
マジョリティは多数派であるが故に、無意識にマイノリティに不利な状況を作ることがあります。マイノリティはその状況から生きづらさを感じていても、マジョリティは当事者ではないため気付かないことが多いでしょう。マジョリティが当然と思って生きている環境が、恵まれたものだと気付くことが大切です。全ての人が権利を尊重して、支え合う社会が理想的ではないでしょうか。
マイノリティにはどんなものがある?

ここからはマイノリティの例をあげていきます。
社会的マイノリティ
幅広い視点から、社会的にマイノリティと判断される人は「社会的マイノリティ」といわれています。障がい者、貧困層、宗教信仰などがその一例です。
分かりやすい例を挙げると左利きの人もマイノリティに当てはまり、その割合は全体の11%とされています。多くの物は右利きの人用に作られているので、左利きの人は不便に感じることが多いのです。
他にも両親がそれぞれ別の国のルーツを持つ人もマイノリティに当てはまります。見た目がマイノリティの人と違うというだけで注目されて、いじめの対象になってしまうこともあります。
性的マイノリティ
「性的マイノリティ」とは、同性が好きな人や体の性別と心の性別が一致しない人を指します。
近年では「LGBT」と呼ばれていて、その意味はレズビアン(女性の同性愛者)、ゲイ(男性の同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(生まれた時の性別とは違う性別で生きる人)の頭文字を取っています。
性的マイノリティの人は、一般社会からの偏見や差別を受けてしまったり、近しい友人や家族にも相談できない孤独感があったりします。異性愛者中心の社会で生きる中で、同性を好きになることの違和感は大きなストレスになり、親や知人に何気なく「結婚しないの?」と聞かれることにも、負担を感じてしまうことが多いようです。
インターセクショナリティとは
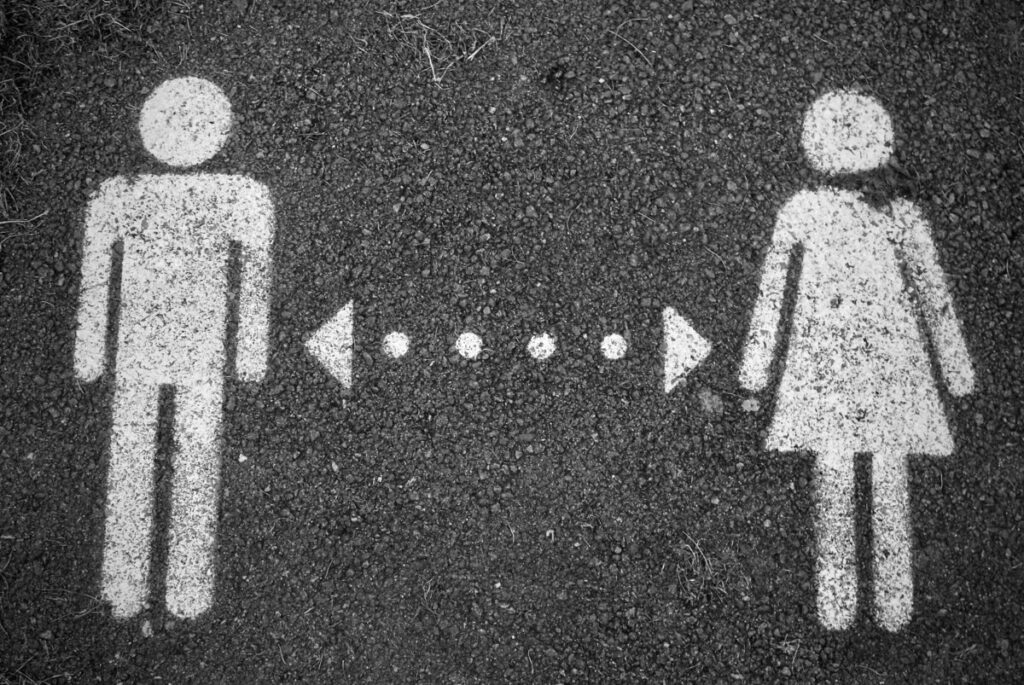
マイノリティやマジョリティ以外に、「インターセクショナリティ」というワードも注目され始めています。
「交差性」という意味があるインターセクショナリティ(intersectionality)。人種や性別、障がいなどマイノリティの属性が2つ以上組み合わさることで起こる差別を可視化して、理解していくための概念とされています。
例えば、少数民族である上に障がい者であったり、難民で性的マイノリティであったりするなど、マイノリティの中でも、さらにマイノリティの人たちと言い換えられるかもしれません。
インターセクショナリティの人は、マイノリティの人以上に社会から取りこぼされてきました。
認定NPO法人ReBitの調査によると、精神・発達障がいのあるLGBTQの人の92.5%が「求職活動でマイノリティに由来した不安や困難を経験した」というデータが出ています。「ロールモデルがいなくて不安だった」「求職活動でマイノリティを伝えたら、合否に影響するかもしれないと不安だった」といった心の声が上がっています。他にも、「面接など選考時の困難やハラスメントを経験した」という人は88.2%にも及びます。
マイノリティの人々が抱える問題を知ろう

ここまで見てきた内容からも、まだまだ社会はマイノリティが生きづらい状況です。しかし昨今では、マイノリティについて、著名人が自ら公表したり企業がメディアで取り上げたりして、その存在が広く知られつつあります。
マイノリティの情報が広まることで、「こういう人がいるんだ」と当事者以外が理解を深めるきっかけになるのです。
マイノリティのことをすべて理解するということは簡単なことではなく、当事者の生きにくさやこうして欲しいという気持ちには、気付けないこともあります。
それゆえにまずは、マジョリティがマイノリティの存在に気付くこと、会社やコミュニティの運営にマイノリティの意見を取り入れること、などを一つずつ実践していくことが重要です。