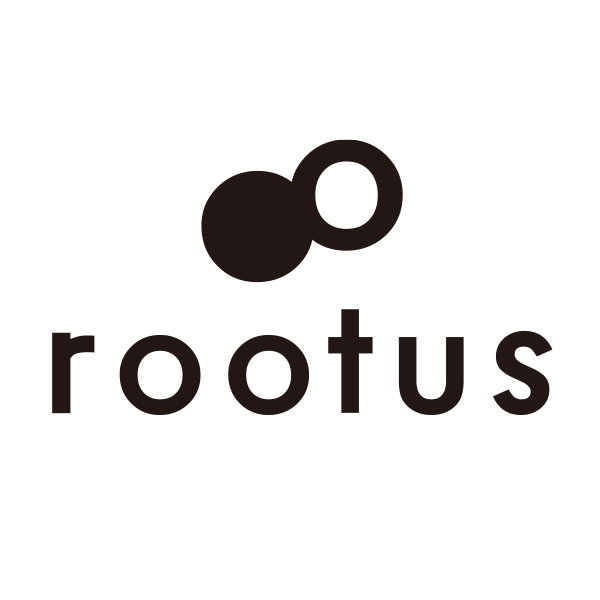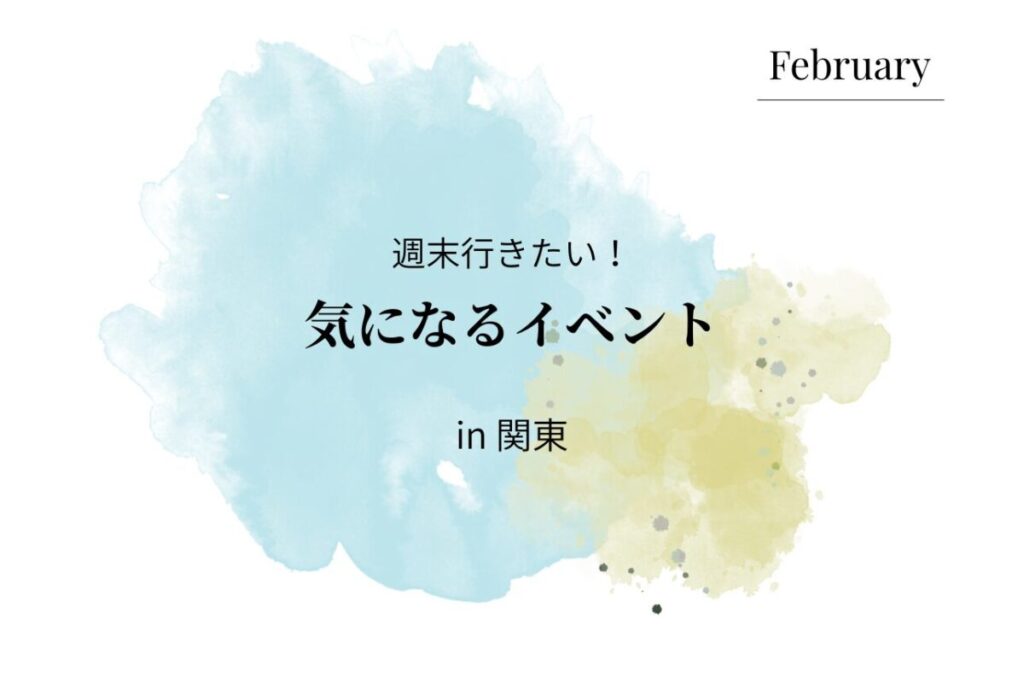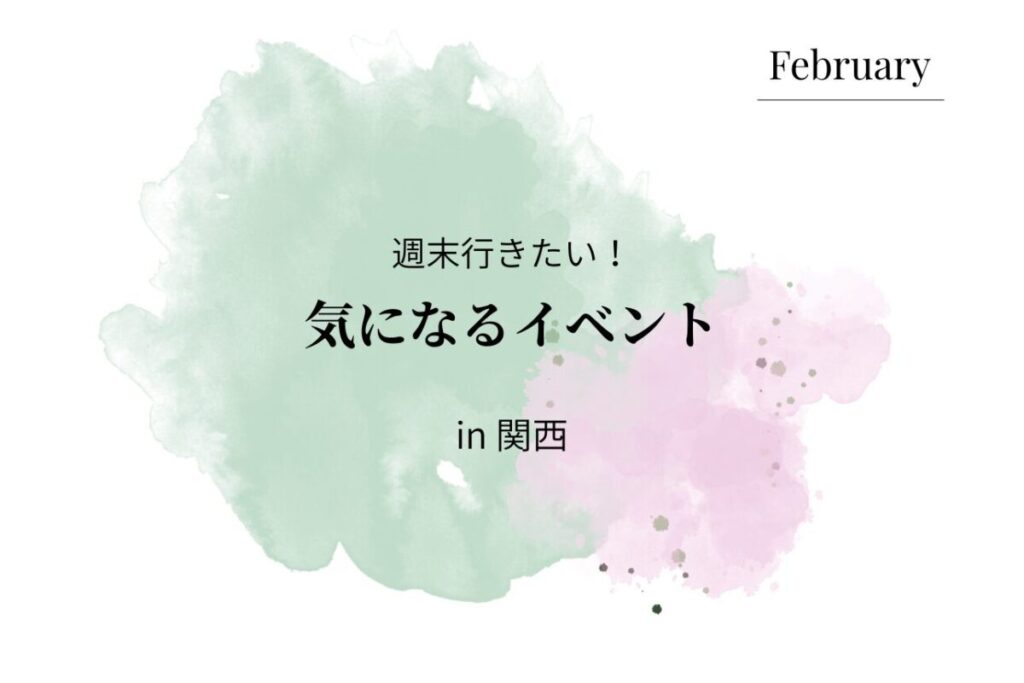近年大きく取り上げられている食品ロスの問題。毎日たくさんの食べ物が無駄になっているなかで、私たちがすぐにできることとは?
食材を選ぶときにできることから、レストランの選び方まで、今日から始められるアクションをご紹介します。
深刻な食品ロス問題の現状

食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のこと。海外でも問題にはなっていますが、日本でもその問題は深刻。農林水産省の報告によると、令和元年度の食品ロスの量は570万トンにのぼり、国民一人当たりの量に換算すると、一人当たり1日にお茶碗1杯分の食べ物が廃棄されていると言われています。
フードロスは、大切な食糧資源を無駄にしているだけでなく、ごみとして燃やす際に出るCO2の排出量も増やすことに繋がってしまうのが、大きな問題です。
フードロスと食品ロスの違い
フードロスと食品ロスは同じような言葉ですが、厳密には違いがあります。
フードロスは、収穫・生産された後、流通の過程で私たち消費者に届く前に捨てられてしまう食品のこと。一方食品ロスは、フードロスに加えて、消費者の手に届いてから捨てられてしまうものを含まれています。
意味が異なるフードロスと食品ロスですが、日本では同じような使われ方をしているケースがほとんどです。
また、規格外野菜などについては、食品ロスの統計には含まれていませんが、廃棄になることも珍しくないため「隠れ食品ロス」と呼ばれることもあります。
家庭で、レストラン選びで食品ロスを少しでも少なく

食品ロスは、大きく事業系食品ロスと家庭系食品ロスに分けられます。令和元年度、事業系食品ロス量は309万トン、家庭系食品ロス量は261万トンでした。
お買い物から調理、食事に至るまで家庭で私たちにできることはたくさんあります。また、外食時は近年増えてきている食品ロスの問題に取り組むレストランを利用することも食品ロスの削減につながります。
食品・食材を購入するときにできること

1.手前取り
最近コンビニなどでも少しずつ見かけるようになった、消費期限や賞味期限が近い食品から購入していく手前取り。食品ロスは消費者である私たちの過度な鮮度志向も影響していると言われています。期限内に食べきれるのであれば、積極的に手前取りを行っていくことが大切です。
2.ロスになりそうな食品を販売するサービスを利用する
食品ロスが出そうなレストランなどの事業者と消費者をつなぐサービスが登場しています。食品ロスの危機にある食品をネット注文できるサイトや、お店に自分で引き取りに行くサービスまで、種類は様々。わかりやすいシステムで、お手頃な価格で購入できるのも嬉しいポイントです。
関連記事:気軽に食品ロス削減に貢献。お得で楽しいショッピングサイト10選
調理するときにできること

1.野菜等の正しい保存法を知る
野菜はその野菜に合った方法で保存するだけで、断然長持ちします。根菜類は常温保存、葉野菜は冷蔵保存など、種類によって適切な温度があります。また、冷蔵庫の野菜室の中で立てて保存した方が良い、などそれぞれポイントがあります。適切な方法を選べば、鮮度を保ったままより長く野菜を使えて、ロスが少なくなります。
https://www.honda.co.jp/tiller/yasai/preservation/
2.「消費期限」と「賞味期限」をきちんと理解する
手前取りとも共通していますが、過度な鮮度志向は食品ロスに繋がります。消費期限は安全に食べられる期限であるのに対し、賞味期限はおいしさなどの品質が保たれる期限です。賞味期限の場合、期限を過ぎたからと言って安全ではなくなる、とは限らないのです。
3.フードロスゼロのレシピをチェック
余りがちな食材や、捨ててしまいがちな野菜の部位。そんな材料を使ったレシピが多く公開されています。食材の栄養をまるごといただけるレシピで、お料理のレパートリーも豊かになります。
https://cookpad.com/kitchen/10421939
https://www.kagome.co.jp/vegeday/eat/202101/10955/
レストラン選びでできること

家庭で出る食品ロスよりも多いのが事業者から出る食品ロスです。外食するときにレストランを選ぶときも少し工夫すれば、食品ロス削減に貢献できます。お店と消費者とが一緒になって、社会全体で食品ロスを減らしていくことが大切です。レストランの食品ロス削減に貢献できるサービスや、食品ロスを出さない工夫をしているレストランがわかる渋谷区の取り組みをご紹介します。
Tabetta
日時や場所、ジャンルを選択すると最適なレストランを選び予約してくれるサイト。急なキャンセルなどが出たお店や食品のロスなどで困っているレストランを通常よりも30%以上安く利用できる。
https://tabetta.jp/
シブラン三ツ星レストラン
渋谷区が、食品ロスの削減、地域環境の美化、ごみの削減に取り組む飲食店を「シブラン三ツ星レストラン」として認証している。食品ロスに関しては、食材の無駄が出ない仕入れの実施や食べ残しが出ないよう、ハーフサイズの提供をしているかなどの認証条件がある。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/gomi/recycle/shiburan_meibo.html
食品ロス削減のために簡単にできることからはじめよう

資源を無駄にして、廃棄が出ることで環境にも負担をかける食品ロスの問題。食べられるのに捨てられてしまう食品を少しでも減らすために、手前取りや野菜の保存方法を見直すなど、今日からできる簡単なことはたくさんあります。また、食品ロス削減に貢献しながら、お得に食材を購入できるサービスなども充実。どれも簡単なので、できるところからはじめてみませんか。