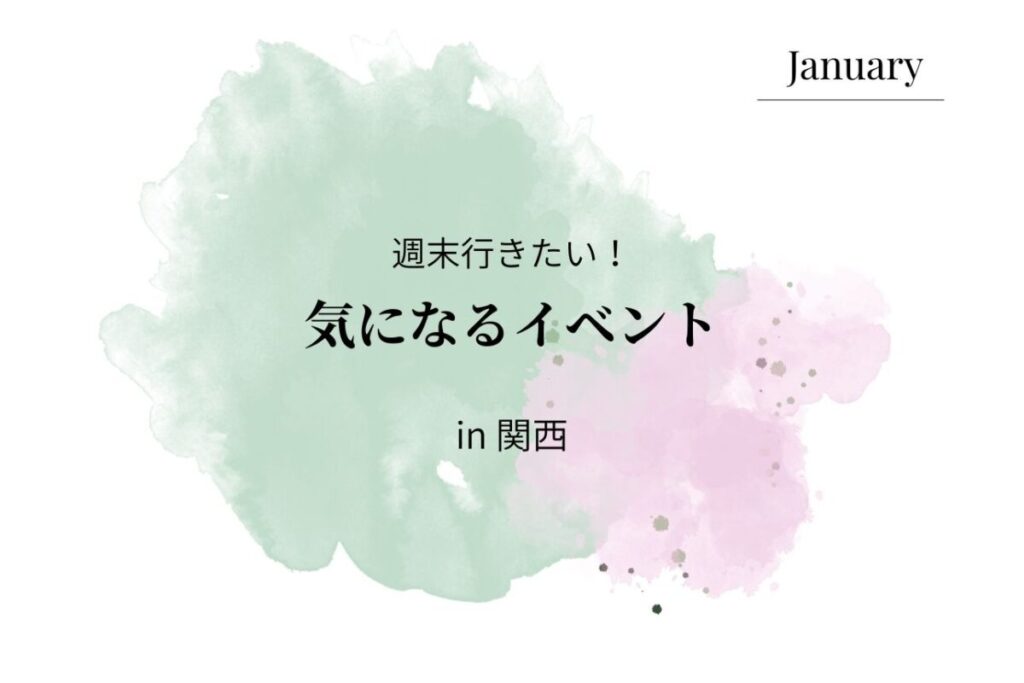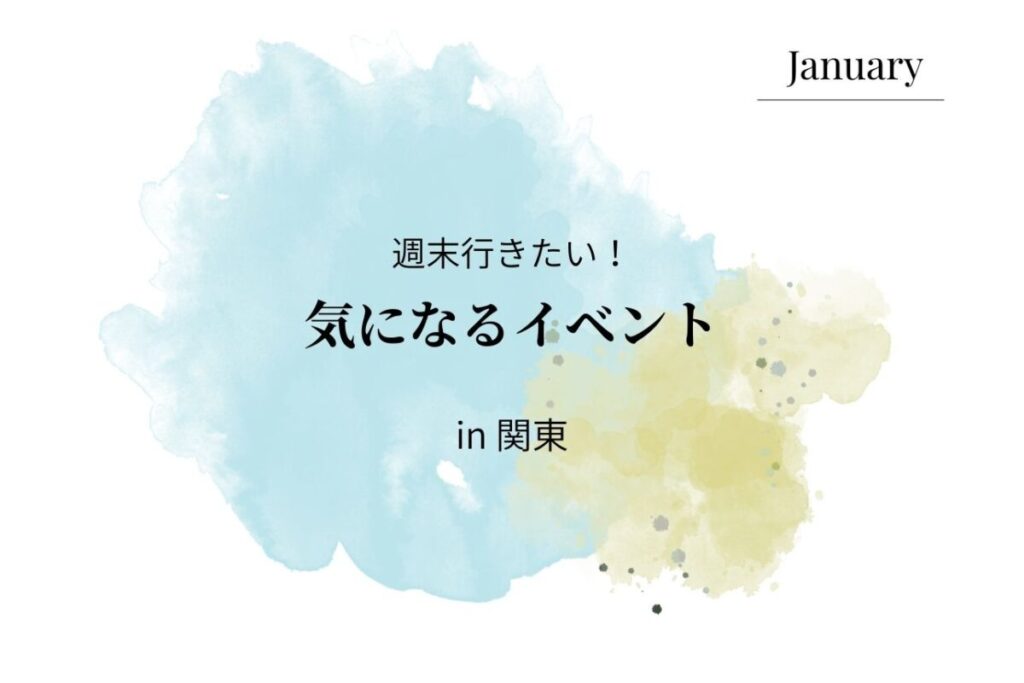美食学と訳されることが多く、高級で芸術的な料理を連想させるガストロノミーという言葉。そのイメージが、今大きく変わりつつあります。
サステナブルな食の在り方や地方創生とガストロノミーが繋がり、新たなムーブメントとなっているのです。その背景と、ガストロノミーを中心とした新たなムーブメントを紹介します。
ガストロノミーとは

ガストロノミーという言葉は、特定の地域の食文化や伝統料理を指すことがある一方、上質な食材を優れた技法で調理し、芸術的に盛りつけるような「美食」を指すこともあります。そのため、ガストロノミーの定義は一様ではなく、さまざまに解釈されているのが実情です。
また、1825年にフランスで出版された「味覚の生理学」において、ガストロノミーは、生産から消費までの過程で美味を探究する原動力であると語られて以降、料理を中心に食や食文化を体系化し科学的に研究する学問としても知られるようになりました。
起源は明らかではありませんが、語源は古代ギリシャに由来し、中世の頃から芸術の題材としても登場することから、美食の象徴として古くから使われていたと考えられています。
サステナブルガストロノミーとガストロノミーツーリズム

ガストロノミーに関するワードとしては、主に以下の2つが挙げられます。これらは、ガストロノミーを中心とした、新たなムーブメントを表すものでもあります。
サステナブル・ガストロノミー
サステナブル・ガストロノミーとは、持続可能な方法で栽培・生育された食材を、なるべく環境や健康に負荷のかからない方法で市場に届け、無駄なく調理・消費することを考慮した料理や食のあり方を意味します。
国際連合食糧農業機関(FAO:Food and Agriculture Organization of the United Nations)を中心に、持続可能な地域の食文化を未来に繋ぐことを目的とした定義が示され、各国、各地域で以下のような取り組みが行われるようになりました。
- 地元の旬の食材を使う
- 認証機関のシーフードを選ぶ
- 食品や包装資材などのロスを削減する
- 有機農業と地域農業を推進する
- フェアな労働、トレード、動物福祉を推進する
- 教育と啓発を行う
ガストロノミーツーリズム
ガストロノミーツーリズムとは、その土地ならではのワインや郷土料理など、食の魅力を観光の中心として捉える旅行のスタイルで、ヨーロッパでは以前から行われていました。
中でも、バスク料理で有名なスペインのバスク自治州のサン・セバスティアンが世界的に注目を集め、この地域が火付け役となり、ガストロノミーツーリズムは国際的な広がりをみせるようになりました。
世界のサステナブル・ガストロノミーの事例

トルコ共和国では、小規模有機農家の支援や伝統食材・料理の保存と継承に力を入れています。一方でEUの基準に適合したオーガニック製品の開発や、サステナブル・ガストロノミーツーリズムの推進も盛んに行われています。
トルコ共和国(Go Turky Experience)
https://sustainable.goturkiye.com/sustainable-gastronomy
日本のサステナブル・ガストロノミーの取り組み

日本でも各地でサステナブル・ガストロノミーの取り組みが進められています。
大分県の臼杵市は、発酵・醸造文化と質素倹約、循環型の食文化が評価され、ユネスコ創造都市ネットワーク(食文化分野)への加盟が認められました。
こういった都道府県による取り組みの他、産官学に現役シェフや醸造家が加わったプロジェクトも各地で盛んに行われています。
また、バイオテクノロジーを活用したフードテック系スタートアップビジネスも、産官学連携がベースになっている場合が多くなっています。
具体的な例をあげると、ふるさと納税で話題になったゲノム編集真鯛は、京都大学と近畿大学の共同研究成果を基に開発された次世代水産養殖システムによる養殖魚です。
その他、環境負荷の少ない陸上での海藻栽培や、永続的な農業のための人工土壌の開発など、さまざまな取り組みが進められています。それらの安全性については、各分野の学者や専門家の間で、慎重であるべきといった声など、賛否両論が存在することを知っておくことが大切です。
賛否両論ある中でも、開発の進行と共に醤油や味噌の醸造家や和食の料理人、三ツ星シェフがプロジェクトに参加し、次世代食材をより美味しく食べるための研究開発も進められています。
こうした取り組み全般の成果を通じて持続可能な食文化を考える場として、京都大学では年に一度、サステナブル・ガストロノミーについてのシンポジウムが開催されています。多くの人が訪れることからも、サステナブル・ガストロノミーへの関心の高さがうかがえます。
世界と日本のガストロノミーツーリズムの事例

サン・セバスティアンをきっかけに世界的に広まったガストロノミーツーリズムは、各国、各地に多彩な事例が展開されていますが、ここでは代表的な3つの事例を紹介します。
アメリカ合衆国オレゴン州のガストロノミーツーリズム
地元農場で栽培されるオーガニック野菜やフルーツ、ワインが豊富。中でも古き良き時代の建物が残る町マクミンビルは、生物多様性を重視した次世代型レストランで食を堪能しながら、自然を満喫できるスポットとして注目が集まっています。
Oregon Coast Visitors Association
https://visittheoregoncoast.com/
国内で楽しむ日本のガストロノミーツーリズム
東と西の都を結ぶ静岡、そして意外と知られていない東京のガストロノミーツーリズムの取り組みを紹介します。
静岡「美味ららら」
https://shizuoka-gastronomy.jp
東京「東京の食の魅力発見の旅」
https://tokyotokyo-delicious-museum.jp/portal/tokyo-gastronomy-tourism
サステナブル・ガストロノミーを知って、豊かな食体験を
サステナブル・ガストロノミーに取り組む地域もまだまだ増えていく気配があります。持続可能な食文化を楽しむ旅のスタイルは、これから世界でも日本でも増えていくのかもしれません。次の旅のプランに「食から始まるサステナブルな体験」を取り入れてみてはいかがでしょうか。