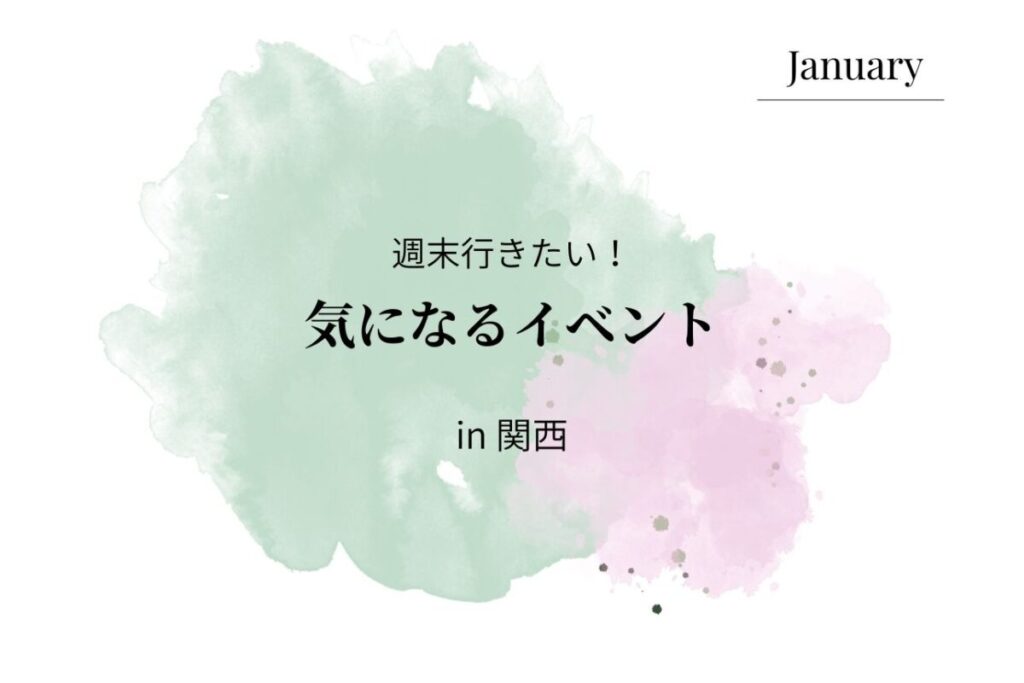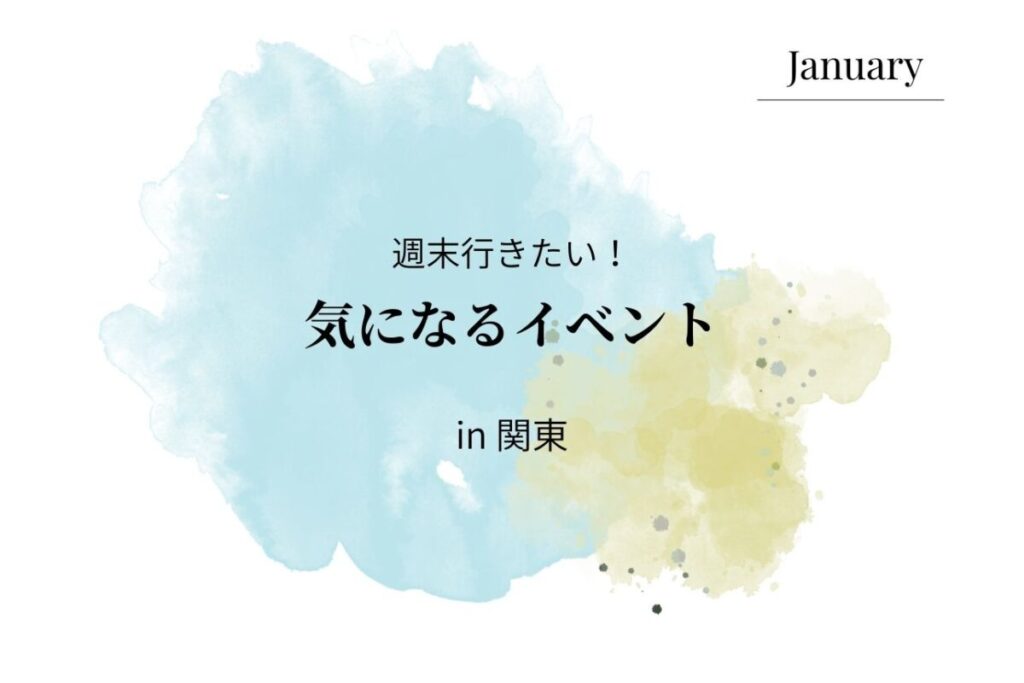「地元に戻ろう」「知らない土地で暮らしてみたい」とふと考えたことはないでしょうか。
地方移住の流れとともにUターンやIターン、Jターンといった言葉を再び耳にする機会も増えましたが、それぞれの違いやメリット・デメリット、具体的な支援制度について、詳しく知る機会は意外と少ないかもしれません。
本記事では、これらの移住スタイルについて、その違いや特徴を整理し、関連する補助金や支援制度の例もご紹介します。
Uターンとは?
就職や転職、また地方創生などのトピックでも目にすることが増えたUターンという言葉、その意味について知っているでしょうか。
Uターンとは、地方で生まれ育った人が、進学や就職のために一度都市部へ移り、その後、再び故郷に戻って働くことを指します。
例えば、地方の高校を卒業して東京の大学に進学し、そのまま東京で就職した人が、数年後に地元に戻り、地元企業で働くケースなどがこれに当たります。
Uターンによって生まれ育った故郷に回帰するという選択は、家族との再会や地域社会への貢献を目指す人々に選ばれるライフスタイルの一つになっています。
Uターンのメリット・デメリット
リモートワークの浸透も追い風となり、再び注目を集めているUターンですが、どんなメリットや、デメリットがあるのでしょうか。
Uターンのメリット
①慣れ親しんだ環境での生活
自身が生まれ育った地域での生活は、環境への適応という面でハードルが低く、生活のストレスを軽減することにつながります。また、地元の文化や習慣に精通しているため、社会的なつながりを再構築しやすいです。
②生活コストの削減
地方では、都市部に比べて物価や地価が低い傾向があります。これにより、生活費や住居費を抑えることが期待できます。
③ワークライフバランスの向上
通勤時間の短縮や自然豊かな環境での生活は、心身の健康維持にも効果的です。また、子育てや介護など、家族との時間を大切にすることができます。
④地域貢献の機会
地元での就業や活動を通じて、地域社会の発展や活性化に直接貢献することができます。こうした志向のある方にとっても好まれる選択肢と言えます。
Uターンのデメリット
①就職先の選択肢の制限
地方では、都市部と比較して企業数が少なく、希望する職種や条件に合致する求人が限られる場合があります。
②収入減少の可能性
生活コストが低減されるということは、賃金水準が都市部に比べると低い傾向にあるということ。そのため、収入が減少するリスクがあります。
③利便性の問題
都市部に比べて、交通機関や商業施設、文化的施設が少ないため、生活の利便性や娯楽性が比較的低いことも、バードルとなります。
④引っ越しや就職活動の費用負担
移住に伴う引っ越し費用や、就職活動のための交通費・宿泊費など、経済的な負担が増加することがあります。
Iターンとは?Uターンとどう違う?
IターンとUターンは、ともに都市部と地方間の移住や転職を指す用語として広く使われています。では両者の違い、Iターンの特徴はどんなものなのでしょうか。
Iターンとは?
Iターンとは、都市部で生まれ育った人が、出身地とは異なる地方へ移住し、就職や転職を行うことを指します。 この「Iターン」という用語は、進路が一直線であることからアルファベットの「I」に例えられています。
例えば、東京都で生まれ育った人が、自然豊かな環境を求めて長野県に移住し、そこで新たな職を得るケースなどが該当します。
Uターンとの違い
先ほど確認した通り、Uターンは、生まれ育った地方から都市部へ進学や就職のために移り、その後再び故郷に戻って働くことを指します。
一方、Iターンは、都市部出身者が縁のない地方へ移住し、新たな環境で生活や仕事を始めることを意味します。
これらの違いは、移住先が故郷か否か、そして移住前の居住地が都市部か地方かによって区別されます。
両者の違いについて整理できたところで、Iターンのメリットとデメリットについても見ていきましょう。
Iターンのメリット
①新たな生活環境でのリスタートができる
都市の喧騒を離れ、自然に囲まれた環境や、地域の人との密な関係性を重視する生活スタイルを選ぶことができます。特に、スローライフ志向やワークライフバランスを見直したい人にとって、大きな魅力となります。
②地域に新しい視点を持ち込める
都市部での経験やスキルを活かして、地域に新しい価値や発想を提供できる可能性があります。地方企業や自治体にとっても、外部人材の視点は貴重とされており、歓迎されやすい傾向も。
③地方移住支援制度が活用できる
多くの自治体では、Iターン希望者に向けた移住支援金や住居補助、就業サポートを提供しています。
Iターンのデメリット
①地域との人間関係の構築に時間がかかることがある
地縁や血縁がないため、地域コミュニティになじむまで時間がかかることがあります。特にやや閉鎖的な風土のある地域では、信頼を得るまで地道な関係構築が求められます。
②生活スタイルのギャップに戸惑うことも
都市部とは違い、交通の便が悪かったり、商業施設・医療機関が限られていたりと、インフラや利便性でギャップを感じる場合があります。特に、日常生活の中で、車が必須になる地域も多い点は大きなギャップの一つです。
③仕事の選択肢が限られる可能性
Uターンと同様に、地方は業種・職種の選択肢が都市部より少ない傾向にあります。特にIターンでは、地元の企業や産業構造に詳しくないこともあり、希望職種に出会うまで時間がかかることも。
近年ではJターンも
さらに、1990年代以降には「Jターン」という言葉も登場しました。
Jターンとは、地方で生まれ育った人が一度都市部へ進学や就職で移住した後、生まれ故郷ではなく、その近隣の地方都市に移住し、就職や定住することを指します。
例えば、青森県出身の人が東京で働いた後、故郷に近い仙台市に移住するケースが該当します。
近年、Jターンが注目されている背景には、いくつかの社会的な変化が関係しています。まず、都市部での生活コストの上昇や通勤ストレスなどにより、よりゆとりのある暮らしを求めて地方への移住を考える人が増えています。加えて、政府や自治体による地方創生政策の推進や移住支援制度の整備により、地方都市への転職・移住が現実的な選択肢として広がってきました。
また、テレワークやリモートワークの普及により、勤務地にとらわれず、自分のライフスタイルに合った場所で働くことが可能になってきたことも、Jターンを後押ししています。
地方移住に向いている人の特徴
UターンやIターン、さらにはJターンについて紹介してきましたが、こうした地方移住は、都市部を離れ、自然豊かな環境や地域コミュニティの中で新たな生活を始めることを意味しています。
しかし、地方での生活は都会とは大きく異なるため、全ての人に適しているわけではありません。では、どのような人が地方移住に向いているのでしょうか。
自然が好きで、のんびりした生活を求める人
地方は自然環境に恵まれ、四季折々の風景やアウトドア活動を楽しむことができます。自然の中での生活に魅力を感じ、ゆったりとした時間の流れを好む人は、地方移住に適していると言えます。
地域の慣習や文化に柔軟に適応できる人
地方には独自の慣習や文化が根付いています。これらを尊重し、柔軟に受け入れる姿勢を持つ人は、地域社会に溶け込みやすいでしょう。
コミュニケーションを大切にし、社交的な人
地方では近所付き合いや地域のコミュニティ活動が盛んです。人とのつながりを大切にし、積極的にコミュニケーションを取ることができる人は、地方での生活をより豊かにすることができます。
新しいことにチャレンジする意欲のある人
地方移住は、新しい環境での生活や仕事に挑戦することを意味します。未知の状況を楽しみ、前向きに取り組む姿勢を持つ人は、移住先での生活を楽しめる可能性が高いと言えます。
自分で生活を切り盛りできる人
地方では、都市部のような利便性がない場合があります。そのため、自分でライフプランを立て、問題を解決する能力が求められます。自己管理が得意な人、好きな人は、地方での生活に適応しやすいでしょう。
Uターン、Iターン、Jターンの支援制度
Uターン、Iターン、Jターンの支援制度を実施している自治体は、全国に多数存在します。どんな支援制度があるのか、その具体例をご紹介します。
支援制度例①高知県
高知県では、「高知家で暮らし隊会員制度」という無料の会員制度を実施しています。これは、高知県出身の方や、高知へのU・Iターンを考えている方を対象にした制度です。
登録すると、U・Iターンに役立つ最新情報がメールで届くほか、レンタカーや引越し費用の割引など、うれしい特典も充実しています。さらに、定期的に開催されるアンケートの抽選会や、会員限定の交流イベントにも参加できます。
また、「高知県への移住に興味はあるけれど、県まで足を運ぶのは難しい」といった声に対応するため、高知県では「移住支援特使」という制度を設けています。
この制度では、高知県にゆかりのある方や、「高知家」の取り組みに共感した県外在住の民間企業の方などに、移住に関する情報提供や相談の窓口として協力を依頼しています。
支援制度例②島根県
島根県では、県外からの移住を希望する人や、移住して間もない人を対象に、「U・Iターン応援カード制度」を実施しています。この制度は、移住に関する経済的なハードルや生活上の不便さを少しでも下げることを目的としたもので、宿泊施設や引越し、賃貸物件の契約、教習所の利用など、暮らしに関わる様々なサービスで割引や特典が受けられるのが特徴です。
対象となるのは、島根県外に住むU・Iターン希望者、18歳以上の学生、そして移住して1年以内の人です。協賛店舗やサービスは県内に200以上あり、今後も拡大が予定されています。
移住の検討段階から、実際の引越し、移住後の暮らしまで幅広くサポートしてくれる制度として、島根県ならではの移住支援の一つとなっています。
支援制度例③秋田県
秋田県の実施するAターン制度は、秋田県へのUターン・Iターン・Jターンを包括的に支援する取り組みで、「秋田(Akita)」と「All Turn」をかけています。県外在住者を対象に、秋田への就職・移住を支援する情報やサービスを提供しています。
利用者は「あきた就職ナビ」に登録することで、個別にカスタマイズされたマイページを持つことができ、企業情報や求人情報、イベント案内、市町村の移住支援情報など、さまざまな最新情報を受け取ることができます。
秋田での就職や移住を検討している人に向けて、情報提供だけでなく実際の行動に移すためのサポート体制を整えた仕組みになっているのです。
移住支援金や補助金の事例
UターンやIターン、Jターンを促進する支援の取り組みは、補助金や支援金といった形でも進められています。
国の整備する移住支援金
地方への移住や定着を後押しするため、国(内閣府地方創生推進事務局)は「移住支援金」や「起業支援金」といった経済的支援制度を整備しています。これらは各自治体を通じて実施されており、移住者が地方で新たな生活や仕事を始める際の初期費用負担を軽減することを目的としています。
「移住支援金」は、東京圏から地方へ移住し、中小企業などに就職したり起業したりする人を対象に、最大100万円(単身の場合は最大60万円)を支給する制度です。
また、地域課題の解決に取り組む「社会的事業」を地方で立ち上げる人には、最大200万円の「起業支援金」が用意されています。両制度を併用すれば、最大で300万円の支援を受けることも可能です。
自治体の実施する各種補助事業
国の整備する支援金の他、各自治体においても移住者を増やすための支援が行われています。
新潟県上越市では、市外からの移住・定住(U、I、Jターン)を促進し、市内の空き家を有効に活用するため、「空き家定住促進利活用補助金」を設けています。この制度では、空き家などのリフォームにかかる費用の一部が補助されます。
また、福島県南会津町では、町内で創業する方を対象に、事業にかかる経費の一部を補助する「ビジネスチャレンジ支援事業補助金」を実施。こちらの制度は、地域での事業活動を後押しし、経済の活性化や雇用の創出を目的としています。
さらに、静岡県富士市では、子育て世帯(6歳未満の子どもとその親がいる世帯、または母子手帳の交付を受けた妊婦がいる世帯)が富士市に再転入した場合を対象に、各種費用を最大50万円まで補助する「富士市子育て世帯Uターン支援補助金」制度を実施しました。
ここでご紹介した補助金制度は、ほんの一例にすぎません。各自治体によって制度の内容や条件などは異なります。
制度が充実し、移住する人に優しい社会に
本記事では、UターンやIターン、さらにJターンについて解説してきました。それぞれ意味は異なるものの、住む場所を移すことを指しています。
多様な生き方や働き方に興味を持つ人が増加する中、移住する方が増えてきました。各自治体でも受け入れのための制度が拡充されつつあるので、少しでも興味を持った方は、まずは各自治体のホームページをチェックしてみてはいかがでしょうか。「こんなサポート制度があるんだ」という発見があるかもしれません。
参考:
高知県移住ポータルサイト「高知家で暮らす。」
しまね移住情報ポータルサイト「くらしまねっと」
公益財団法人秋田県ふるさと定住機構
内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」
上越市,南会津町,静岡県富士市の移住定住応援サイト「富士市移住コトハジメ」