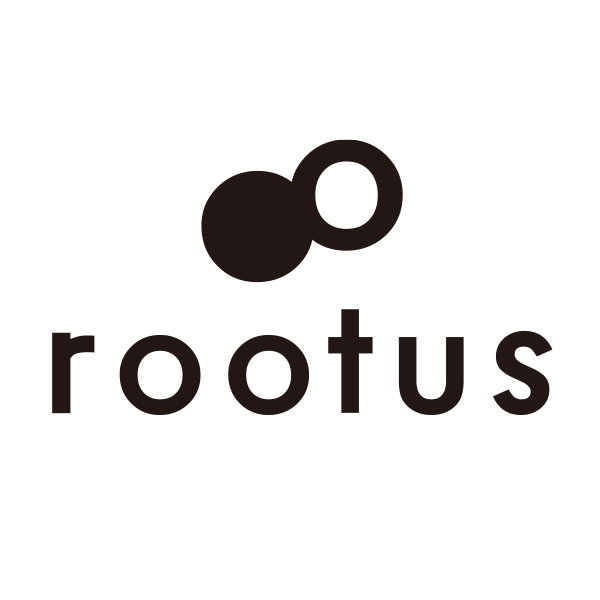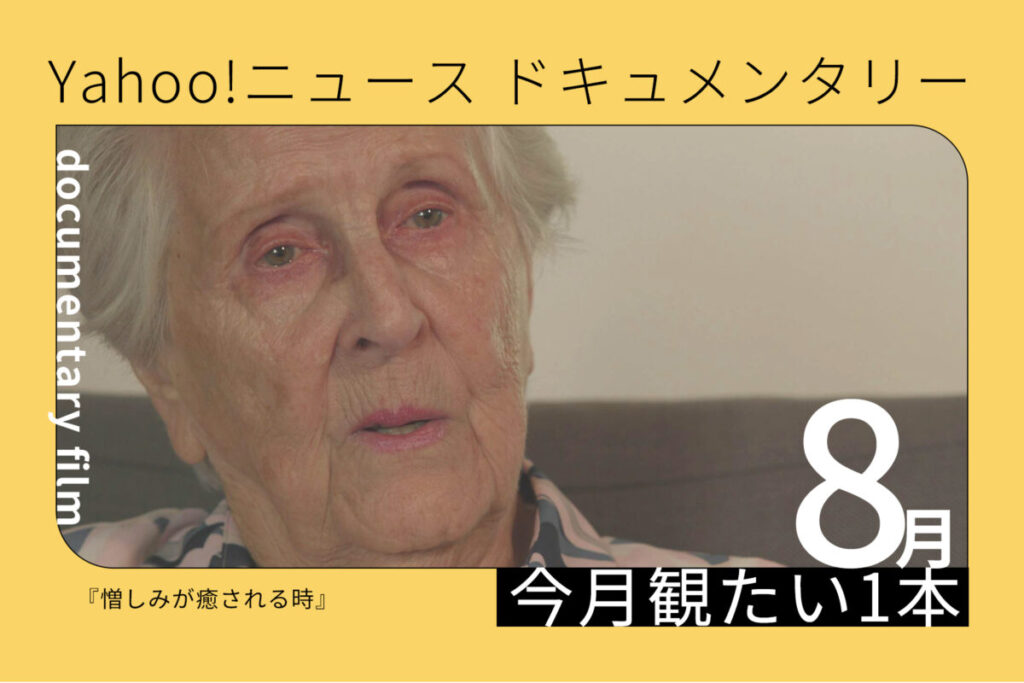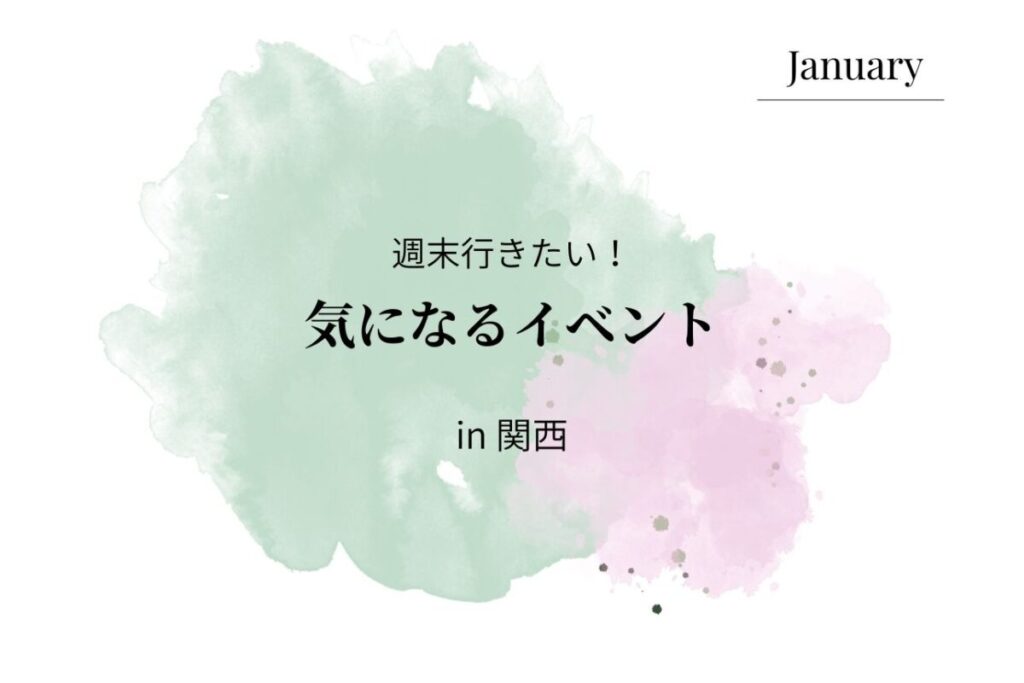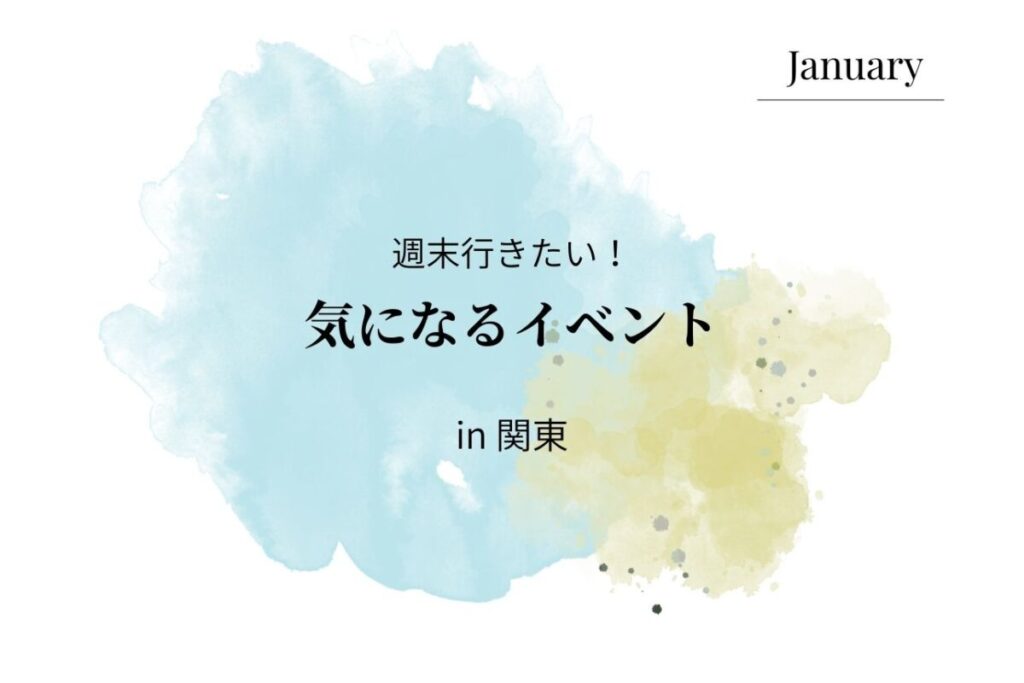東京、神田に画期的なコーヒーショップがあるのをご存知でしょうか。ソーシャルグッドロースターズ千代田は、福祉施設でありながら、こだわりのコーヒーを提供するコーヒーショップです。今世界が未来に向けて目指す、「誰一人取り残さない社会」はどのように作られるのか?そのヒントを探すため、商品のクオリティだけでなく、コーヒーに関わる人たちに重きを置くソーシャルグッドロースターズを取材しました。
新しいかたちの福祉施設

平日の昼下がり。ソーシャルグッドロースターズには、近隣に住む人や、オフィスで働く人々が一杯のコーヒーを求めて次々と来店する。
コーヒーの香ばしい香りが充満する店内は、生豆の選別や焙煎、接客、コーヒーのドリップなど、それぞれの仕事に取り組むスタッフで活気づいている。
ソーシャルグッドロースターズが他のコーヒーショップと違う点は、焙煎所を兼ねるロースタリーカフェでありながら、障がいがある人が働く福祉施設でもあるという点だ。ここでは様々な障がいのある人たちが、コーヒーづくりから接客に至るまで、それぞれ得意な分野を担当しながら専門的な経験を積める就労の場として活用している。
はじまりは障がい者の働き方の現状を知ったこと
ソーシャルグッドロースターズを運営する一般社団法人ビーンズ代表の坂野さんは、障がい者の方と一緒に外出するボランティアをしていた際、本人やその母親から働き先がない、と聞くことがよくあったと言う。
「実際に障がい者の人と一緒に仕事を探してみると、働き先の数はあるものの、職種が極端に少ない状況でした。どうしても単純作業が多く、やりがいやスキルアップの機会を見いだせない仕事が多かったのです。それは高い離職率からも顕著でした。そこで、障がい者の人も、社会で働く他の人々と同じように、技術を習得でき、自分の仕事に誇りを持って働けるような福祉施設を作りたいと思い、このような場所を立ち上げることになりました。」
“障がい者でもできる仕事”ではなく、“みんながやりたいと思えるような仕事”で、スキルも身に着けられるような仕事を、と選んだのがコーヒーショップだった。
一人ひとりの個性が生かされたコーヒーづくり

ここでのコーヒーづくりは、人の手で生豆をひとつひとつ選別するハンドソーティングから始まる。農産物である生豆の中には虫が食っているものや欠けている豆があり、それが入ってしまうと雑味に繋がるとされるため、取り除く必要があるのだ。簡単なようで、意外と難しいハンドソーティングは、集中力と根気がいる作業だ。
選別された豆は、世界でもトップクラスの焙煎機「GIESEN」で焙煎。
ブレンドの作業では、一人ではなく味覚の鋭い障がい者を含めたスタッフ数人で行い、調整して本当に美味しいと思えるものに仕上げている。
そして最後にコーヒーは、ハンドドリップで一杯ずつ丁寧に淹れていくか、バリスタの手によってエスプレッソマシンで淹れられ提供される。
このように、ハンドソーティングからはじまり、焙煎、ブレンド、ドリップ、接客に至るまで、たくさんの役割がある中、スタッフは、それぞれが自分の能力を発揮できる持ち場についている。美味しいコーヒーをつくり提供するという共通のゴールを持ちながら、個性を生かし、尊重し合いながら働いているのだ。
社会の一員として誇りを持って働ける現場を

ソーシャルグッドロースターズでは、立ち上げの際の設備投資を惜しまなかったと坂野さんは話す。
「みんながチャレンジしていける場を作りたかったんです。そのためには世界レベルの焙煎機やエスプレッソマシンが必要だと思いました。最初は誰一人として機械の使い方がわからなかったんですよ(笑)でも今は、使いこなせるスタッフが数名います。」
実際にここで働くことで一人ひとりの知識や経験値、技術が向上しているのだ。
「スタッフには、福祉施設だということをアピールしないで下さいよ、と言われます。障がいのあるなしに関わらず、全員が社会で働く一人として、プライドを持って働いてくれているんです。」
お店でコーヒーが作られていく過程を見ると、どの工程も訓練やスキルがないと難しい。そして出来上がったコーヒーも一流のコーヒーショップと遜色がない。
声を掛け合う和やかな空気が流れる中、スタッフがそれぞれの仕事に熱中する様子からは、美味しいコーヒーを作りたいという意気込みが伝わってくる。
どこまでも平等であることを追求する

ソーシャルグッドロースターズで仕入れる豆は、インドのコーヒー農園からフェアトレードで購入している。持続可能なコーヒーの生産を目指すコーヒーサプライヤーであるオリジンコーヒーグループと「人に優しいコーヒーを」という思いを一緒に、できるだけコーヒー生産者に売り上げを還元できるような仕組みを整えた。
豆が生産されてからお店に届くまで、どこにどのくらいコストがかかっているか、徹底的に透明化。ソーシャルグッドロースターズでは、その詳細を毎回仕入れごとに確認している。
社会にとって平等であるか、ということをどこまでも追及しているのだ。
一杯のコーヒーを通して見えてくるこれからの社会

名前の通り、「ソーシャルグッド」な流れを生み出すソーシャルグッドロースターズ。ここにいると、「誰一人取り残さない社会」とはどんなものなのか、一杯のコーヒーを通して見えてくる。
障がいのあるなしに関わらず、一人ひとりの多様性を認め合い、みんなが平等に社会の一員として活躍できること。そしてそれが社会にとって良い循環を生み出していくこと。美味しいコーヒーとともに、誰もが大切に思われる社会の重要性を考えさせてくれる貴重なコーヒーショップだ。
ソーシャルグッドロースターズ千代田
東京都千代田区神田錦町1-14-13 LANDPOOL KANDA TERRACE 2F
10:00~18:00日曜定休
・都営新宿線/三田線/東京メトロ 半蔵門線「神保町駅」徒歩6分
・都営新宿線「小川町駅」徒歩2分
・東京メトロ 丸ノ内線「淡路町駅」徒歩2分
・東京メトロ 千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩2分
・JR/つくばエキスプレス/東京メトロ 日比谷線「秋葉原駅」徒歩12分
https://sgroasters.jp/