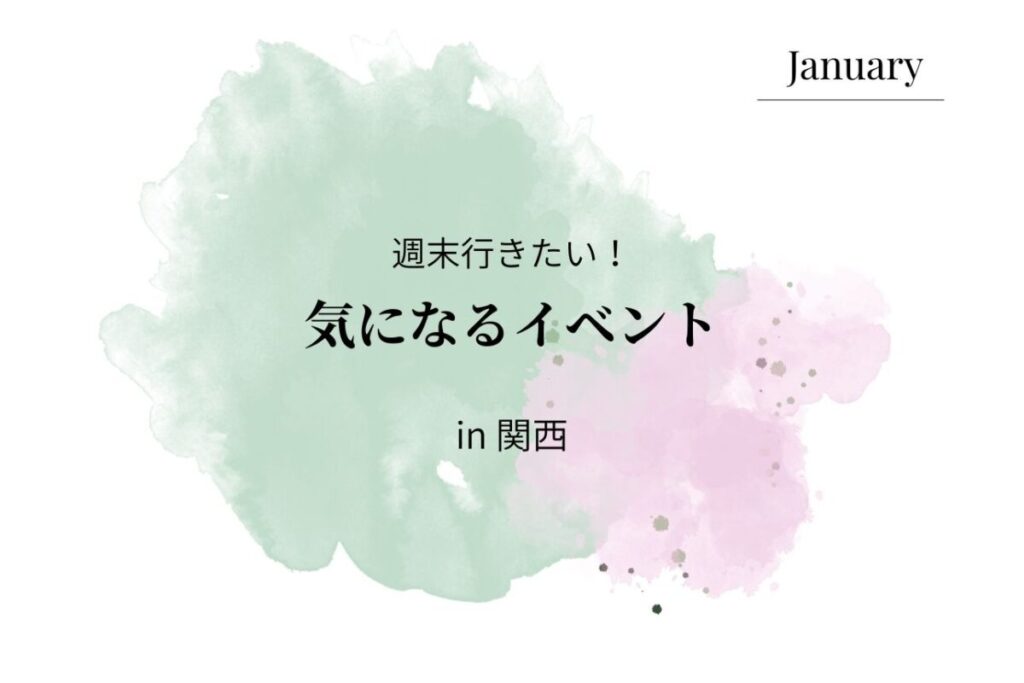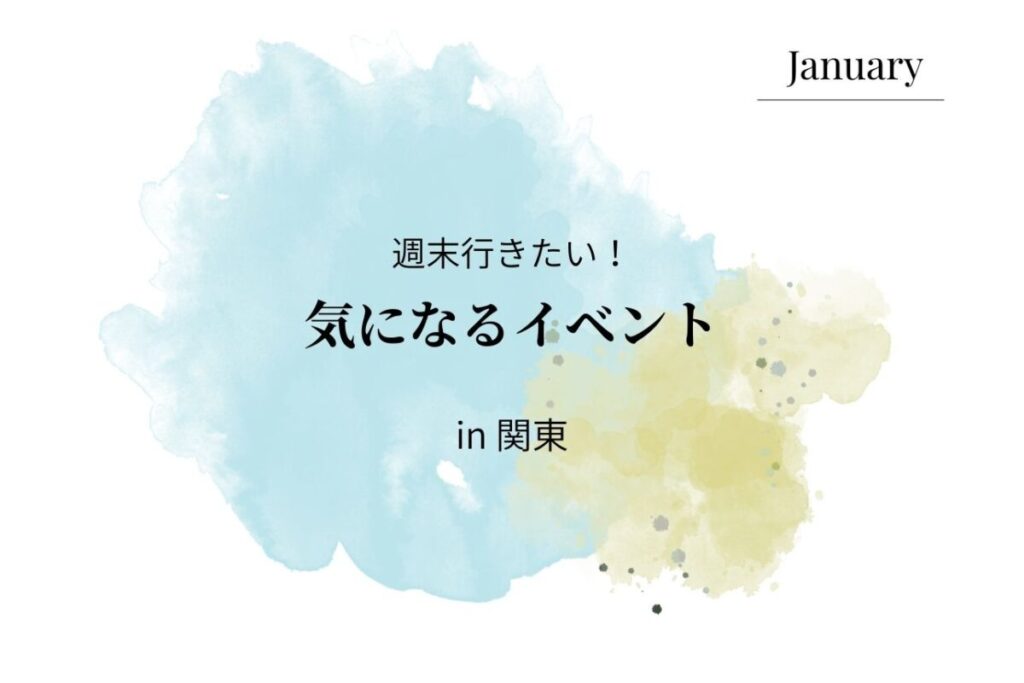働いてお金を稼ぎ、そのお金で生活をする。それが当たり前の世の中ですが、近年「ベーシックインカム」という新しい概念が登場しています。ベーシックインカムとはどんなものなのか、世界の事例とともにご紹介します。
ベーシックインカムとは?

ベーシックインカムとは、政府が国民全員に対し決められた額のお金を定期的に支給する社会保障制度のことで、最低所得保障制度とも呼ばれています。
これまでの社会保障と大きく異なる点は、個人の労働収入や保有資産など、受給資格や条件が設けられておらず、無条件で国民全員が受け取れることです。
個人が一定の生活資金を恒久的に得られるベーシックインカムは、21世紀の新しい資本主義のあり方として世界の行政からも注目を集めています。
ベーシックインカムのメリット
ベーシックインカムが導入されるとある程度の収入が保障されるため、「生きるために働く」状態から脱し、最低限の生活を維持できるようになります。その結果、以下のようなメリットがあると期待されています。
・貧困の解決や対策になる
・少子化の解消に繋がる
・長時間労働の削減や労働環境の改善
・多様な生き方が可能になる
また、国民全員に一律で支給することから、社会保障制度を簡略化や生活保護の不正受給問題の解決にもつながります。管理が効率化されるため、支給される側だけではなく、する側にとっても大きなメリットとなります。
ベーシックインカムの課題
一方で、ベーシックインカムを導入する場合は以下のような課題があります。
・財源の確保
・従来の社会保障制度の見直し
・個人の労働意欲や企業の競争力の維持
他に、適切な支給額の算出が難しいという問題もあります。そのため、本格的に導入する前に大規模な実証実験を行い、支給額に対してどの程度の効果と影響があるかを検証する必要があるでしょう。
ベーシックインカムはなぜ注目されている?

ベーシックインカムは、コロナ渦をきっかけに訪れた経済危機をきっかけに、実施を検討する国や自治体が増加しました。
日本においては、進む少子高齢化で年金制度への不安が増していることや、AIの発展によって失業者が増える可能性があるといった社会背景も脚光を浴びている一因です。
“わたしたちは、持続可能な世界を築くためには、極度の貧困をふくめ、あらゆる形の、そして、あらゆる面の貧困をなくすことが一番大きな、解決しなければならない課題であると、認めます。”
SDGsの前文で上記のように宣言されていることからわかるように、貧困問題や格差の是正は世界的に大きな悲願であり、ベーシックインカムが有効な手段のひとつとして各国で模索が進んでいるのです。
ベーシックインカムの導入国と成功例
ベーシックインカムは、“全員が国からお金をもらえる”という一見夢のような話ですが、実際に導入された場合に社会は正常に機能するのでしょうか。
実はコロナ禍以前からベーシックインカムの議論はされていて、ベーシックインカムの導入に向けて条件を絞った実証実験を行っている国や自治体は多くあります。それらの事例から、成功例を3つお届けします。
ブラジル

ブラジルでは2004年に「市民ベーシックインカム法」が成立。その第一段階として、最も困窮している層を対象に給付する政策「ボルサ・ファミリア」が始まりました。2023年からは「新ボルサ・ファミリア」として給付が始まり、平均給付額は714 レアル(約2万円)に。受け取れる基準が変更され、対象は2,080万世帯まで拡大する見込みです。
ブラジルでは、市単位でもベーシックインカム支給の動きがあります。リオデジャネイロ州のマリカ市では、2013年から貧困層を対象に給付を開始。コロナ禍で額が上がり、3人家族なら1ヵ月あたり日本円で約1万9000円の支給が行われています。特筆すべきは、市内の加盟店でのみ使える現地通貨「ムンブカ」をカードやスマートフォンへチャージして使用するという点です。これにより地域経済の活性化と雇用の促進が期待でき、人々がベーシックインカムを何に使ったのかなど、消費動向データを収集し分析できるようになっています。
フィンランド

2017年1月から約2年間の期間で、失業者からランダムに選出された2,000人を対象に毎月560ユーロ(約7万円)が無条件で支給されました。
フィンランドの社会保険庁は、「人々の労働日数にほぼ変化は見られず、勤労意欲に変化がない傾向がある」と結果を発表。劇的な雇用の改善には繋がらなかったものの、悪化もしておらず、ベーシックインカムの懸念として挙げられることの多い「勤労意欲の低下」は見られない結果となりました。
また、生活保障を得たことでライスワーク(生きるための仕事)から脱し、起業などのライフワークへ挑戦する意欲が高まったとポジティブな回答も見られました。
カナダ

2017年7月から、オンタリオ州では約4,000人を対象におよそ所得の約50%を給付するベーシックインカムの実験を開始。
3年続くはずだった実験は、多大なコストを理由に1年で終了となったものの、参加者へのインタビューでは、タバコやアルコールの摂取が減ったという例や、うつ状態から回復し社会復帰のために職業訓練に通い出したという例もあり、心身の健康状態へポジティブな影響が見られました。
ベーシックインカムの導入国は増える?
ベーシックインカムは、貧富の格差を解消し社会保障制度を単純化するなどのメリットがありますが、実証実験を行ったものの本格的な導入には至らないケースが多いこともあります。足踏み状態となる原因として、まず財源確保の課題があります。
例えばブラジルのマリカ市は油田を持ち石油会社からの税収で財政が潤っているため、コロナ渦でもベーシックインカムで多くの市民の生活を支えることができました。しかし、これは稀なケースと言えるでしょう。
他にも、日本を含む社会保障が手厚い国では従来の社会保障とベーシックインカムのバランスをどう調整していくかという点も議論の焦点となっていくでしょう。
まだまだ発展途上のベーシックインカム。SDGsで貧困をなくすことが目標とされ、AIが進歩が目覚ましい中、どのような国や地域がどのような施策を打ち出していくのでしょうか。これからのベーシックインカムにますます注目が集まりそうです。