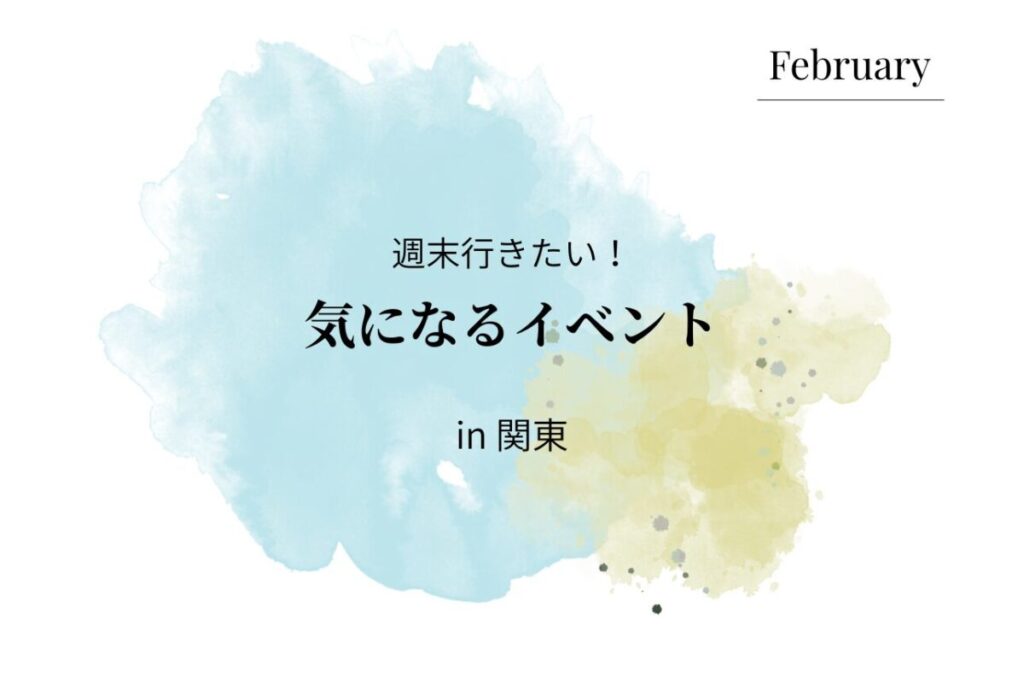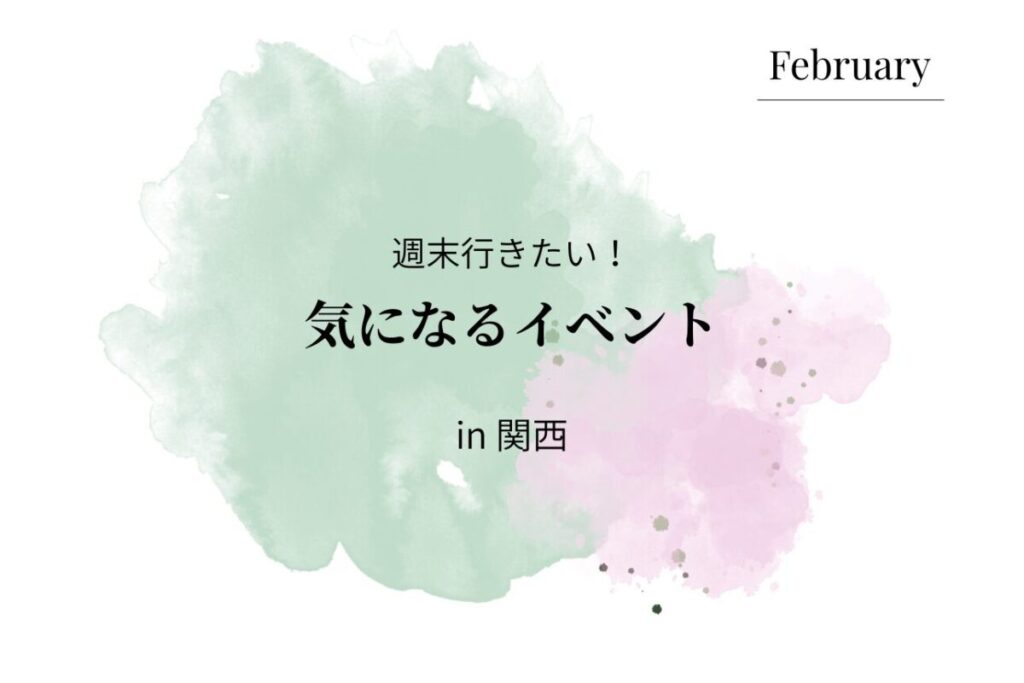日常生活の中で 「エコ」や「環境にやさしい」という言葉を見ない日はないほど、社会では環境に配慮する風潮が高まっています。気候変動など地球レベルの社会問題に対応するため、あらゆる業界が脱炭素や環境配慮の方向へとビジネスの舵を切っていますが、その中で生まれた新たな問題のひとつがグリーンウォッシュです。
消費者や企業は何に気を付ければいけないのでしょうか。グリーンウォッシュへの対応策を学んでいきます。
グリーンウォッシュ(Greenwashing)とは
グリーンウォッシュ(Greenwashing)とは、その実態は環境配慮がなされていないのにも関わらず、消費者に商品やサービスがあたかも環境に良いものだと見せかけることです。
“うわべだけ”や“ごまかし”を意味する「ホワイトウォッシュ」と“エコ”や“環境に良いこと”を意味する「グリーン」を組み合わせた造語で、1980年代に米国の環境活動家ジェイ・ヴェステルフェルトが使い始めたとされています。
サステナブルな社会が目指される中で、グリーンウォッシュは商品を購入する消費者はもちろん、販売する企業担当者も留意するべき点を知り、気を付けなければならない問題です。
どんなものがグリーンウォッシュになる?

ここではグリーンウォッシュについて、具体的にどんなことに留意するべきか見ていきましょう。
米国の第三者安全科学機関であるULソリューションズが、消費者のためのグリーンウォッシュ判断基準である「グリーンウォッシュ7つの罪(Sins of Greenwashing)」を発表しています。
1. トレードオフの罪:環境に配慮している点のみ主張し、他方でより大きな環境負荷が発生していても隠ぺいする
2. 証拠のない罪:十分な証拠や根拠を提示していない
3. 曖昧さの罪:環境配慮に対する定義が不十分である
4. 偽りのラベルを表示する罪:あたかも第三者から認められたような偽のラベルを表示する
5. 無関係の罪:環境にやさしいものを求める消費者には関係のない、環境に関する事実を並べる
6. 2つの悪のうち小さい方の罪:製品カテゴリー内で比べて環境負荷が低いことを主張し、全体から見ると環境負荷が高いことから視点をずらす
7. ねつぞうの罪:虚偽を記載する
以上の「グリーンウォッシュ7つの罪」をより具体的な例で見てみましょう。もしかすると思い当たる商品やサービスがあるかもしれません。
・化石燃料へ投資しているにも関わらずそれは公開せず、自社の行う植林活動だけをピックアップして自社HPに記載する
・十分な根拠がないのに、生分解性プラスチックのカトラリーを「土に還る」と表現する
・環境配慮への生産背景が見えないにも関わらず「エコ・フレンドリー」をうたう
・独自基準で作成したエコラベルを第三者機関が関わっているかのように見せかけ、商品に記載する
・根拠のないファッションアイテムに緑色や自然をイメージする画像を使用した広告
・環境負荷が高いと言われる飛行機だが、「他社よりも環境負荷が低い」とアピールする
・エコな要素がないのに、エコであると主張する
なぜグリーンウォッシュは問題になる?

企業は自社製品やブランド価値向上のためのツールとしてエコや環境配慮といったイメージを利用しているケースがあります。事実に基づいたものであれば何ら問題はありませんが、消費者に誤認させてしまうことが大きな問題に繋がります。グリーンウォッシュによって引き起こされる問題を見ていきましょう。
1. 環境のことを考えたアクションが実は環境に良い影響を与えていない
真っ当なグリーン製品であれば、環境負荷を減らし気候変動問題に少なからず寄与するはずです。しかしグリーンウォッシュの製品やサービスでは「見せかけのエコ」であることから、エコだと思ってアクションをしているはずなのに、環境のためではなく、企業の売上に貢献しているだけの場合があります。
2. 消費者が本物のエコな製品・サービスを見つけることが難しくなる
環境負荷の低い製品と、見せかけの製品が混在することにより、消費者は嘘のない製品を選ぶのが難しくなってしまいます。
3. 企業イメージの損失
企業がグリーンウォッシュだと消費者や国から指摘されることは、消費者と企業の信頼関係が揺るがされる事態に発展します。事実が明るみに出れば利益を失うことはもちろん、企業イメージの損失など大きな代償が伴います。
各国で進むグリーンウォッシュの規制

世界では今、企業やサービスに対する告発や懲罰の例が既に存在し、未然防止のための規制強化が進んでいます。近年の事例を見ていきましょう。
2022年には、アメリカのFTC(Federal Trade Commission:米連邦取引委員会)が、製品の素材にレーヨンが使われているのにもかかわらず竹が使われていると虚偽の表示を行い、あたかも環境にやさしいかのように販売していたとして、大手スーパーマーケットのウォルマートと大手百貨店のコールズに対し、2社合わせて550万ドルの民事制裁金を請求しました。
同じく2022年、日本では、レジ袋やごみ袋などが「生分解性である」など環境に配慮した製品であると表示していたにもかかわらず、それを裏付けする根拠がないとし、消費者庁が10社に対して、処置命令を出しています。
欧州でも各国で規制の整備が進んでいます。英国の競争・市場庁(CMA)は21年9月にグリーンクレームコード(環境配慮の主張に関する指針)を発表。フランスでも同年の21年4月に規制法が採択され違反した広告には広告費の最大8割の罰金を課されます。
直近では2023年3月には「グリーンクレーム(環境主張)指令」提案が欧州委員会により採択されました。これにより、企業側は国際認証などパブリックな認定を受けた根拠を示すことでのみ「エコ・フレンドリー」などの表現を使用することができることとなります。企業側は独自の判断ではなく、第三者機関などによる認証を得ることが求められ、消費者はグリーンクレーム指令を理解するとともに、購入前に正しい基準に則った認証マークが付与されているか確認することが求められます。
消費者にできることは?

消費者にできることとしては、「環境に優しい」、「エコ」など、一見イメージの良いキャッチコピーを鵜吞みにせず、どういった点がサステナブルなのか、地球環境にやさしいとする根拠の提示がなされているか、一度立ち止まって確認することが大切です。また企業へ直接問い合わせることで本当に環境にやさしいのかを知ることができる上に、企業側に情報公開の要望があることを知ってもらう機会になります。
企業も十分に気を付けたいグリーンウォッシュ

消費者庁が証拠不十分の生分解性ゴミ袋の会社に措置命令を出したように、今後さらに監視の目は厳しくなるかもしれません。また、グリーンウォッシュだと指摘された場合のイメージの損失ははかり知れないものです。
企業側も意図せずグリーンウォッシュをしていることがないよう、十分にグリーンウォッシュについて知り、適切なマーケティングを行っていく必要があります。
イメージに流されず、本当に必要なものを選ぼう
2020年、欧州委員会は、環境配慮をうたう製品やサービスの実に40%に「根拠がない」という発表をしました。残念なことに日本企業の商品やサービスにもグリーンウォッシュは数多く潜んでいるのが現実です。グリーンな製品を購入するときは、グリーンウォッシュに加担しないためにも、ぜひその生産方法などをチェックしてみてはいかがでしょうか。