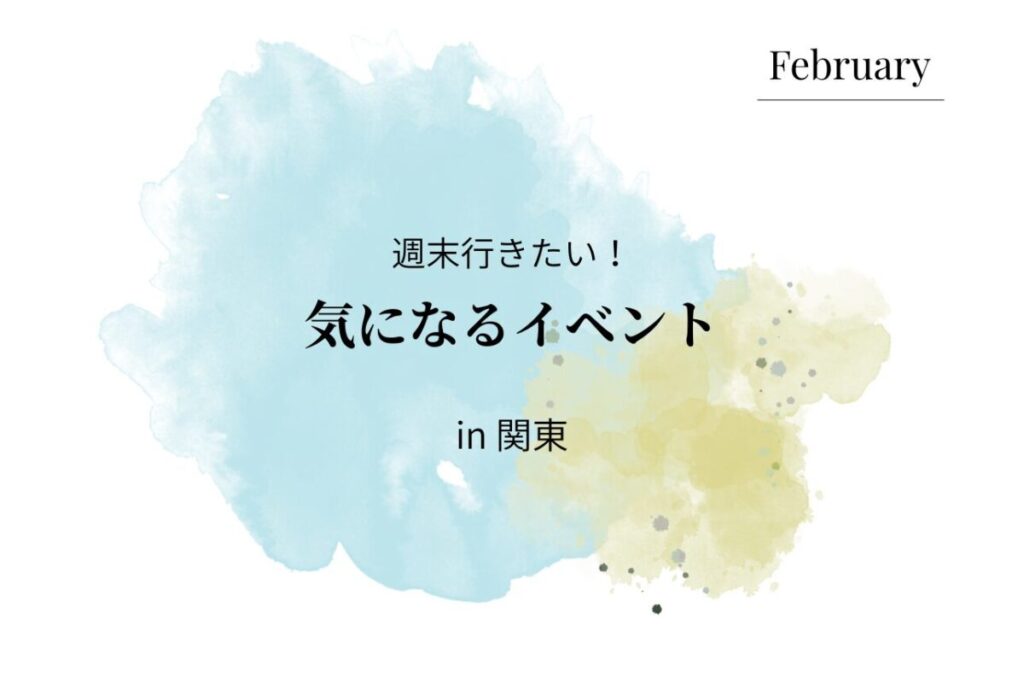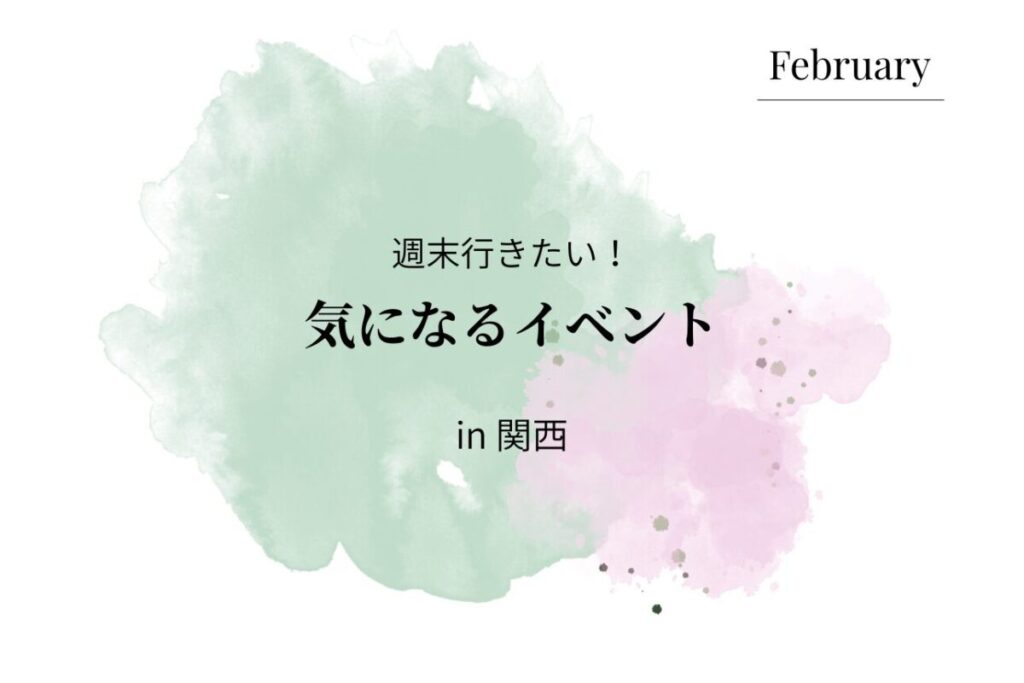現代の私たちの衣生活には、切っても切り離せない存在のファストファッション。手軽におしゃれを楽しみたいときには、安価でトレンド感があるファストファッションのお店やECショップが便利です。
SDGsやエシカルファッション、サステナブルファッションという言葉を聞く機会が増えた昨今。改めてファストファッションとはどういうものなのか、良い側面や問題とされている点、ファストファッションとの上手な関わり方など、一緒に考えてみましょう。
そもそもファストファッションとは

「早く、安く、手頃な」食事がファストフードであるように、「流行の最先端をいち早く取り入れた、低価格で、程よい品質」のファッションのことをファストファッションと言います。
ファッションのサイクルは、大きく春夏シーズンと秋冬シーズンの年2回で分けられます。しかし、ファストファッションブランドでは、半年に1回ではなく、月や週など短いサイクルで新商品を絶え間なく導入しているケースが多くみられます。
ものづくりの仕組みとして生産ロットというものがあり、一度にたくさん生産する方が、少量生産より格段に単価が安くなります。そして人件費の安い国で生産するなどの要素によって、低価格な商品が実現しています。
ファストファッションの歴史

ファストファッションの始まりは、1990年代〜2000年代。
日本を代表するグローバルブランドとなった「ユニクロ」が1984年に広島に1号店をオープンし、1998年にフリースが評価され一気に名を上げました。同じくファーストリテイリング社のブランドである「GU」は2006年に誕生。他にも低価格を売りにした国内ブランドが人気を獲得し、国内アパレルの売り上げでも常に上位に位置しています。
ファストファッションの勢いが加速した理由として、海外ブランドの日本進出も大きく影響しています。「ZARA」は1998年に、「H&M」は2008年に、一昨年に再上陸を果たした「FOREVER21」は2009年に日本に上陸し、ブームの火付け役となりました。
新型コロナウイルス感染症が蔓延した2020年以降は、ラグジュアリーブランドのような高価格帯と、ファストファッションのような低価格の2極化が進んだと言われています。
中でも、SHEINやTemuといった、ファストファッションよりもさらに早くて安い「ウルトラファストファッション」が若者世代を中心に大ヒットするという現象が起きました。
ファストファッションが誕生した背景

数十年で一気に広がったファストファッションの背景には、どのような時代の変化があったのでしょうか。
1990年代以降、グローバル経済が進展し、製造拠点を人件費の安い国へ移すことが可能になったこと、それがファストファッションを支えている大きな柱と言えます。
バングラデシュ、中国、ベトナムなど、労働コストが低い国での大量生産がビジネスモデルを支えたのです。
また、輸送・物流の高速化により、世界中の市場に迅速に供給できるようになりました。
「今すぐ流行の服が欲しい」「たくさんの服を安く楽しみたい」という消費者のニーズも大きく関係しています。消費者のファッションに対する嗜好が多様化し、加速。それに応えたのがファストファッションでした。
また、近年はSNSでモデルやインフルエンサーが日々ファッションやコーディネートを発信することで、トレンドのサイクルが早まっていることもファストファッションが広まっている要因と考えられます。
ファストファッションのメリット

ここでは、現代のファッションを支えてきたファストファッションのメリットに目を向けていきます。
誰でも気軽にファッションを楽しめる
ファストファッションの大きなメリットとして、ファッションの大衆化が挙げられるでしょう。
もともとファッションは、限られた人だけが楽しめるものでした。例えば、オートクチュールのドレスは限られた一部の富裕層だけが身につけられるものであり、コレクションブランドのアイテムも同様、庶民が日常的に購入できるものではありませんでした。
しかし、流行の最先端のデザインを一般の消費者にも取り入れやすい価格で提供するファストファッションが隆盛・台頭したことにより、生活費の中から衣料品代に多くの支出を割かずとも、おしゃれを楽しめるようになりました。
サステナブルアクションにチャレンジしやすい
サステナブルな取り組みをしているブランドの商品は、「少し高い」と思われているのが現状です。
しかし、実はファストファッションブランドでも、再生繊維を使用したり、オーガニック繊維を使用したり、衣料品回収を行っていたりと、サステナブルな取り組みを行うブランドは多く存在します。これらの取り組みは日常の買い物の延長線上にあり、無理なくサステナブルアクションにチャレンジできます。
資本力がある企業が多いことにより、影響力が大きい
アパレル企業で売上高の上位を占めているのは、ファストファッションブランドを抱える以下のような企業です。
- 株式会社ファーストリテイリング
- インディテックス
- H&M
- Gap など
このような企業は大きな資本力を持っているからこそ、何かしらの取り組みをした際には、多くの人々にリーチできるのです。
例えば、ユニクロが取り組むウクライナの人々への支援活動や、ブランドのグローバルサステナビリティアンバサダーに緑色のドラえもんが就任したニュース、H&Mのリサイクルシステム「Looop」の導入など。有名企業がこのような取り組みを行うことで、業界や国を超えて、多くの人々にアパレル業界の取り組みを認知してもらえるチャンスが広がるのです。
ファストファッションの問題点

ファストファッションにはメリットがある一方で、デメリットや問題点も多く抱えています。ここからは、ファストファッションの問題点を見ていきましょう。
大量生産・大量消費・大量廃棄がもたらす環境への負荷
ファッション産業は、石油産業に続く世界2位の汚染産業と言われています。なぜこのような不名誉な称号を与えられてしまったのでしょうか。
その要因として、この20年ほどで商品価格が2分の1に、生産量が2倍になったことが挙げられます。これはすなわち、安価で大量に生産して、大量に消費し、売れなかった場合は大量に廃棄されることを意味します。
買う側としては、安く服を買えることは、嬉しいこと。しかし、1枚あたりの価格が下がったことにより、買っても着ない服や、すぐに飽きて着なくなった服が増えたと感じる人も多いのではないでしょうか。これが廃棄(手放す)量の増加に繋がっています。
廃棄された衣料品の中で、リユース・リサイクルされるものは30%強といったというデータもあります※。その中でも、リセール市場で価値の付かないものや、寄付を目的として回収されたものがグローバルサウスの国々へ運びこまれ、そこでも誰の手にも渡らず飽和し、ごみの山になっているなど、現地の環境に負荷を与えている現状も無視できません。
膨大な水資源の使用・水質汚染など環境への影響
化学繊維の生産・使用による水質汚染や膨大な水資源の使用も、大きな問題になっています。
環境省のデータによると、一着の服を作る際、2,300リットルの水を使用し、約25.5kgのCO2を排出することがわかっています。身近なもので例えると、浴槽11杯分の水、500ミリリットルのペットボトル255本を製造できるCO2の量です。
これは、現在流通している衣料品の素材として主流である化学繊維の製造時に、CO2の排出が多いことが関係しています。また、化学繊維は、洗濯時にマイクロプラスチックが流出することも問題視されています。
一方、天然素材が環境に優しいかと言えばそうとも言えないのも事実です。綿栽培には大量の水を必要とし、大規模に生産するとなると農薬や化学肥料の使用により土壌を汚染したり、生産者の健康を害してしまったりということも考えられます。
また、染色工程でも大量に水を消費するうえに、排水処理をきちんと行わないと、人体や環境に影響を及ぼす可能性のある成分が海や川に流出する危険性もはらんでいます。
環境負荷は製造時のみならず、産業構造にも起因しており、行程ごとに場所(国)を移すため輸出入が増え、その分輸送の際に排出するCO2の排出も多くなってしまうのです。
長時間労働や低賃金労働などの問題
世界規模の分業制である現代のビジネスモデルでは、環境への影響以外に「人」にも影響が及んでしまいます。
一着の洋服が作られる行程にはたくさんの人が関わっていますが、現在の産業構造では追跡が難しく、透明性が担保できません。私たち消費者から見えるのはタグに記載されている生産国だけ。生産国は最終工程の地を表記しているので、その前に誰がどこで何の加工をしたのかは、知ることができないのが現実です。
どんなに機械やAIが発達しても、洋服づくりに人の手を欠かすことはできません。原材料をつくるにも、生地をつくるにも、染めるのにも人が関わっています。
そして、服を形作る最も重要なパートである縫製に関しては、人がミシンを使って生地と生地をつなぎ合わせているのです。
こんなにも「人」が介在するからこそ、労働問題や人権問題も取りざたされてしまいます。ファッション業界の歴史のなかで、最も甚大で、世界を震撼させた事件が2013年にバングラデシュで起きてしまいます。
関連記事:悲劇から10年。エシカルファッションの原点、ラナ・プラザ崩壊事故とは
ファストファッションの製造を支える拠点の一つであった商業ビルが崩壊した「ラナ・プラザ崩壊事故」では、死者1,100人以上、負傷者2,500人以上にのぼりました。大半が若い女性だったといいます。
この悲惨な事故を契機に、消費者運動や協定が制定されるなど、今まで明るみにならなかった実情を改善すべく、世界中で様々な動きが起こりました。
勤務状況は適切か、賃金は正常に支払われているか、安全基準は遵守されているか、不当な扱いを受けていないか。サステナブルにファッションを楽しむためには、生産に携わる人々が無理なく働ける環境を整えることが重要です。
ファストファッションはどのくらい取り入れられている?
前述の通り、近年はSHEINをはじめとする「ウルトラファストファッション」が若者世代を中心に支持され、急成長を見せています。物価上昇が著しい中、安くておしゃれに見えるウルトラファストファッションはありがたい存在と言えるでしょう。
しかし、消費者は問題点を知らずに購入しているわけではないようです。Z世代をターゲットにした研究機関「デカボLab」が調査したところによると、ウルトラファストファッション購入経験のある人のうち、大半は環境への影響を知っているものの「安くてかわいい」に抗えないことがわかっています。
これは若者世代だけの話ではありません。2021年に消費者庁が行ったサステナブルファッションの意識調査(全国の15~69歳男女、2000人対象)によると、60代以上を除き、どの世代でもファストファッションでの購入率が最も高いことがわかりました。なお、ファストファッションの背景にある社会課題に対しては、年齢層が上がるにつれて認識が乏しいという結果がでています。
世界的に見ても、アパレル企業の売り上げ上位を占めるのはファストファッションブランドの運営会社であることから、いかにファストファッションが全世代的に浸透しているかがわかるでしょう。
ファストファッションに関する日本や海外の取り組み
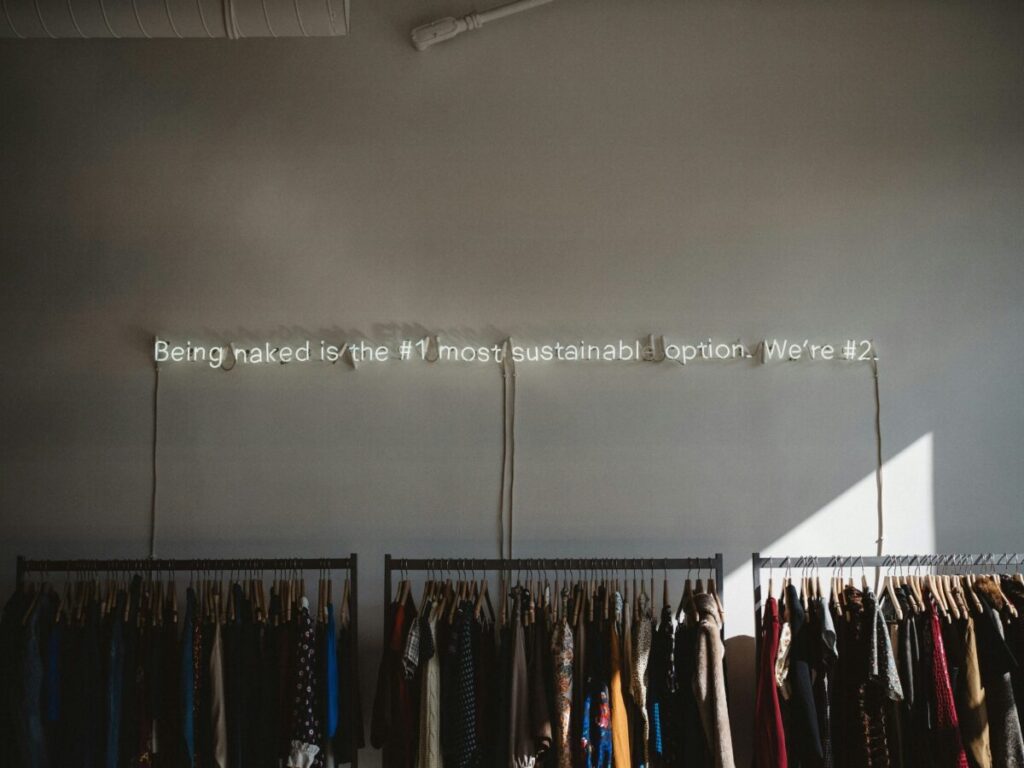
ここでは、環境省や世界各国で行われているファストファッションの問題を解決するために取り組まれている事例を紹介します。
環境省がサステナブルファッションのサイトを作成
2021年、サステナブルファッションの情報発信や啓発のためのオンラインサイトを環境省が作成しました。
https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/index.html
ジャパンサステナブルファッションアライアンス(JSFA)創設
サステナブルなファッション産業を推進するため、2021年に業界団体「ジャパンサステナブルファッションアライアンス(JSFA)」が発足されました。環境省などの行政をパブリックパートナーとし、伊藤忠ファッションシステムと一般社団法人unistepsが事務局を務めています。
https://jsfa.info/news/established-press-release
フランスのファストファッション規制
2024年3月にフランス国民議会(下院)で、ファストファッションを規制する法案が全会一致で可決されました。当初は2025年1月に施行される予定でしたが、審議の延期が重なり、2025年6月に上院で可決されました。
ファッション協定
ファッション業界が協力しあって、「生物多様性」「気候変動」「海洋」の環境負荷低減の目標達成に向かうために「ファッション協定」が締結されました。
日本企業ではスポーツアパレルの「アシックス」、ブランド品買取のなんぼやをはじめとする循環型企業「バリュエンス」、THE NORTH FACEなどのアウトドアブランドを束ねる「ゴールドウイン」の3社が加盟しています。
繊維·縫製産業における健康と安全のための国際協定
ラナプラザ崩落事故から1ヶ月後に策定され、悲惨な事故を繰り返さないために欧州のブランドなどで締結された「バングラデシュにおける火災および建物の安全性に関する協定(the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh)」。
これを引き継ぐ形で、2021年に締結された新協定が「繊維·縫製産業における健康と安全のための国際協定(International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry)」です。ユニクロを有するファーストリテイリング社も署名しています。
ファストファッションとの上手な付き合い方
ファストファッションの問題点を紹介しましたが、決してファストファッションブランドが悪者というわけではではありません。実際に私たちにとって便利で欠かせない存在です。
ファストファッションの服も、ワンシーズンで着られなくなるような脆い服ばかりではありません。たくさん着て、気を使わずに洗濯もでき、耐久性が高いものが多いと感じる人がほとんどではないでしょうか。
ワンシーズンで処分しようと思っていた服をもう1年長く着ると、日本全体で約3万トンの廃棄削減に繋がると言われています。
ファストファッションブランドの服も、コートなどのアウター類はクリーニングに出したり、ニット類はこまめにブラッシングをしたり、洗濯はネットに入れてあげたりするだけで、十分に長持ちします。
ライフサイクルアセスメントの面でも考えてみましょう。現代の日本の四季を乗り越えるには欠かせない機能性インナーは化繊であり、製造時にCO2が排出されます。しかし、着用時に冷暖房の過剰使用を抑えられることで、エアコン使用時に排出されるCO2の削減に繋がると考えることもできるのです。
大切なのは、「ファストファッションだから」と短いサイクルで消費せず、丁寧に扱うこと。そして、ファストファッションを取り入れることで得られる効果や気持ちの高まり、コストパフォーマンスなどを総合的に見て、価値を判断することではないでしょうか。
※ライフサイクルアセスメント(LCA):製造から使用、廃棄までの商品の寿命に対する環境負荷を評価すること
ファストファッションをサステナブルに楽しもう
ファストファッションを取り入れることで、知らず知らずのうちにサステナブルアクションの第一歩を踏み出していることもあります。
オーガニックコットンやリサイクルポリエステルを原材料に採用したり、不要な衣類を回収したり、自社製品のリサイクルに取り組んでいたり。ファストファッションのサステナブルな取り組みが加速しています。
ファストファッションかどうかに関わらず、環境や人により良いものを選ぶことを意識してみませんか。
参考:
海外ユニクロにもひろがる難民支援|ユニクロ、
緑の『ドラえもん』がグローバルサステナビリティアンバサダーに就任|ユニクロ
H&M、リサイクルシステム「Looop」で不要な衣類を新たなファッションアイテムに変換|PR TIMES
SUSTAINABLE FASHION|環境省
【Z世代の環境意識調査】ウルトラファストファッションの誘惑に揺れるZ世代。環境影響を認識しつつも半数以上が続ける「ごめんね消費」をデカボLabが調査|PR TIMES
「サステナブルファッション」に関する消費者意識調査|消費者庁