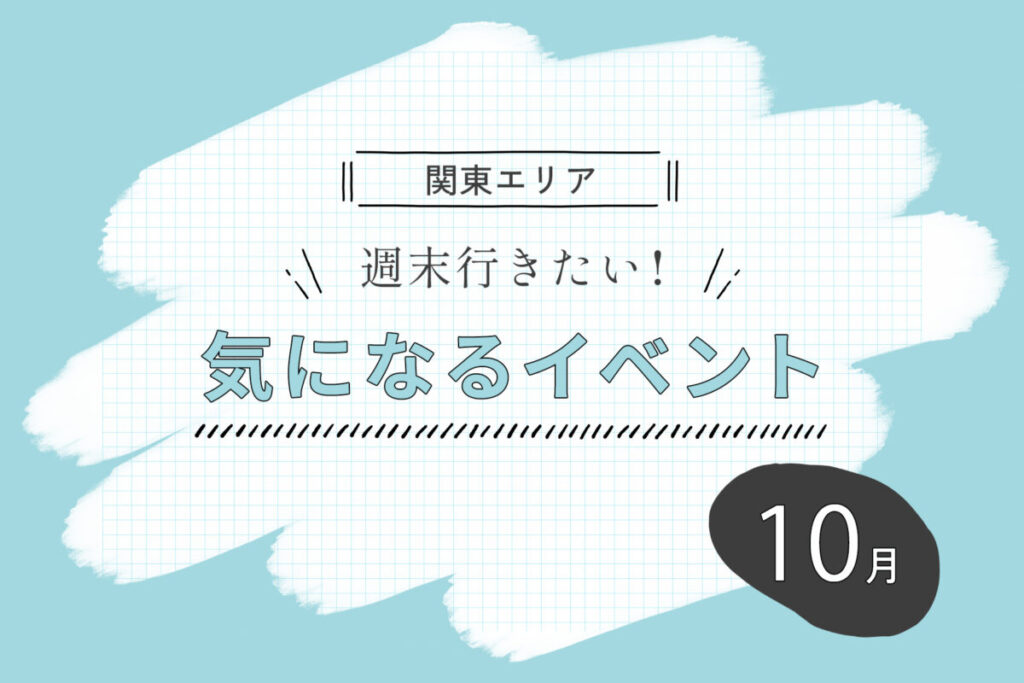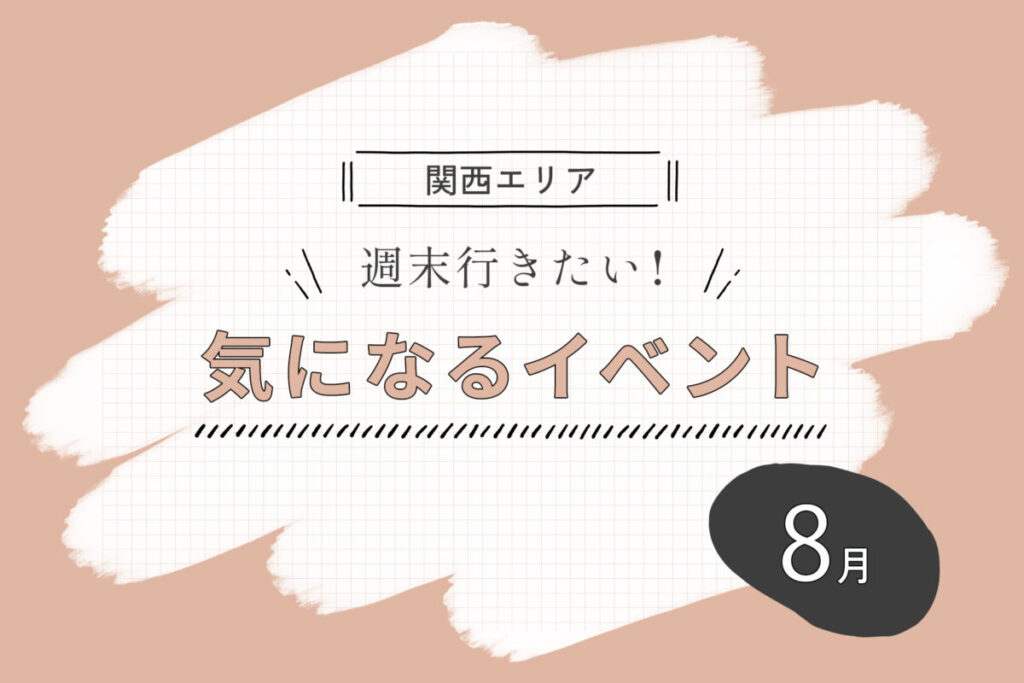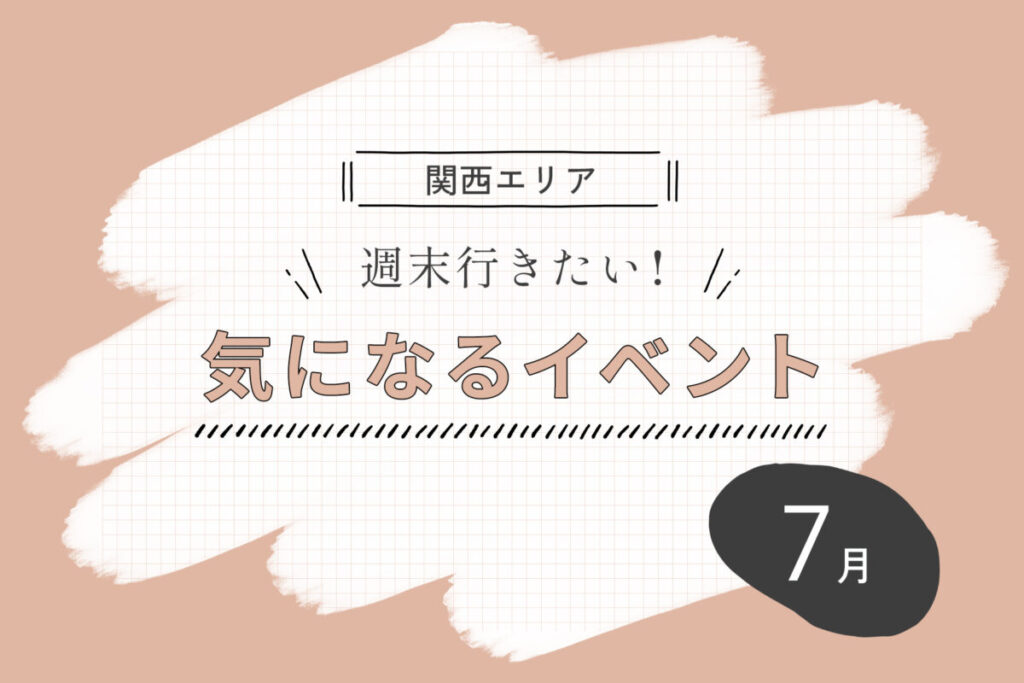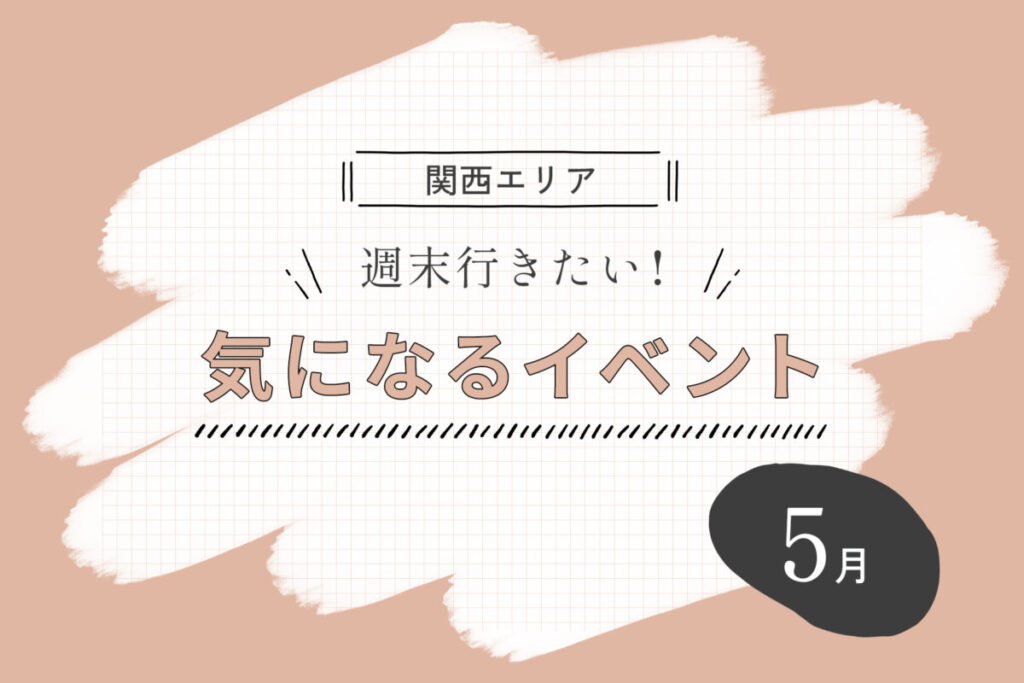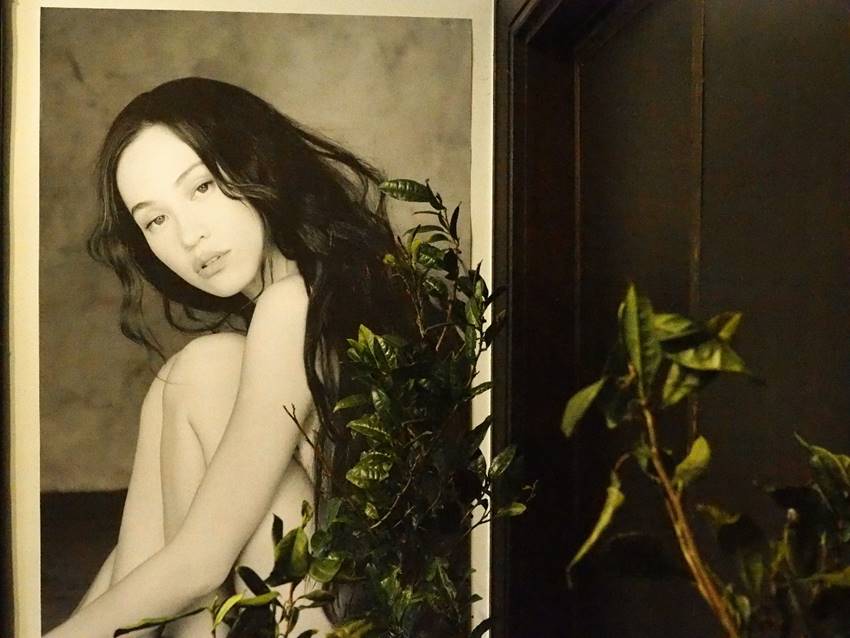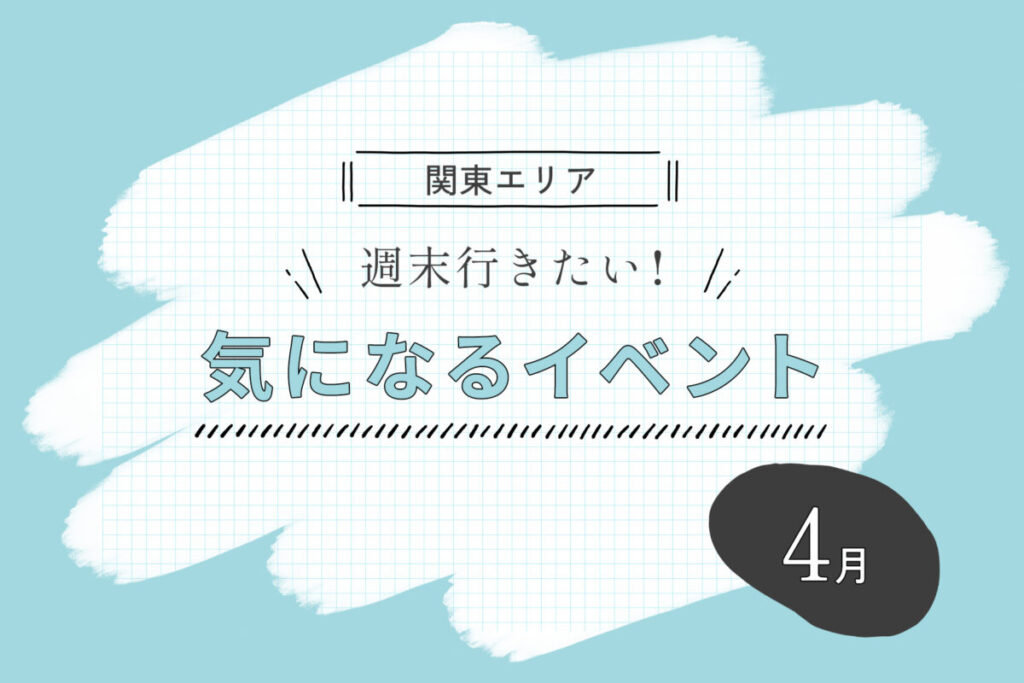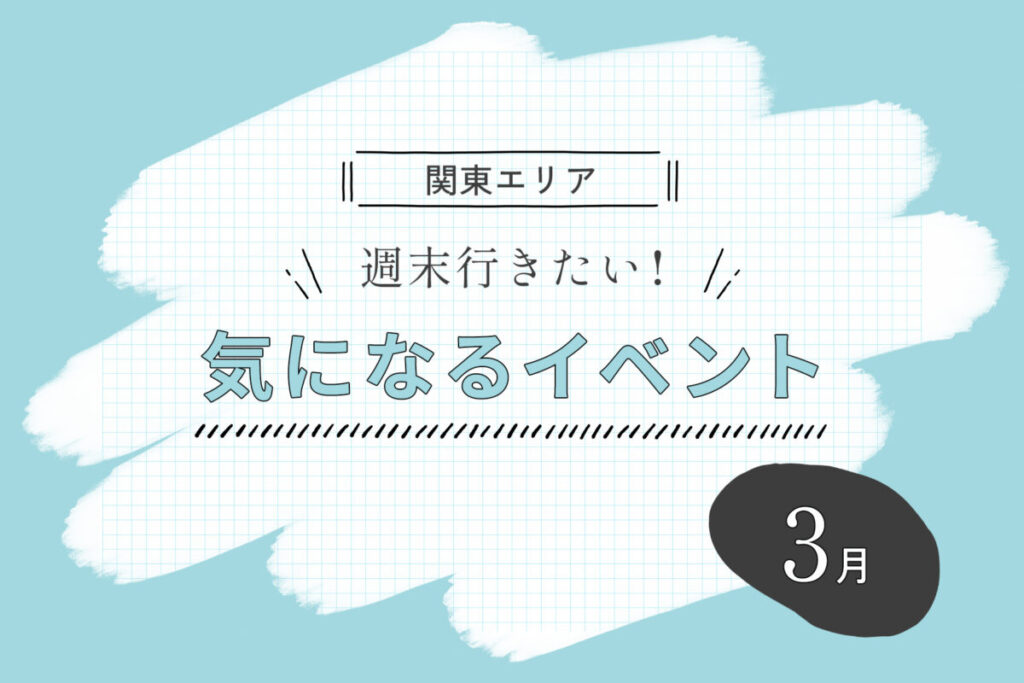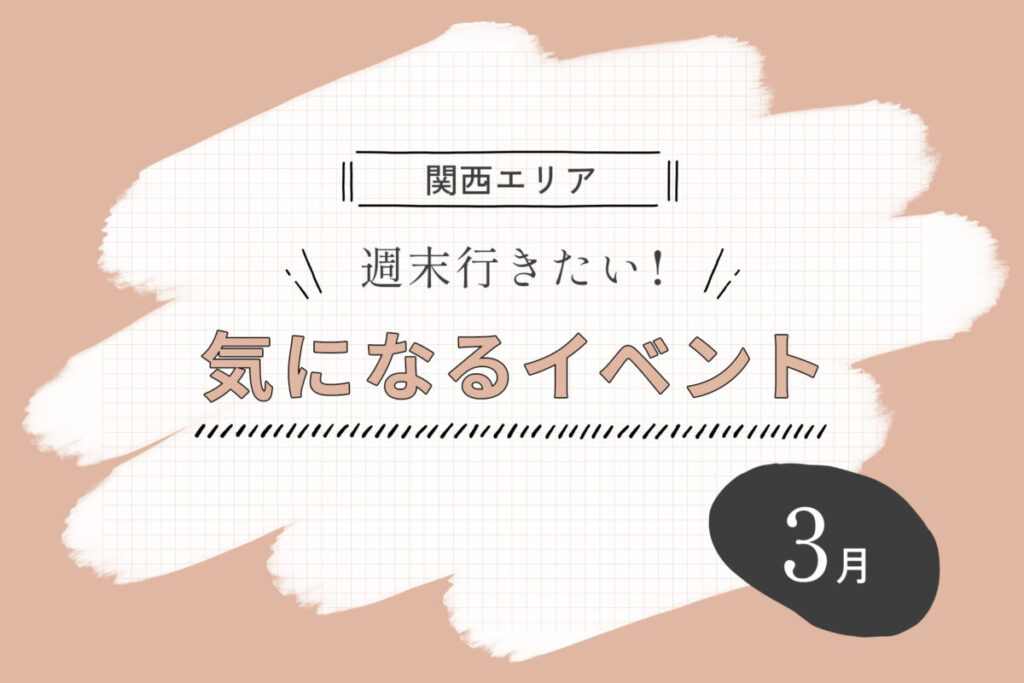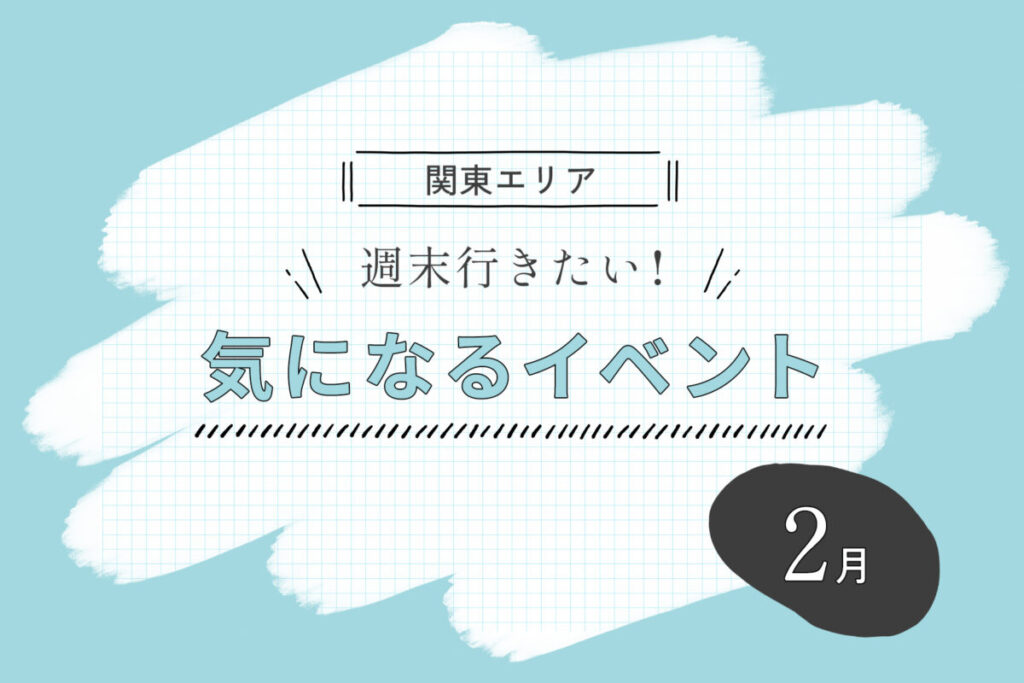アップサイクル– tag –
-

豊かな海と食文化を守りたい。厄介者の魚のウロコが華やかなファッションになるまで
-

CACL×LIXIL×永山祐子建築設計が能登半島地震で廃材となった黒瓦をアップサイクル
-

【2025年10月】週末行きたい!気になるイベントin関東
-

【2025年8月】 週末行きたい! 気になるイベントin関西
-

【2025年】暑中見舞い、何を贈る?夏に喜ばれるエシカルな贈り物まとめ
-

アートの街・大阪北加賀屋。「SMASELL Sustainable Commune」でSDGsな衣食住を楽しむ
-

生産者や環境に配慮。全国の美味しいものが集まる代官山の“Tide&Taste”
-

【2025年7月】 週末行きたい! 気になるイベントin関西
-

使い捨てプラスチックは何が問題? 日常生活で今できることを紹介
-

世界最先端の食が知れる、食べれる!新虎エリアの注目カフェ「サステナブルフードミュージアム」
-

【2025年5月】 週末行きたい! 気になるイベントin関西
-

【サステナブルコスメアワード受賞】水原希子さん本人が語る、kiiksに込めたエシカルマインドとは?
-

【2025年4月】 週末行きたい! 気になるイベントin関東
-

日本工芸品の魅力を再発見。ずっと大切にしたい食器に出会える「HULS Gallery Tokyo」
-

ソーシャルプロダクツ・アワード2025が決定。能登半島地震復興につながる商品・サービスなどがテーマ
-

【2025年3月】 週末行きたい! 気になるイベントin関東
-

【2024年3月】 週末行きたい! 気になるイベントin関西
-

渋谷で古紙から3,580個のトイレットペーパーを生産。サステナブルツーリズムの実現へ
-

【2025年2月】 週末行きたい! 気になるイベントin関東
-

みかんの皮お風呂はピリピリする?安心して楽しむための作り方と注意点