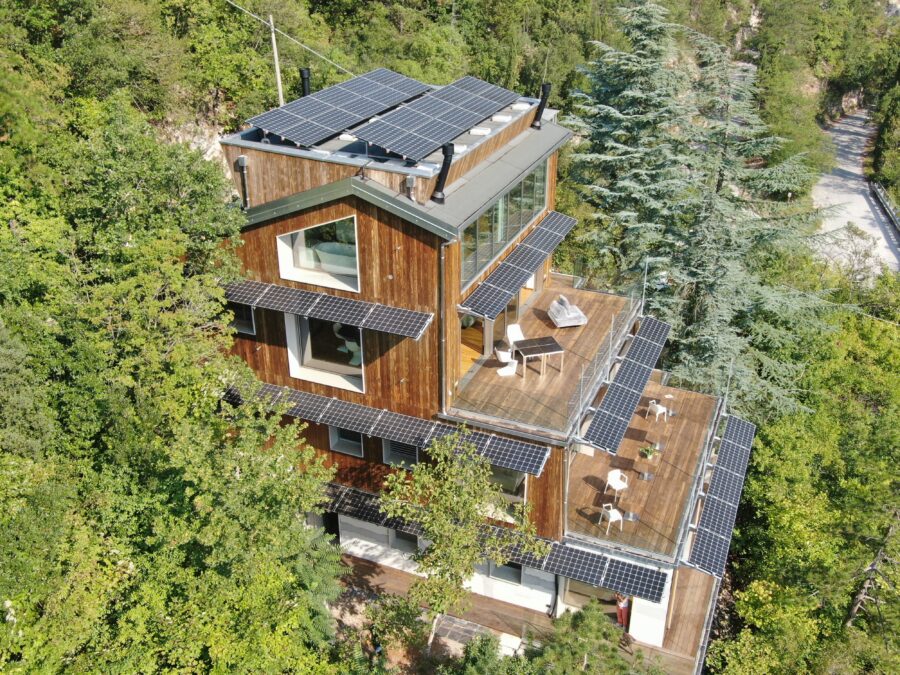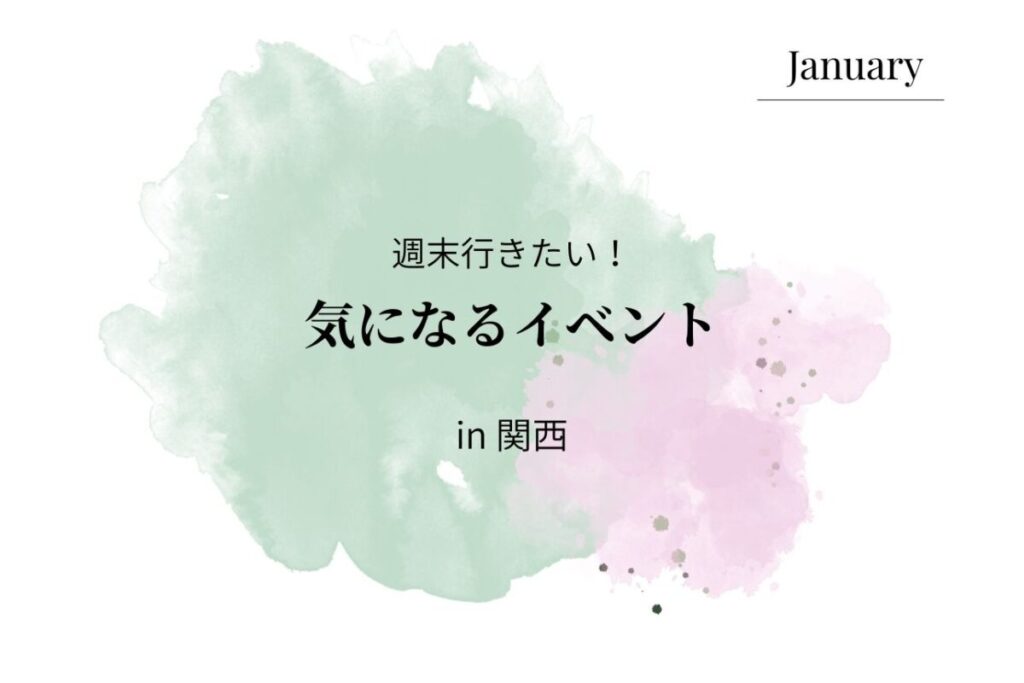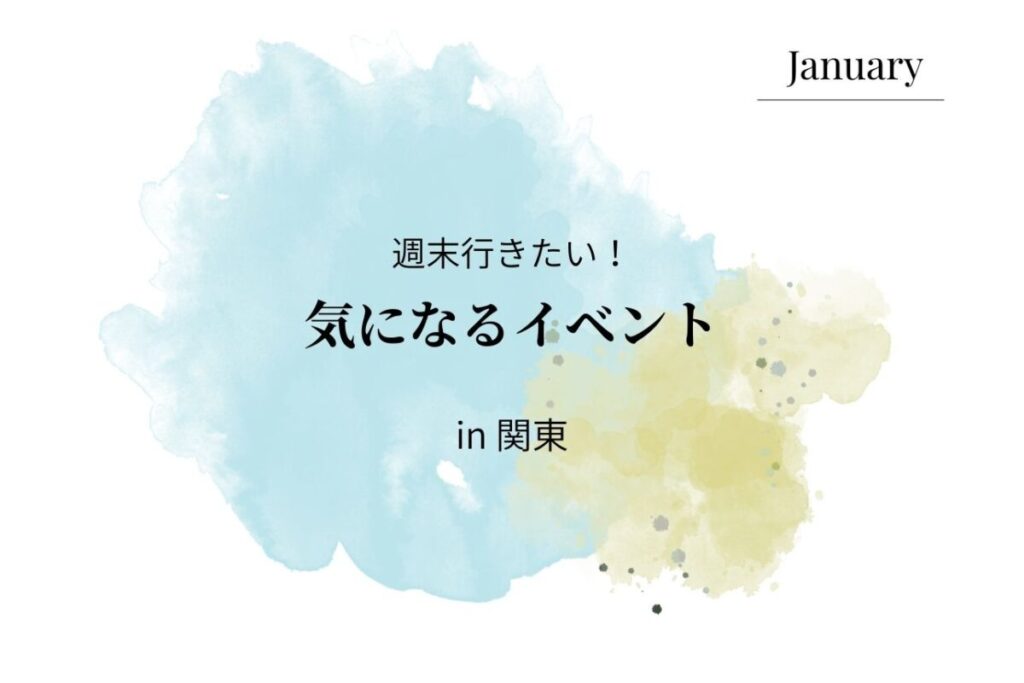日本では、令和元年に「食品ロス削減推進法」が制定され、食品ロスに関する認識が広まりつつあります。食品ロスは日本に限らず他国も抱えている大きな問題で、国や都市、企業や団体が主体となり、食品廃棄に対して、様々な施策が行われています。
今回は、行政や民間に関わらず、世界で行われている食品ロス削減の取り組みをご紹介します。
世界の食品ロスの現状は?
今、世界の食料廃棄量は年間13億トン近くにのぼり、生産された食料の約1/3は廃棄されているのが現状です。食品ロスは、まだ食べられるものを無駄にしているだけでなく、焼却処分の段階でCO2を排出するなど、環境にも負荷をかけています。
企業やレストランがうまく食材を使いきるよう努力することや、消費者一人ひとりが食べ物を無駄にしないという意識を持つことが大切になっています。
関連記事:家庭から減らそう。食品ロスの現状と私たちにできること
関連記事:気軽に食品ロス削減に貢献。お得で楽しいショッピングサイト10選
先進国から新興国まで。世界の食品ロス対策
コンビニなどでの手前取りが広がり、食品ロス削減のためのショッピングサイト等が増えてきている日本ですが、海外ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。ヨーロッパからアジアまで5つの国を見ていきます。
デンマーク

サステナブル意識が高い国として知られるデンマークですが、少し前では食品ロスが多く、問題になっていました。
デンマークではある女性の活躍により、食品ロスが劇的に減少しています。セリーナ・ユールさんは、食品が大量に捨てられていくデンマークの現状をどうにかしたいと2008年に「Stop madspild(食品ロスを止めよう!)」と銘打ってSNSなどで活動を開始。活動は政府や王室をも動かし、5年間でデンマークの食品ロスを25%も削減することに成功したのです。
関連記事:世界中が注目。豊かな社会へ導くチェンジメーカー7人
デンマークでは、wefood(ウィーフード)という世界で初めての「食品ロス専門食品スーパー」も登場しています。賞味期限が過ぎている、ラベルが間違っている、パッケージが破損しているなどの理由で、通常のスーパーマーケットでは販売できなくなった商品を取り扱うスーパーです。
さらにToo Good To Goというアプリが誕生。今では、国境を越え、ヨーロッパをはじめとした国々に広がっています。アプリでは、飲食店で残ってしまったものを安く引き取ることができます。中身は受け取ってからのお楽しみ、というワクワク感もあるサービスです。
アメリカ

以前よりアメリカでは、持ち帰り用のバッグ、通称「ドギーバッグ」が人々に定着しています。これは、レストランなどで食べきれなかった食事を袋に詰めて持って帰るという文化。
どのレストランでも必ずと言っていいほどドギーバックが用意されており、余ってしまった食事を気軽に持ち帰ることができます。
アメリカ政府としては、農務省と環境保護庁が食品ロスを2030 年までに50%削減するという目標を発表。「US Food Loss and Waste 2030 Champions」というプロジェクトで民間企業と一緒に食品ロス削減に取り組んでいます。賛同する企業にはアマゾンやスターバックスコーヒーなど大企業も名を連ねています。
オーストラリア

国が2030年までに食品ロスを半減させるという目標を公言しているオーストラリア。2004年に設立されたOzHarvestは、企業から寄付してもらった余剰食品を食べ物に困っている人に届ける活動や、学生向けに健康的な食事や廃棄を出さない料理などを学べるプログラムを実施するなど、様々な方面から食品ロスにアプローチしています。
OzHarvestが運営するマーケットでは、余剰食品を販売。販売と言っても価格が決まっているわけではなく、購入者が価格を決めることができるので、どんな人でも購入しやすくなっています。
タイ

食品ロスに対する取り組みは、先進国だけでなく新興国でも始まっています。
国民一人あたりの年間食品廃棄量は約254㎏とヨーロッパの国と比べて食品ロスが多く、食品ロスに対する法整備やサプライチェーンもまだ整備されていないタイですが、その中でも食品廃棄物を削減の意識は少しずつ広まりつつあります。
面白い取り組みとしては、ナーケー郡、ナコーンパノム県で始まった、行政主導の「ミミズコンポスト」があります。ミミズによる生ごみ処理ができるコンポストを家庭に設置し、生ごみをオーガニックの堆肥にする取り組みです。
生ごみを焼却するのではなく、土に戻すことができるコンポストは、そもそも余分な生ゴミを出さない行動にも繋がります。
他にも、廃棄になりそうな食品をアプリで購入できるサービスが始まるなど、食品ロス削減の意識が広まりつつあるタイ。今後も新たなムーブメントが生まれてくるのではないかと思われます。
インド

もうひとつ新興国の例を見てみましょう。
インドは、世界でも最大の食糧生産国ですが、一方で収穫された農作物の約30%が廃棄されているとされています。
そんな中でも、国民の関心を集めたひとつのアイデアがあります。
インド南部にあるタッタダバタレストランでは、店先に「nanma maram(=善意の木)」という冷蔵庫を設置。冷蔵庫の中には、まだ食べられるのに廃棄になってしまうはずだった食事が入れられています。
以前から食品ロスに心を痛めていたオーナーが、廃棄になってしまう食事を、ホームレスなど食べ物にありつけない人に提供しようと始めた活動です。冷蔵庫は誰でも開けることができ、24時間自由に食べ物を持ち出すことができます。
このアイデアの反響は大きく、今では設置したレストランに加えて、近隣のレストランからも食事が届けられるそうです。
世界規模で始まる食品ロス削減の動き
食品ロスは、資源を浪費しているだけではなく、ゴミとして燃やすときのCO2排出など自然環境にとっても大きなダメージとなります。また、十分な食糧にありつけない人がいる中で、食糧を無駄にせず、よりたくさんの人にいきわたらせることが大切です。
国によって現状は違っても、「食糧を無駄にせず、食べるものに困っている人にも食糧を平等に行きわたらせる」というという認識は、世界でどんどん広がっています。
わたしたちも、学べることは他国から学びながら、今日からできることを改めて確認していきたいですね。